今のマメトラ管理機はオンボロで大きいので、サブで使う小型のミニ耕運機を買いたいと思案中です。
我家の家庭菜園の面積は、約100坪(330m2)。家のすぐ隣のリンゴ畑の片隅で作っているので、料理中にあの野菜が足りないとなっても、直ぐに採りに行けるので、とても便利です。 ただ、この他に、今まで人に貸していた2枚の畑を返されてしまったので、併せて約300坪、つまりほぼ1反分(300坪、約1,000平方メートル)の野菜畑を耕さねばなりません(汗)。
耕運機で耕せる面積の目安はどのくらいでしょう?。カタログによると、ホンダの小型耕運機の速度(スピード)は、前進低速時で0.2m/s~0.3m/s。間をとって速度0.25m/sとし、耕幅を500mmとすると、1分間で耕せる面積は 0.25m/s×0.5m×60秒=7.5m2。1時間で、450m2となります。
ただし、実際には同じ場所を2度くらい耕す重なりと、旋回時間や石を拾ったりする作業ロスの時間を見込むと、この半分から3分の1くらいになってしまうでしょうか。そうすると、凡そ1時間での実作業は、約50~60坪(約150~200m2)前後と見込むのが妥当そうです。
すると、1反分全部を耕すには、休憩時間なしで5~6時間もかかってしまいます(汗)。
 今使っている耕運機は、マメトラの「SRV35D」、積んでいるエンジンはG510LN型という、超年代的な代物。フロントロータリー式の管理機で、左側のクラッチレバーのワイヤーが切れているので、左旋回時には力技が必要だったり、耕うん高の切り替えレバーが錆びついて蹴飛ばさないと動かなかったり、数日使わないでいると、なぜか燃料タンク内のガソリンが消えて無くなってしまいます。漏れている形跡は無いのですが…。それでも使えているのが立派です。今の機械は直ぐに壊れてしまいますが、昔の機械ほど、本当に丈夫で長持ちします。最近の機械は、耐用年数が過ぎたら、ちゃんと壊れる仕掛けがしてあるんじゃないかと、疑いたくなってしまいます。まぁメーカーも、何十年も買い替えずに使われるより、頻繁に買い替えてもらった方が儲かりますからね~。
今使っている耕運機は、マメトラの「SRV35D」、積んでいるエンジンはG510LN型という、超年代的な代物。フロントロータリー式の管理機で、左側のクラッチレバーのワイヤーが切れているので、左旋回時には力技が必要だったり、耕うん高の切り替えレバーが錆びついて蹴飛ばさないと動かなかったり、数日使わないでいると、なぜか燃料タンク内のガソリンが消えて無くなってしまいます。漏れている形跡は無いのですが…。それでも使えているのが立派です。今の機械は直ぐに壊れてしまいますが、昔の機械ほど、本当に丈夫で長持ちします。最近の機械は、耐用年数が過ぎたら、ちゃんと壊れる仕掛けがしてあるんじゃないかと、疑いたくなってしまいます。まぁメーカーも、何十年も買い替えずに使われるより、頻繁に買い替えてもらった方が儲かりますからね~。
しかし、普段ちょっと耕すには大きいし、力が要ります。それに、フロント・ロータリー式の管理機は、進むタイヤの回転とは逆に、ローターは下から向こう側へ回転して、土を耕します。そのため、土を起こすと同時に、土を向こう側へと押しやってしまうので、土寄せ作業をするには便利ですが、ただ耕うんする場合には、場所によって土量(土の高さ)が違ってしまいがちです。広い畑を耕す場合であれば大した問題ではありませんが、狭い1~2か所の畝を耕す場合などは、後で手作業で土を動かして均す作業が必要となってしまい、それが結構重労働だったりします(汗)。
そこでサブ用に、時々狭い場所を耕す時に使える、小型の管理機(ミニ耕運機)を買ってみようと思案中です。
最近は、「ミニ耕運機」どころか、もっと小さな「プチ耕運機」なるものが登場しています。エンジンではなく、バッテリー式の電動なので、軽くてコンパクト。価格も、例えば「高儀 GREEN ART 電動耕うん機 菜援くん 800W GCV-110」(左)なら、amazonで¥16,874(税込、送料込み)と、格安です!。
しかし、さすがにプチ耕運機で、100坪からの菜園を耕すには無理があります。そこで、私の購入候補は、車軸式の小型orミニ管理機で、10万円前後のものです。しかし、その大きさと価格に絞ってもなお、各メーカーから様々な耕運機が発売されており、どれがいいのか分かりません。そこで、気になる馬力や重量の違いなどを、横並びで比較できるよう、主だったメーカーのおすすめ耕運機を一覧表にしてみました。
耕運機を買おうと思って、まず気になったのが、「耕運機」と「管理機」の違いです。あと、「耕耘機」(こうてんき?)って何?という疑問も…。
まず、耕耘機は『こううんき』と読みます。『こうてんき』と読んだのは、私の単なる無知でした…(汗)。田畑を耕す(たがやす)ことを、”耕(こう)うん”すると言いますが、それを正しくは漢字で「耕耘」と書きます。
 「耘」という漢字は、音読みで『ウン』、訓読みで『くさぎ(る)』と読みます。耘る(くさぎる)とは、『田畑の土をまぜかえして、雑草をとり、土の間に空気を入れる作業のこと』だそうです!。
「耘」という漢字は、音読みで『ウン』、訓読みで『くさぎ(る)』と読みます。耘る(くさぎる)とは、『田畑の土をまぜかえして、雑草をとり、土の間に空気を入れる作業のこと』だそうです!。
しかし、「耘」なんて漢字は、私の様に読めない日本人が大勢います。そこで日本新聞協会が設置している新聞協会用語懇談会が、普段は「耕耘機」を「耕運機」と代用表記することに決めたため、今では「耕運機」の方が日常的に使われる機会が増えてしまいました。ちなみに、クボタやヰセキなど耕耘機メーカーでは、多くの場合、「耕うん機」と平仮名で表記しているようです。
 耕耘機(=耕運機、こううんき)とは、田んぼや畑を耕すために用いられる農業機械の1つです。主にロータリーによる耕耘を目的としたものが多いため、英語の Rotary tiller から、ティーラーもしくはテーラーと呼ばれることもあります(ウィキペディアより)。
耕耘機(=耕運機、こううんき)とは、田んぼや畑を耕すために用いられる農業機械の1つです。主にロータリーによる耕耘を目的としたものが多いため、英語の Rotary tiller から、ティーラーもしくはテーラーと呼ばれることもあります(ウィキペディアより)。
耕耘機は、1920年頃に、オーストラリア人のハワードさんが発明したんだそうです。蒸気トラクターの動力を使って、L字型の金具を回転させることで、土を耕す仕組みを考え付きました。つまり、耕うん機の原型は、トラクターですね!。基本的には、エンジンを積んだ車体が、連結された耕すローターを後ろに曳いて、田畑を耕していく機械のことを、「耕耘機」(耕うん機)と呼びます。
当初の耕耘機は、トラクターの小型版とはいえ、大型のものでした。田畑の土を耕すことを主目的としていましたから、それなりのパワーも当然必要です。その後、耕耘機は、土を耕す目的だけでなく、様々な「アタッチメント」(付属作業機)を取り付けたり取り替えたりすることで、畝を立てたり、マルチ(シート)を被せたり、播種(はしゅ、種まきのこと)や除草、整地作業をする目的でも使われるようになりました。
 日本でも耕耘機が普及するようになると、日本の農業機械メーカーは、日本の農業に合う様に、大規模農家向けにはトラクターを主力製品として開発販売を進め、小規模な畑作用には、より小型化しながら、土の耕うん目的だけでなく、畝を立てたり中耕したりマルチ掛けが出来たりと、畑の様々な”管理”を任せられる、より汎用的な機械を開発販売するようになりました。これが、「管理機」の誕生です。英語では、CULTIVATOR(カルチベーター)と呼ばれています。
日本でも耕耘機が普及するようになると、日本の農業機械メーカーは、日本の農業に合う様に、大規模農家向けにはトラクターを主力製品として開発販売を進め、小規模な畑作用には、より小型化しながら、土の耕うん目的だけでなく、畝を立てたり中耕したりマルチ掛けが出来たりと、畑の様々な”管理”を任せられる、より汎用的な機械を開発販売するようになりました。これが、「管理機」の誕生です。英語では、CULTIVATOR(カルチベーター)と呼ばれています。
したがって、「耕うん機」も「管理機」も、意味的には特段の違いはありません。農業機械メーカーが、『今度の耕うん機は、以前の耕うんを主目的とした大型の”耕耘機”ではない、小型で、より便利で、どんな作業にも使える、扱いやすい機械ですよ!』、『畑の管理作業は、これ1台に全てお任せ下さい!』という宣伝目的で冠した名前が、「管理機」というわけです。まぁ例えるなら、”オーブン”と”グリル”の違いとか、”オーブン”と”オーブントースター”の違いのようなものでしょうか?(笑)。
ところで、耕うん機や管理機には、昔からのロータリー式(リア式)と、フロント・ロータリー式がありますが、どっちが家庭菜園で使うにはいいのでしょうか?
 後ろにロータリーを曳いた形の「リア・ロータリー式」は、耕うん機が開発された当初から使われてきた形です。エンジンの重みで、土を耕すロータリーを地面に押し付けながら曳くことで、深く安定して耕すことが出来るメリットがあります。力学的にも至極理にかなった、一般的な普及タイプの耕うん機の形です。パワフルに、より細かく土を粉砕できる点でも優れています。
後ろにロータリーを曳いた形の「リア・ロータリー式」は、耕うん機が開発された当初から使われてきた形です。エンジンの重みで、土を耕すロータリーを地面に押し付けながら曳くことで、深く安定して耕すことが出来るメリットがあります。力学的にも至極理にかなった、一般的な普及タイプの耕うん機の形です。パワフルに、より細かく土を粉砕できる点でも優れています。
しかし、デメリットもあります。回転する爪(刃)が付いたローターリーが、耕うん機を操作する人の足元にあるので、往々にして足を巻き込まれ、ケガをする人が出てしまいます。特に昔は、バック時に爪を逆回転させる均し作業で、ケガ人が多発したようです。そこで今では、安全上、汎用のリア式耕うん機は、バック時にはロータリーが回転しない仕組みになっています。しかし、それでも時々、足を巻き込まれる事故が、今も起きてしまっているのが現状のようです。
 一方、前側に付いたロータリーを押す形の「フロント・ロータリー式」は、ロータリーを地面に強く押し付け、土を深く安定して耕すには不利な形ですが、足元にロータリーが無い分、安全面では有利です。もちろん、操作する人が失敗やミスをすれば、大ケガに繋がり兼ねない危険な機械であることに、変わりはありませんが…。
一方、前側に付いたロータリーを押す形の「フロント・ロータリー式」は、ロータリーを地面に強く押し付け、土を深く安定して耕すには不利な形ですが、足元にロータリーが無い分、安全面では有利です。もちろん、操作する人が失敗やミスをすれば、大ケガに繋がり兼ねない危険な機械であることに、変わりはありませんが…。
また、フロント式だと、畑の隅や端を耕しやすくなります。車体の後ろにロータリーが付いたリア式だと、畑の隅を耕す場合、耕うん機を一旦畦まで上げるか、バックして畦に寄せないと耕せません。さらに、フロント式は、重いエンジンを積んだタイヤ部が後ろにあることで、耕うん機の向きを変えたい時に、フロント部分のロータリーを軽い力で持ち上げることができ、ロータリーを回したまま旋回が簡単に出来るメリットもあります。デメリットとしては、上述したとおり、土を前に押して行ってしまう事です。また、価格がリア式より総じて高めで、同程度の能力の機種で比べると、値段的には不利です。
 最近は、より小さい”ミニ耕うん機”と呼ばれる、「車軸ローター式」の管理機が登場し、人気が出てきています。
最近は、より小さい”ミニ耕うん機”と呼ばれる、「車軸ローター式」の管理機が登場し、人気が出てきています。
最大の特徴は、小型で軽量なこと。軽トラックが無くても、ハンドルを畳めば、小型のワンボックスやバン型の軽自動車の荷台(トランク)にも積める大きさです。値段も安く、10万円を切る製品もあって、家庭菜園で使うには、とても助かります。
ただし、タイヤが付いていないので、道路を移動させたり、安定して耕すには、コツが必要です(移動用に、補助輪や移動車輪のアタッチメントはあります)。操作に慣れていないと、力任せに抑えつけようとして、特に非力な女性には、最初は扱い難いかもしれませが、逆に慣れてくると、タイヤが付いていない分、抵抗棒を土に深く刺すことで、わざと同じ場所に留まって深く細かく耕したり、抵抗棒を浅くすることで、早く浅く耕したりということが出来て、便利に使えるようになります。また、フロント・ロータリー式の様に、土を押して行ってしまうこともありませんし、パワーも重量も限られるので、リア式ほど危険でもありません。
最近、特に注目を浴びているのが、さらに手軽さを追求した、充電式(バッテリー式)の管理機や、家庭用のカセット式ガスボンベを燃料とした耕うん機です。もちろん、ガソリンエンジンを積んでいないので、さらに軽量でコンパクトになっています。充電式は、エンジン式に比べて排気ガスを出しませんし、音も静かなので、都会の真ん中で家庭菜園をする人には、好都合でしょう。
ただし、特に充電式の機械は、エンジン式と比べると、パワーが非力な面は否めません。また、連続使用時間が短いので、一度に広い面積を耕すことが出来ません。
マキタの「MUK360D」(メーカー希望小売価格 113,300円)の場合、1本のバッテリーで作業できる時間は約15分です(約60分の満充電時、最大2本搭載時は合計で約30分)。最大出力は720W。動力的には、1kW=1.36ps(仏馬力)ですから、馬力に換算すると、最大出力は約1ps。例えば、ホンダのガソリンエンジン式耕うん機シリーズの中で一番小さな「プチな FG201
![]() 」(メーカー希望小売価格 79,970円)の最大出力は 1.6kw(=2.2ps)ですから、その半分以下の最大パワーということになります。
」(メーカー希望小売価格 79,970円)の最大出力は 1.6kw(=2.2ps)ですから、その半分以下の最大パワーということになります。
一方、家庭用カセットボンベで動く、ホンダの「ビアンタ FV200」(メーカー希望小売価格 112,970円)は、1本のカセットボンベで約1時間の連続作業が可能だそうです。パワー的には、最大出力(馬力)が1.1kw(1.5ps)と、排気量50ccのガソリンエンジン式「プチな FG201」と、マキタの「充電式耕うん機 MUK360DWB」との、ちょうど中間ですね。
充電式にカセットボンベ式、何れも大きな働きを期待するのは無理ですが、高齢者や非力な女性が、家庭菜園を楽しむには、あったら便利なことは確かでしょう。
日本は、技術立国であると同時に、農業先進国でもあり、農業機械のメーカーがとても数多くあります。耕うん機や管理機を生産・販売するメーカーは、井関農機(ヰセキ)、ヤンマー、クボタ、本田技研工業(ホンダ)、マメトラ農機、三菱マヒンドラ農機、やまびこ(旧・新ダイワ工業と共立が合併、エコーブランドも)、マキタ、オーレック、片倉機器工業、関東農機、日立工機、旭陽工業、ニッカリ、リョービ等と多彩ですが、一般的にホームセンターで購入できる農機のメーカーは数少ないのが現状です。
 ホームセンターや通販で買える、主だったメーカーとしては、クボタ、ホンダ、リョービ、イセキなど。数は少ないですが、三菱マヒンドラや、やまびこ(新ダイワや共立)、ヤンマーの耕うん機や管理機も見かけることがあります。
ホームセンターや通販で買える、主だったメーカーとしては、クボタ、ホンダ、リョービ、イセキなど。数は少ないですが、三菱マヒンドラや、やまびこ(新ダイワや共立)、ヤンマーの耕うん機や管理機も見かけることがあります。
一方、地方の農家の多くは、農協(JA)や、地元の農機具専門の商社や卸し問屋から購入しています。なぜなら、壊れた時の修理や、消耗品パーツの入手ルートの確保が欠かせないからです。しかし、一年間に動かす回数が限られる家庭菜園での耕うん機の使用であれば、こうしたアフターフォローやメンテナンス機会の必要性は、極端に少なくなるので、ホームセンターやインターネットの通信販売等で、格安で購入するというのも、あながち悪くない選択肢だと、私は思います。少々のトラブルであれば、自分で調べて対応できる自信もありますし、汎用的な耕うん機であれば、消耗品パーツもネット通販で安く調達することが出来るからです。ただし、自分で修理できない様な故障が生じた場合の対応策だけは、事前に確認しておいてください。なぜなら、簡単に修理に送ったりすることが出来ない、重量物の機械だからです。
ただ、物は試し! まずは一度、ネットで商品を検索してみて、値段を比べてみては?。
耕運機を買う際に、注目すべきポイントを幾つか整理してみました。耕運機の選び方や、比較する際の参考にして下さい。



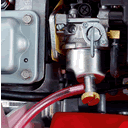 なお、ガソリンエンジンは、雪国の冬期など長い期間使用しない場合は、ガソリンを抜いておかないと、次に使う時に始動トラブルを起こすことがあります。ホンダの「こまめ F220
なお、ガソリンエンジンは、雪国の冬期など長い期間使用しない場合は、ガソリンを抜いておかないと、次に使う時に始動トラブルを起こすことがあります。ホンダの「こまめ F220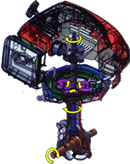 私が調べた中で、そこそこ使えそうな耕うん機の最軽量は、ホンダ「プチな FG201」(メーカー希望小売価格:69,000円+税)の18kgだと思います。他のメーカーの同等品と比べ、約1割(2kgほど)も軽量です。最大出力2.2psの、4サイクル50ccエンジンを積んでこの軽さを実現するためにホンダが開発した技術が、”プチな
私が調べた中で、そこそこ使えそうな耕うん機の最軽量は、ホンダ「プチな FG201」(メーカー希望小売価格:69,000円+税)の18kgだと思います。他のメーカーの同等品と比べ、約1割(2kgほど)も軽量です。最大出力2.2psの、4サイクル50ccエンジンを積んでこの軽さを実現するためにホンダが開発した技術が、”プチな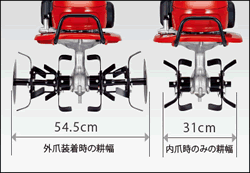 中耕作業に便利なように、外爪を外して、耕幅を変えられる機種もあります。少々の畝数であれば、外爪を外したり付けたりしている間に、鍬で畝間を鋤いてしまった方が早そうですが、土が固いと、それも結構な重労働だったりしますので、助かるかもしれません。ただし、内爪と外爪の連結部は、取外しが簡便なようにピン止めされているだけなので、長い年月の使用で、どうしても連結部が緩みがちになってしまう可能性は否めません。
中耕作業に便利なように、外爪を外して、耕幅を変えられる機種もあります。少々の畝数であれば、外爪を外したり付けたりしている間に、鍬で畝間を鋤いてしまった方が早そうですが、土が固いと、それも結構な重労働だったりしますので、助かるかもしれません。ただし、内爪と外爪の連結部は、取外しが簡便なようにピン止めされているだけなので、長い年月の使用で、どうしても連結部が緩みがちになってしまう可能性は否めません。
 また、クラッチレバー(握るとローターが回転します)は、自転車のブレーキの様に下から握るタイプより、クボタや三菱、新ダイワ等が採用している、上から押し下げるタイプの「デッドマンクラッチ」の方が、疲れ難く便利そうです。それに自転車のブレーキだと、危ない!と思った瞬間、つい握っちゃいがちですよね(汗)。ちなみに、デッドマン(Dead-man)装置とは、その名の通り、機械の操縦者が死んでしまうなど、操縦が続けられない緊急の事態に陥った場合(クラッチレバーでは握った手を放すことで)、自動停止して事故を防止するための安全装置のことです。
また、クラッチレバー(握るとローターが回転します)は、自転車のブレーキの様に下から握るタイプより、クボタや三菱、新ダイワ等が採用している、上から押し下げるタイプの「デッドマンクラッチ」の方が、疲れ難く便利そうです。それに自転車のブレーキだと、危ない!と思った瞬間、つい握っちゃいがちですよね(汗)。ちなみに、デッドマン(Dead-man)装置とは、その名の通り、機械の操縦者が死んでしまうなど、操縦が続けられない緊急の事態に陥った場合(クラッチレバーでは握った手を放すことで)、自動停止して事故を防止するための安全装置のことです。| メーカー | クボタ |
イセキ | ホンダ | 京セラ(リョービ) |
|---|---|---|---|---|
| 商品 |  Midy Smile-mini(TMS200) |
 パンジーmini(KM17) |
 こまめ(F220) |
 耕うん機 RCVK-4300 |
| エンジン 総排気量 最大出力 燃料タンク |
空冷4サイクル 49cc 1.6kW(2.2ps) 0.6L |
空冷4サイクル 36cc 1.2kW(1.6ps) 0.65L |
空冷4サイクル 57.3cm3 1.5kW(2.0ps) 0.67L |
空冷2サイクル 42.7ml 1.27kW(1.7ps) 1.2L(混合ガソリン) |
| 対応面積 最大耕深 爪径/軸径 耕うん幅 |
~30坪 140mm - 575mm |
- 120mm 245mm 480/225mm |
~100坪 - 280mm 545/310mm or 600/330mm |
~30坪 280mm - 360mm |
| 全長×幅×高 機体重量 |
110×58×98cm 22kg |
106×54×96cm 20~23kg |
112×59×98cm 27kg |
100×48×97cm 19kg |
| 変速段数 ローター形 ハンドル形 |
前進1、移動尾輪別売 ナタ爪ロータ/一体 Y型 |
前進1、移動尾輪付 ナタ爪ロータ/分割 Y型 |
前進1、移動輪別売 ナタ爪/分割(別タイプ選択可) Y型 |
前進1、移動尾輪付 ナタ爪ロータ/一体 Y型 |
| メーカー希望小売価格 (税込) |
106,810円 楽天市場へ |
オープン価格 楽天市場へ |
109,780円 楽天市場へ amazonへ |
101,000円 楽天市場へ amazonへ |
| 特徴 | コンパクトだけど、しっかりパワフル。重さ約22kgで持ち運び簡単!長時間の作業も快適にこなせる。移動用双尾輪が別売りなのがちょっと残念…。 | サイドディスクで直進性が高く、きれいに耕うん。本格ナタ爪で、しっかり耕うん。480mmの耕うん幅を225mmにも分割でき、中耕作業にも活用できます。 | 粘り強いパワーのエンジンと車体バランスの良さが、優れた耕うん性能を発揮。54.5cmの広い畝幅で効率よく耕うん。外爪を外して中耕培土作業も可能。 | 楽々スタートのKスタート付で、2サイクルエンジン(混合ガソリン仕様)。2ストでパワーの出るコンパクト設計ながら、排出ガス自主3次規制に適合。 |
※ リョービは2018年1月、会社分割(新設分割)によりパワーツール事業を京セラインダストリアルツールズ株式会社へ譲渡しました。
※ 製品の詳細については、必ずメーカーの公式情報でご確認ください。
もし私が、この2馬力クラスの車軸式ミニ耕うん機の中から、コンパクトさや軽さ、パワーなど能力のバランスで選ぶなら、ホンダの「こまめ F220」かな?と思います。最大出力はクボタの「Midy Smile-mini(TMS200)![]() 」の方が上ですが、排気量が大きい分、トルクが出ると思いますし、車体バランスの良さが取り回ししやすく、扱い良さそうです。重量は増えますが、20キロ台なら一般男性であれば大差感じませんし、逆に少し重い位の方が深く耕うんするには助かります。一方、ラインナップやアタッチメントの充実度、農業機械メーカー大手という信頼性の面では、クボタやイセキ(ヰセキ)も見逃せません。特に支店や営業所、サービスセンターの数では、農協を除けばクボタがトップでしょう!。長野の片田舎でも、クボタのサービスカーが走っているのを時々見かけます。でも、ホンダだって、近所にホンダショップのバイク屋があれば、一般的なエンジントラブルは簡単に解決できそうです(笑)。
」の方が上ですが、排気量が大きい分、トルクが出ると思いますし、車体バランスの良さが取り回ししやすく、扱い良さそうです。重量は増えますが、20キロ台なら一般男性であれば大差感じませんし、逆に少し重い位の方が深く耕うんするには助かります。一方、ラインナップやアタッチメントの充実度、農業機械メーカー大手という信頼性の面では、クボタやイセキ(ヰセキ)も見逃せません。特に支店や営業所、サービスセンターの数では、農協を除けばクボタがトップでしょう!。長野の片田舎でも、クボタのサービスカーが走っているのを時々見かけます。でも、ホンダだって、近所にホンダショップのバイク屋があれば、一般的なエンジントラブルは簡単に解決できそうです(笑)。
| メーカー | クボタ | イセキ | ヤンマー |
新ダイワ(やまびこ) |
|---|---|---|---|---|
| 商品 |  Midy Smile(TMS300) |
 KM30 |
 ミニ耕うん機 YK301QT |
 管理機 CAR251-MU1 |
| エンジン 総排気量 最大出力 燃料タンク |
空冷4サイクル 川崎 GB101 98cc 2.2kW(3.0ps) 0.8L |
空冷4サイクル 川崎 GB101PN 98cc 2.2kW(3.0ps) 1.2L |
空冷4サイクル 三菱 GB101LN 98cc 2.2kW(3.0ps) 1.0L |
空冷4サイクル 三菱 GB101PN 98cc 2.2kW(3.0ps) 1.2L |
| 対応面積 最大耕深 爪径/軸径 耕うん幅 |
~30坪 160mm - 650/345mm |
~30坪 - 290mm 600/310mm or 600/330mm |
- - 300mm 530mm/280mm |
- - - 540mm |
| 全長×幅×高 機体重量 |
120×65×110cm 44~47kg |
111×60×98cm 37~42kg |
119×53/61×100cm 34~43kg |
111×60×108cm 40kg |
| 変速段数 ローター形 ハンドル形 |
前進1、移動輪別売 スターロータ/一体or分割 Y型(旋回レバー仕様あり) |
前進1、移動尾輪選択 ナタ爪/分割orスターロータ選択 Y型 |
前1/前1後1/前2後1、移動尾輪選択 ナタ爪/分割(別タイプ別売) Y型 |
前進1、移動尾輪付 ナタ爪/一体(別タイプ別売) Y型 |
| メーカー希望小売価格 (税込) |
109,450~145,640円 楽天市場へ |
オープン価格 楽天市場へ |
107,800~163,900円 楽天市場へ |
125,840円 楽天市場へ amazonへ |
| 特徴 | 推進力に優れたロータで耕うんが安定し、コツ要らずで初心者にも簡単に耕せるコンパクト機。ハンドルの左右に旋回レバーが付いたS仕様なら、旋回も楽々。 | 耕うん爪軸はナタ爪耕うんロータ(D型)とスターロータ(M型)が選べ、ともに爪軸の分解ができます。見えるタンクで燃料の残量が確認できるのは便利!。 | 新開発の低振動爪でハンドル手元の振動を従来機より40%も軽減。簡易フリフリ抵抗棒で直進も旋回もラクラク。握るとバックで狭い場所でも旋回しやすい。 | コンパクトで家庭菜園に最適、簡単操作でしっかり耕うん。手軽に使えて、移動もらくらく。本格耕うん爪付で深くきれいな仕上がり。三菱のMM300とのOEM。 |
ここに挙げた3馬力クラスの車軸式ミニ耕運機が、我が家の様な100坪クラスの家庭菜園で使うには、大きさやパワー、価格的にもベストな選択ではないでしょうか?。この4機種は、何れも川崎GB101エンジンを採用していて、最大出力は全く同じ。細かいことを言うと、ヤンマーが採用しているL型(LN)の方が、P型(PN)より最大トルクが若干大きい様です(逆に定格出力は抑えられています)。
価格がほぼ横並びだとすると、あとは機能で選ぶことになりますが、後進ギアが欲しいとなるとヤンマーの「YK301QT![]() 」の一択です。ただ、下方に記した「耕運機で起きやすい事故事例」にもある通り、耕運機での事故のトップは「バック時の事故」です。十分ご注意ください!。なお、様々なアタッチメントが充実しているのは、クボタとヤンマー。ただ、100坪程度の家庭菜園で、アタッチメントを付けてまで畝立てをする機会がどれ程あるかは疑問です。実際、分割式ローターでさえも、わざわざ分割させるのは結構な手間です…。そう考えれば、一番シンプルな基本機能だけに絞られた、新ダイワ(やまびこ)の「CAR25
」の一択です。ただ、下方に記した「耕運機で起きやすい事故事例」にもある通り、耕運機での事故のトップは「バック時の事故」です。十分ご注意ください!。なお、様々なアタッチメントが充実しているのは、クボタとヤンマー。ただ、100坪程度の家庭菜園で、アタッチメントを付けてまで畝立てをする機会がどれ程あるかは疑問です。実際、分割式ローターでさえも、わざわざ分割させるのは結構な手間です…。そう考えれば、一番シンプルな基本機能だけに絞られた、新ダイワ(やまびこ)の「CAR25![]() 」が、私的には一番のおすすめです。ナタ爪ローターは唯一分割式でありませんが、分割して使う機会が無ければ全く気になりませんし、分割部分を接続している金属ピンが頻繁に割れて交換する頻度が高いことを考えれば、無い方がマシとも言えます。標準で移動尾輪も付いていて、見た目的にスタイルが低重心で扱い易そうなのも私が気に入った理由です。
」が、私的には一番のおすすめです。ナタ爪ローターは唯一分割式でありませんが、分割して使う機会が無ければ全く気になりませんし、分割部分を接続している金属ピンが頻繁に割れて交換する頻度が高いことを考えれば、無い方がマシとも言えます。標準で移動尾輪も付いていて、見た目的にスタイルが低重心で扱い易そうなのも私が気に入った理由です。
あと、比較選択のポイントになりそうなのが、デッドマンクラッチ。イセキとヤンマーは自転車のブレーキの様に下側のレバーを握るタイプ。一方、クボタと新ダイワは上側のレバーを押し下げるタイプ。「いざ」という時のことを考えると、後者の方が私は安全に感じます。ただ、クボタの燃料タンクは0.8Lと4機種の中では一番小さいのが気になります。
いくら小型でも、車軸式では能力不足。ロータリー式(リア式)の耕うん機・管理機で、できるだけ小型でコストパフォーマンスに優れた機種を探すならこれ!という、各社おすすめの耕うん機をピックアップしてみました。ちなみに、フロント・ロータリー式の耕うん機はどうしても価格が高くなってしまうので、今回のサブマシン用途としての候補からは除外しました。
| メーカー | クボタ |
イセキ | ホンダ | 三菱マヒンドラ |
|---|---|---|---|---|
| 商品 |  菜ビSmile TRS300 |
 Myペット KMR303 |
 ラッキーボーイ FU400 |
 エコ・ラテR ELR20 |
| エンジン 総排気量 最大出力 燃料タンク |
空冷4サイクル 98cc 2.2kW(3.0ps) 1.4L |
空冷4サイクル 98cc 2.2kW(3.0ps) 1.6L |
空冷4サイクル 118cc 2.6kW(3.5ps) 1.7L |
空冷4サイクル 79cc 1.6kW(2.2ps) -(カセットガス使用) |
| 対応面積 最大耕深 爪径/軸径 耕うん幅 |
~120坪 140mm - 450mm |
~270坪 140mm 280mm 450mm |
~100坪 120mm 290mm 460mm |
- - - 500mm |
| 全長×幅×高 機体重量 |
129×49×105cm 53kg |
133×55×101cm 70kg |
139×56×105cm 71kg |
138×58×109cm 60kg |
| メーカー希望小売価格 (税込) |
189,860~221,980円 楽天市場へ |
オープン価格 楽天市場へ Yahoo!ショッピングへ |
184,690円 楽天市場へ |
163,900円 楽天市場へ |
| 特徴 | タイヤ付きで安定、軽快に耕せる。畝立て機が不要の簡単畝立てマット機能付き。ロータリの逆回転はレバー操作だけ。硬い畑でもしっかり耕うん。 | ハンドルの上下をワンタッチレバーで調整可能。外爪と内爪が逆転する一軸正逆転で(HX型)、堅い土でもしっかり食い込み耕うんできます。 | 粘り強いパワーを発揮する118ccのエンジンで作業がスムーズ。耕うん爪を覆うカバーの中に土を格納してかき回し、きめ細やかな土に仕上げます。 | 燃料は家庭用カセットボンベで、ガソリンに比べてとても扱いやすいのが魅力的。業界最大排気量の80ccの大排気量ながら、きれいな排気のエコ仕様。 |
農林水産省の調査によると、全国で令和元年に起こった農作業に伴う事故死亡者数は、前年より7人増加し 281人でした。そのうち、「歩行型トラクター」による死亡事故は 22人(7.8%)です。痛ましいことに、この10年間(平成22年~令和元年)で 313人もの人が、歩行型トラクター(耕運機・管理機)による事故で亡くなっています。
家庭菜園は生活の糧でもありますが、とても楽しい趣味にもなります。しかし、それでケガをしたり死んでしまっては、元も子もありません。耕運機を使う際には、十分注意して取り扱う必要があります。
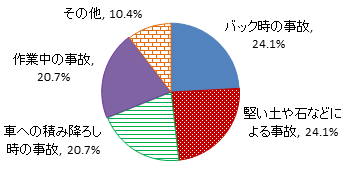 耕運機を使っていて作業者が起こしやすい事故は、農林水産省が2011年~2014年にかけて対面調査によって調べた「こうして起こった農作業事故」報告書によると、「バック時の事故」と「固い土や石などによる事故」が、それぞれ24.1%と、とても多いことが分かっています。続いて、「車への積み降ろし時の事故」と「作業中の事故」が20.7%ずつで、この4種類の事故で全体の約9割を占めています。
耕運機を使っていて作業者が起こしやすい事故は、農林水産省が2011年~2014年にかけて対面調査によって調べた「こうして起こった農作業事故」報告書によると、「バック時の事故」と「固い土や石などによる事故」が、それぞれ24.1%と、とても多いことが分かっています。続いて、「車への積み降ろし時の事故」と「作業中の事故」が20.7%ずつで、この4種類の事故で全体の約9割を占めています。
→ 農林水産省・農作業安全研修資料「SERIES 安全対策・これだけは … 耕耘機の事故」(PDF)
![]()