長野県内に数多くある温泉地。その泉質と効能を分類し、温泉マップを作ってみました。
信州・長野県には、本当に数多くの温泉地があります。長野県内に住んでいて、日帰り温泉巡りをしようと思っても、公共の日帰り温泉施設を制覇するだけで、何年もかかってしまいそうです。
環境庁の「平成28年版 環境統計集」によると、平成26年度時点で、長野県内にある「温泉地の数」は 221箇所(全国の7.2%)で、北海道の246箇所に続いて全国2位です。また、温泉の「宿泊施設数」は 1,240施設(全国の9.3%)で、これも北海道に続いて全国2位。そして、「温泉利用の公衆浴場の数」では、671箇所(全国の8.5%)と全国1位です。
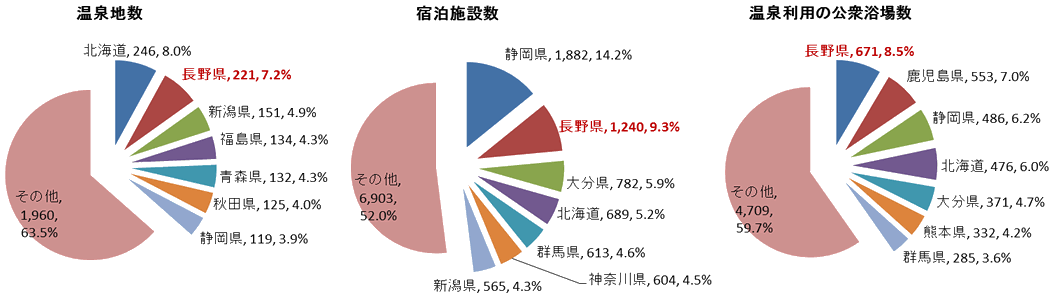
ちなみに、月に4箇所、毎月入り続けたとしても、一年間に入れるのは48箇所。長野県内にある 221箇所の温泉地を訪れるのには4年半、671箇所ある公衆浴場を制覇するには、14年もの歳月がかかってしまいます(汗)。
 温泉法では、
温泉法では、温泉とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、温泉源から採取された時の温度が25度以上か、または、別に定める溶存物質を一定以上有するもの
と記されています。
したがって、湧き出した湯温が25度以上あれば全て「温泉」であり、また、特定物質を1種類でも一定量以上含んでいれば、冷たくても「温泉」です。
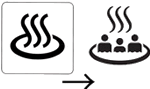 ちなみに、この温泉マーク。2020年の東京オリンピック開催に向けて、外国人にも分かりやすいデザインに変えていこうという取り組みにおいて、大きな議論が巻き起こりました。結局のところ、2018年2月20日の改正で、従来の温泉マークと、世界的共通指針となるISOのピクトグラムの図案との、両方が併記される形となり、表示者が何れか適切と思う方を選らんで表示することとなりました(汗)。
ちなみに、この温泉マーク。2020年の東京オリンピック開催に向けて、外国人にも分かりやすいデザインに変えていこうという取り組みにおいて、大きな議論が巻き起こりました。結局のところ、2018年2月20日の改正で、従来の温泉マークと、世界的共通指針となるISOのピクトグラムの図案との、両方が併記される形となり、表示者が何れか適切と思う方を選らんで表示することとなりました(汗)。
 温泉には、大きく分けて以下の3つの効果があります。
温泉には、大きく分けて以下の3つの効果があります。
 温泉の効果や効能は広く知られていますが、すべての人に役立つものとは限りません。温泉成分が逆に病気を悪化させてしまう禁忌症の人はもちろん、同じ症状でも、人によって改善する場合もあれば、効果が現れない人もいます。また、間違った入浴法により、症状を悪化させてしまう場合も。
温泉の効果や効能は広く知られていますが、すべての人に役立つものとは限りません。温泉成分が逆に病気を悪化させてしまう禁忌症の人はもちろん、同じ症状でも、人によって改善する場合もあれば、効果が現れない人もいます。また、間違った入浴法により、症状を悪化させてしまう場合も。
長湯・頻湯は避け、入浴時間は10分から長くても30分まで、入浴回数は一日に2回までがお勧めの入浴方法。温泉の飲用は、一回に100mlから200ml、一日の量は多くても1リットルまでです。
また、温泉入浴はとても体力を消耗します。長旅で疲れて到着した直後や、運動や食事をした直後は、まずゆっくり休んで体調を整えてから、入浴するようにしましょう。
以前、NHKの「ためしてガッテン」で、湯治のベテランの人達の入浴方法が紹介されていました。晩秋、畑作が終わり農閑期に入った農家のお婆さん達は、隣近所誘い合い、お米と野菜を担いで、1~2週間の湯治に出掛けます。温泉に到着すると、お風呂に直行するのかと思いきや、お婆さん方は、お茶を飲んで、お喋りして、お昼寝・・・。湯治初日にお風呂に入るのは、ようやく夜になって、寝る前です。就寝前にお風呂に入ることで、身体が温まり、快眠が得られるそうです。そして、2日目は2回、3日目は3回入浴し、回数を徐々に増やしますが、湯あたりが出てくる4日目は、温泉に入らず身体を休めます。その後は、帰る日に向けて、今度は逆に入浴回数を徐々に減らして行くのが、身体に負担をかけずに湯治を楽しむコツだそうです!。せっかくだからと、外湯巡りを楽しみつつ、朝昼晩と5回も10回もお風呂に入るのは、愚の骨頂!?
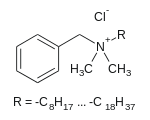 温泉には、様々な物質(成分)が含まれています。そこで「温泉法」では、特定の18種類の物質が一定量以上含まれている温泉を、10種類の「泉質」に分類して、その効能を認めています。
温泉には、様々な物質(成分)が含まれています。そこで「温泉法」では、特定の18種類の物質が一定量以上含まれている温泉を、10種類の「泉質」に分類して、その効能を認めています。
ただし、その泉質の分類は、温泉の分析と効能についての研究が進展するとともに見直され、最近では2014年(平成26年)に、「鉱泉分析法指針」の改定が行われました。この改定を受けて、それまで泉質として認められていた、療養泉のうちの「含アルミニウム泉」と「含銅-鉄泉」の2種類が除外され、代わって「含よう素泉」が加わったことで、それまで11種類あった泉質が、10種類になっています。
※ 除外された、含アルミニウム泉と含銅-鉄泉として認められていた温泉は数が少なく(つまり希少で)、かつその効能は他の成分に由来するものとして、平成26年の改定で泉質分類から外されてしまいましたが、その温泉の効能が間違っていたという事ではないので、むしろその希少性を評価してあげてください。
ちなみに、含アルミニウム泉の代表的な温泉には、恵山温泉(北海道)、塚原温泉(大分県)、蔵王温泉(山形県)、毒沢温泉(長野県)などがあります。
また、含銅-鉄泉としては、磯辺温泉(群馬県)、大谷温泉(島根県)、立科温泉(長野県)などが挙げられます。
「療養泉でない温泉」とは、温泉が「療養泉」の基準に満たない場合で、その温泉には泉質名はありません。したがって温泉分析書には、「温泉法上の温泉」とか、「温泉法第2条に該当する温泉」と記載されています。
なお、昭和53年からは、主な化学成分を記した「新泉質名」を使うようにと環境省から通達されていますが、未だに、重曹泉とか食塩泉といった、いわゆる「旧泉質名」で表記された温泉もあり、混在していますのでご注意ください。
| No | 掲示用新泉質名 | 旧泉質名 | 新泉質名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 単純温泉 | 単純温泉 | 単純温泉 アルカリ性単純温泉 |
| 2 | 塩化物泉 | 食塩泉 含塩化土類-食塩泉 含土類-食塩泉 |
ナトリウム-塩化物泉 ナトリウム・マグネシウム-塩化物泉 ナトリウム・カルシウム-塩化物泉 |
| 3 | 炭酸水素塩泉 | 重炭酸土類泉 重曹泉 |
カルシウム(・マグネシウム)-炭酸水素塩泉 ナトリウム-炭酸水素塩泉 |
| 4 | 硫酸塩泉 | 硫酸塩泉 正苦味泉 芒硝泉 石膏泉 |
硫酸塩泉 マグネシウム-硫酸塩泉 ナトリウム-硫酸塩泉 カルシウム-硫酸塩泉 |
| 5 | 二酸化炭素泉 | 単純炭酸泉 | 単純二酸化炭素泉 |
| 6 | 含鉄泉 | 鉄泉 炭酸鉄泉 緑礬泉 |
鉄泉 鉄(Ⅱ)-炭酸水素塩泉 鉄(Ⅱ)-硫酸塩泉 |
| 7 | 酸性泉 | 単純酸性泉 | 単純酸性泉 |
| 8 | 含よう素泉 | 含ヨウ素-食塩泉 | 含よう素-ナトリウム-塩化物泉 |
| 9 | 硫黄泉 | 硫黄泉 硫化水素泉 |
硫黄泉 硫黄泉(硫化水素型) |
| 10 | 放射能泉 | 放射能泉 | 単純弱放射能泉 単純放射能泉 含弱放射能-○-○泉 含放射能-○-○泉 |
すべての泉質の温泉において、神経痛や筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進などは「適応症」として、その入浴効果が認められています。
ここでは、こうした「万病に効く温泉」と謂われる効能以外で、それぞれの泉質特有の効能を、入浴および飲用別に、一覧表にしてみました。
| 泉質 | きりきず | やけど | 慢性皮膚病 | 虚弱児童 | 慢性婦人病 | 動脈硬化 | 高血圧症 | 月経障害 | ※ 神経痛など |
慢性消化器病 | 糖尿病 | 痛風 | 慢性胆嚢炎 | 胆石症 | 慢性便秘 | 肝臓病 | ※ 肥満症 |
貧血 | 温泉マップへ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単純温泉 |  |
 |
→単純温泉の「温泉マップ」 | ||||||||||||||||
| 塩化物泉 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
両 |  |
→塩化物泉の「温泉マップ」 | ||||||||||
| 炭酸水素塩泉 |  |
 |
 |
 |
両 |  |
 |
 |
→炭酸水素塩泉の「温泉マップ」 | ||||||||||
| 硫酸塩泉 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
→硫酸塩泉の「温泉マップ」 | ||||||
| 二酸化炭素泉 |  |
 |
 |
 |
両 |  |
→二酸化炭素泉の「温泉マップ」 | ||||||||||||
| 含鉄泉 |  |
 |
 |
 |
→含鉄泉の「温泉マップ」 | ||||||||||||||
| 酸性泉 |  |
 |
両 | →酸性泉の「温泉マップ」 | |||||||||||||||
| 含よう素泉 |  |
→含よう素泉の「温泉マップ」 | |||||||||||||||||
| 硫黄泉 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
両 |  |
 |
→硫黄泉の「温泉マップ」 | ||||||||
| 放射能泉 |  |
 |
 |
両 | 両 | 両 | 両 | 両 | →放射能泉の「温泉マップ」 |
※ 「両」は、入浴および飲用の両方で効能が認められているもの。
※ 「」の硫黄泉は、硫化水素型のみ。
※ 「神経痛など」には、筋肉痛、関節痛を含む。「肥満症」には、高コレステロール血症を含む。
※ 長野県温泉協会「湯治ノススメ」に掲載されている情報を参考にさせて頂きました。
 「禁忌症」(きんきしょう)とは、温泉療法を行ってはいけない病気や症状のことです。
「禁忌症」(きんきしょう)とは、温泉療法を行ってはいけない病気や症状のことです。
泉質によって禁忌症は異なりますが、一般的には、急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性の疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(とくに初期と末期)の人は、温泉に入ったり飲用をしてはいけません。
また、皮膚や粘膜が過敏な人、特に光線過敏症の人や、皮膚乾燥症の高齢者は、硫黄泉や酸性泉には入ってはいけません。
 温泉の飲用においては、腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのある時、甲状腺機能こう進症の時、下痢をしている時などは、泉質にもよりますが、原則的に禁忌と判断し、特に温泉療法医の指導を受けていない場合は、飲用すべきでありません。
温泉の飲用においては、腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのある時、甲状腺機能こう進症の時、下痢をしている時などは、泉質にもよりますが、原則的に禁忌と判断し、特に温泉療法医の指導を受けていない場合は、飲用すべきでありません。
同じ温泉地でも、源泉によって泉質が異なる場合もありますが、代表的な泉質についてのみ、効能別にマッピングしました。
なお、「酸性泉」や「含よう素泉」の温泉は、長野県内でも少ないため、特定物質が基準値以上含まれている源泉がある場合は、その温泉地の代表的な泉質でない場合でも、敢えて挙げています。(その意味では、他にも該当する温泉地があり得るかもしれません。)
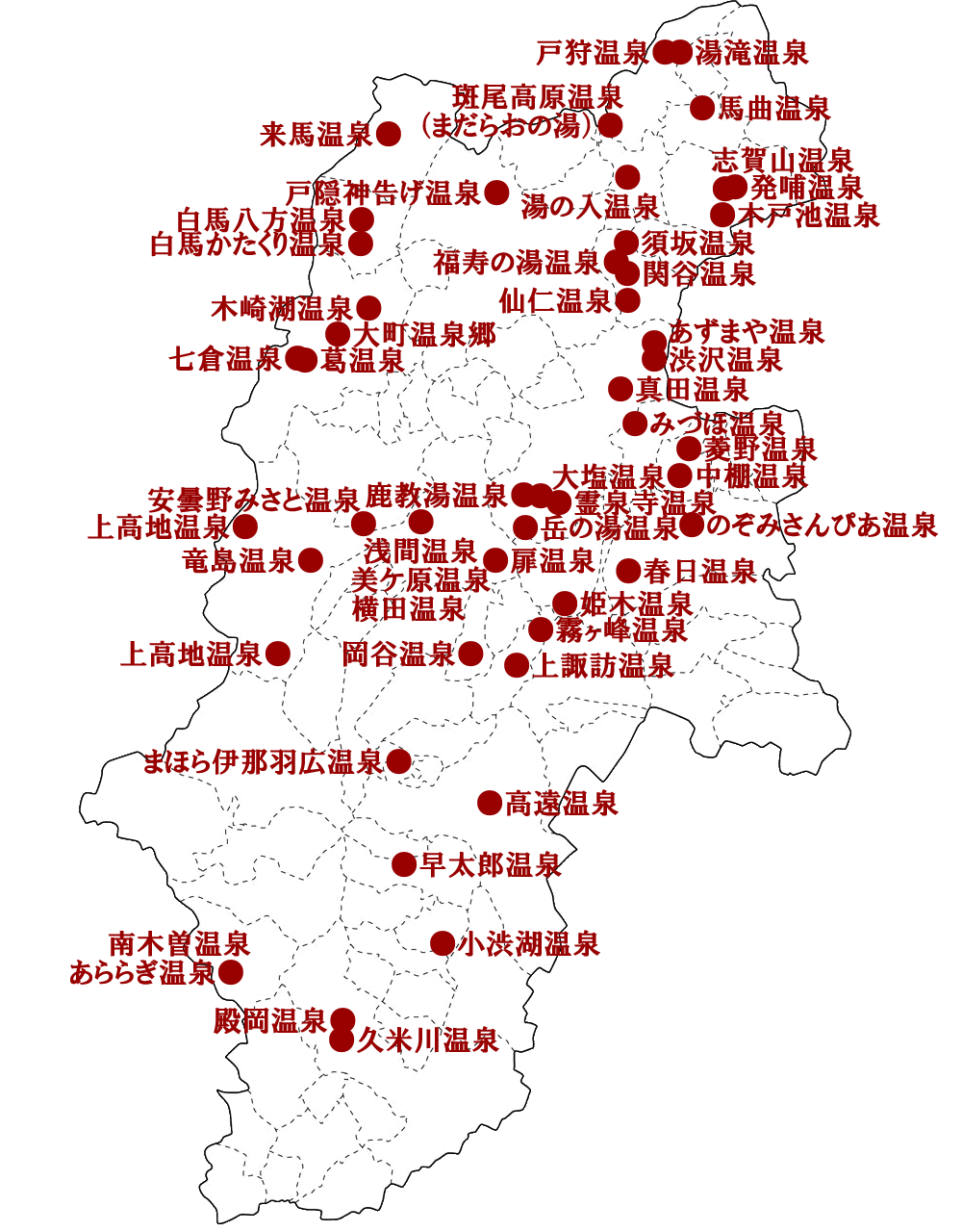
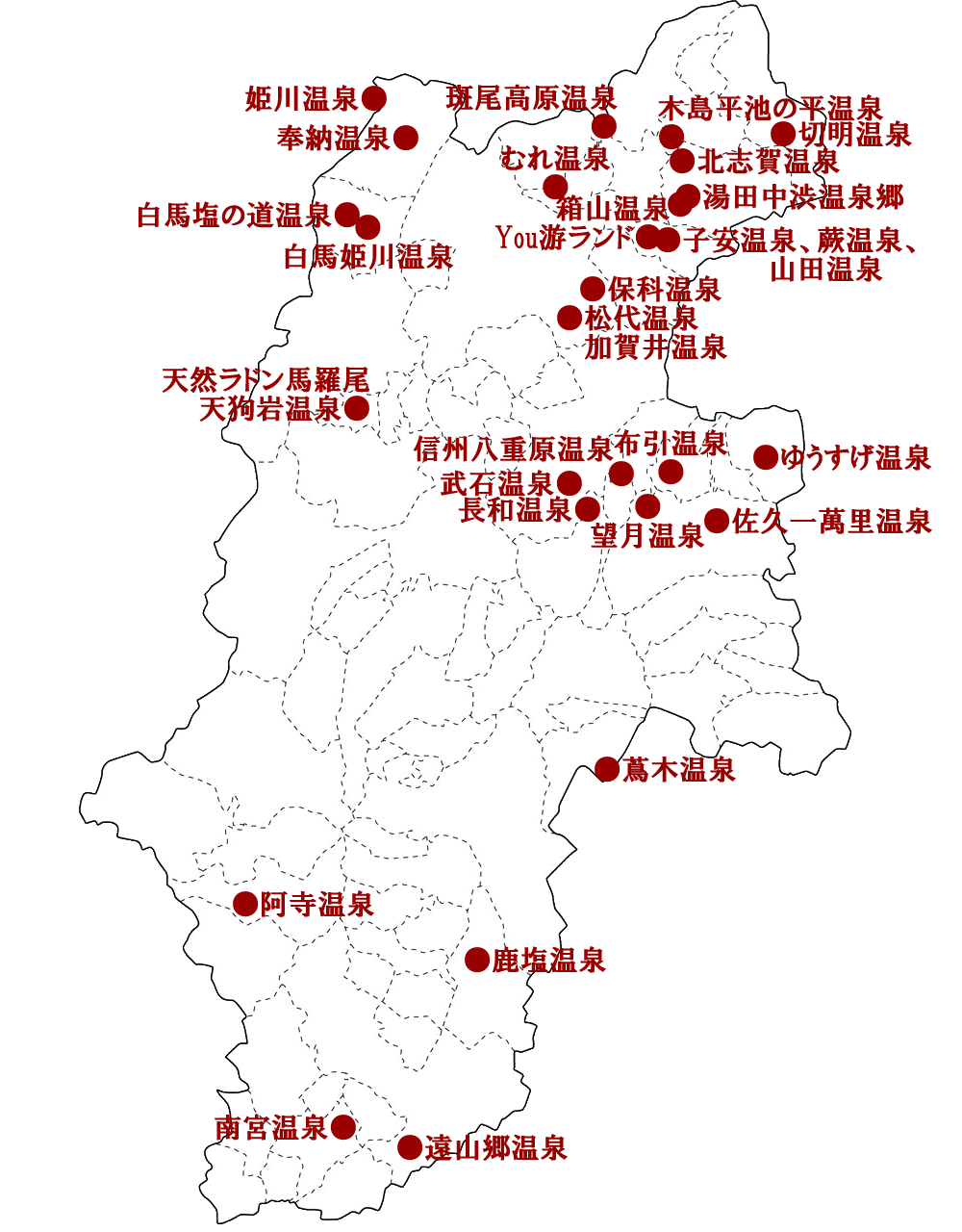
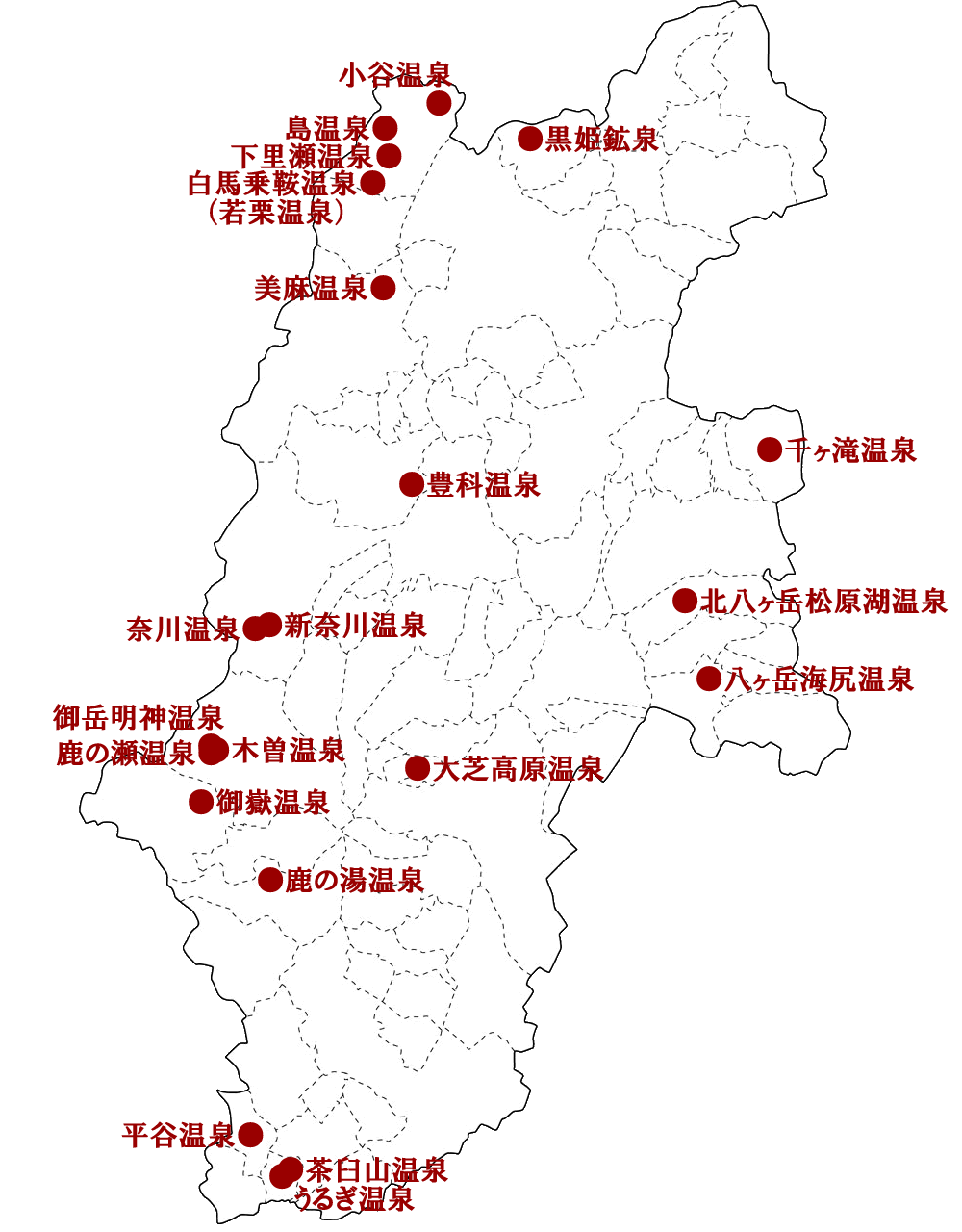
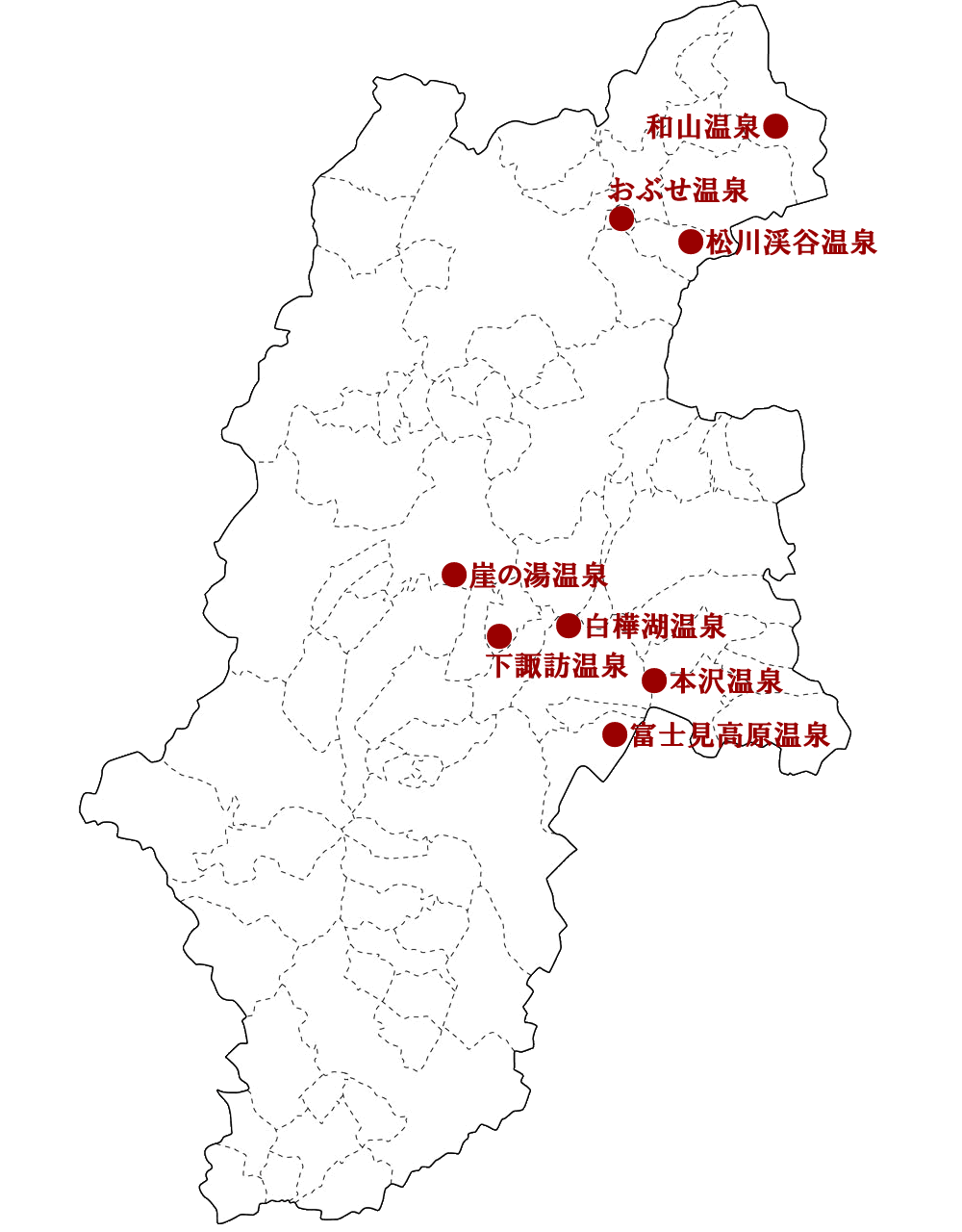
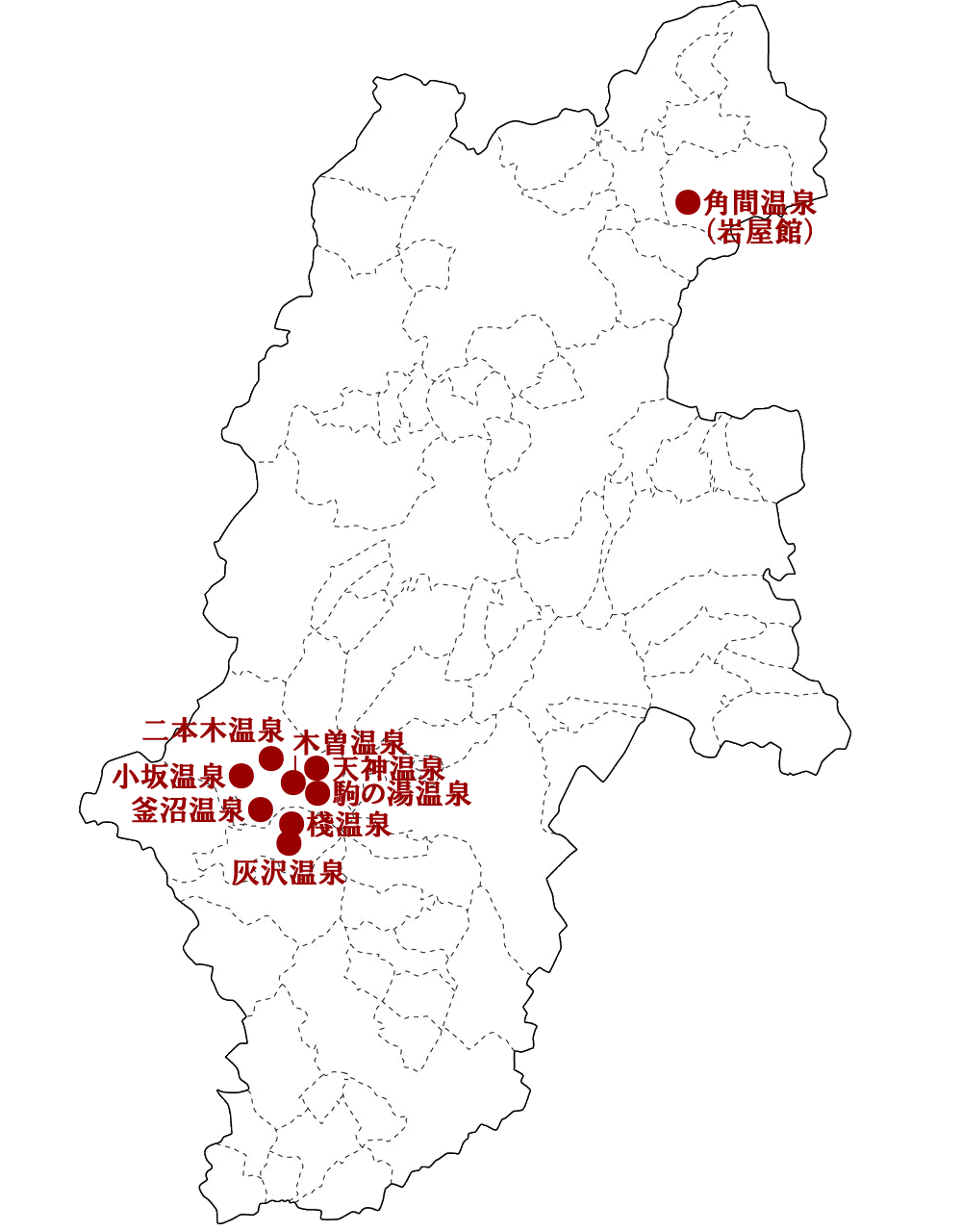
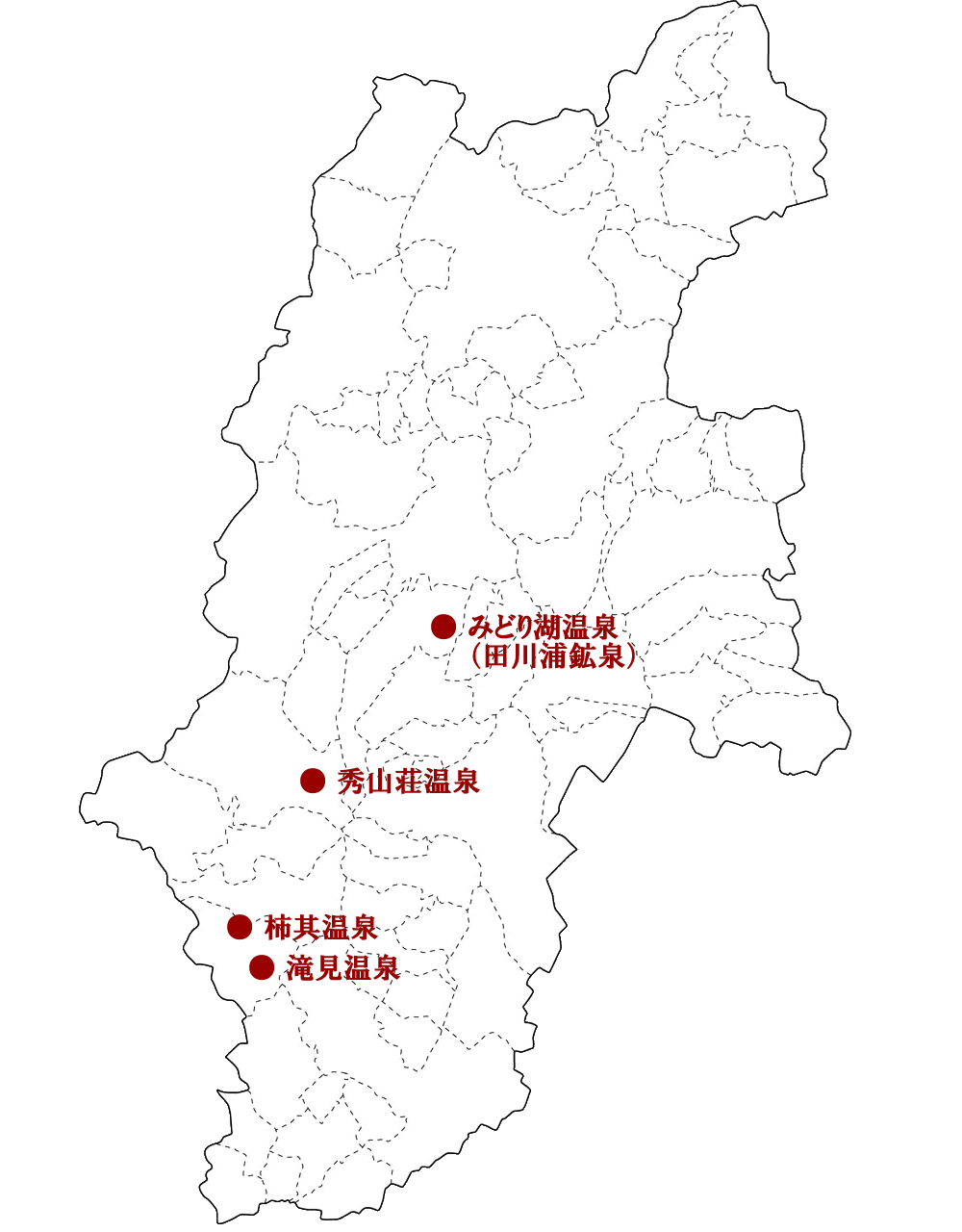
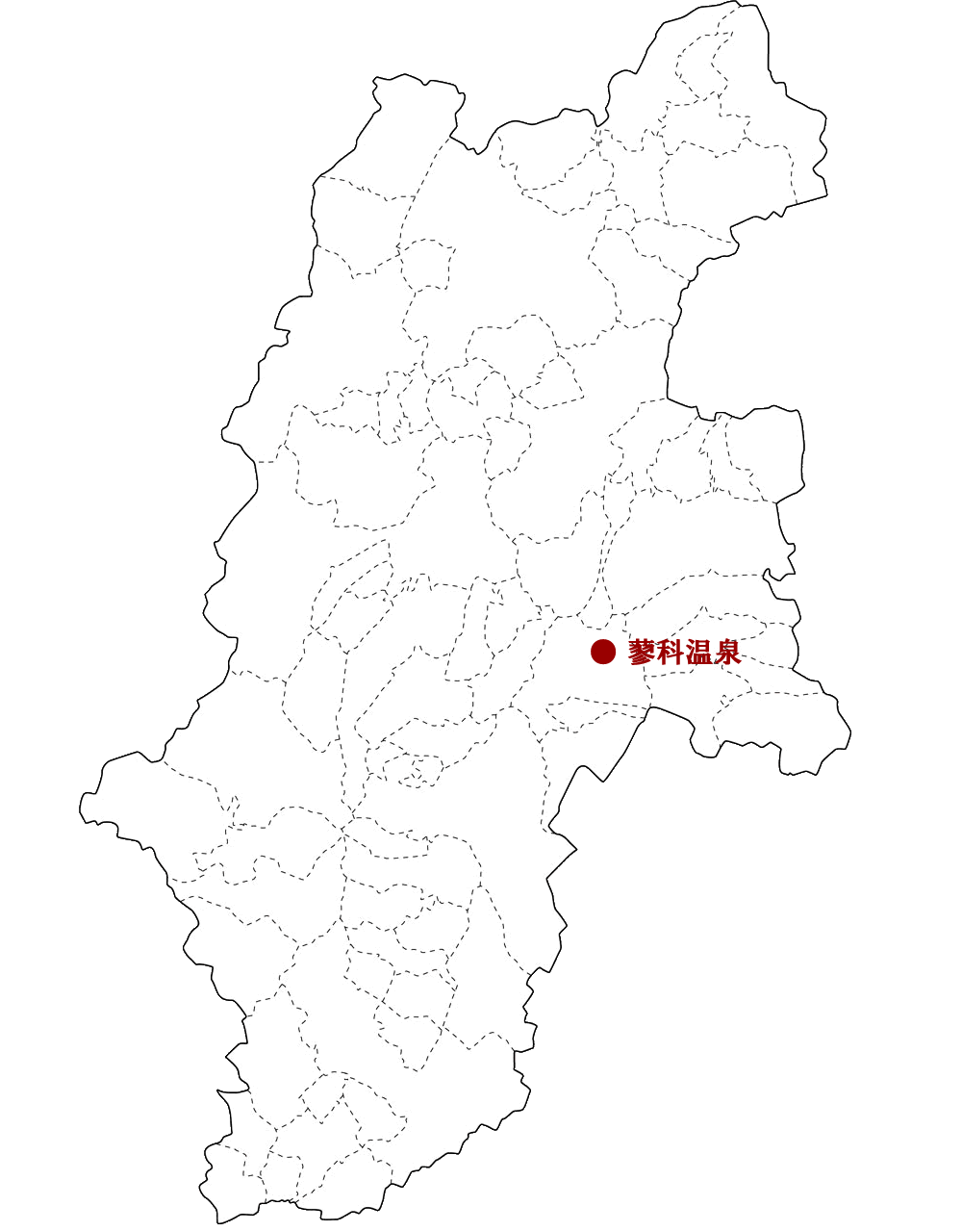
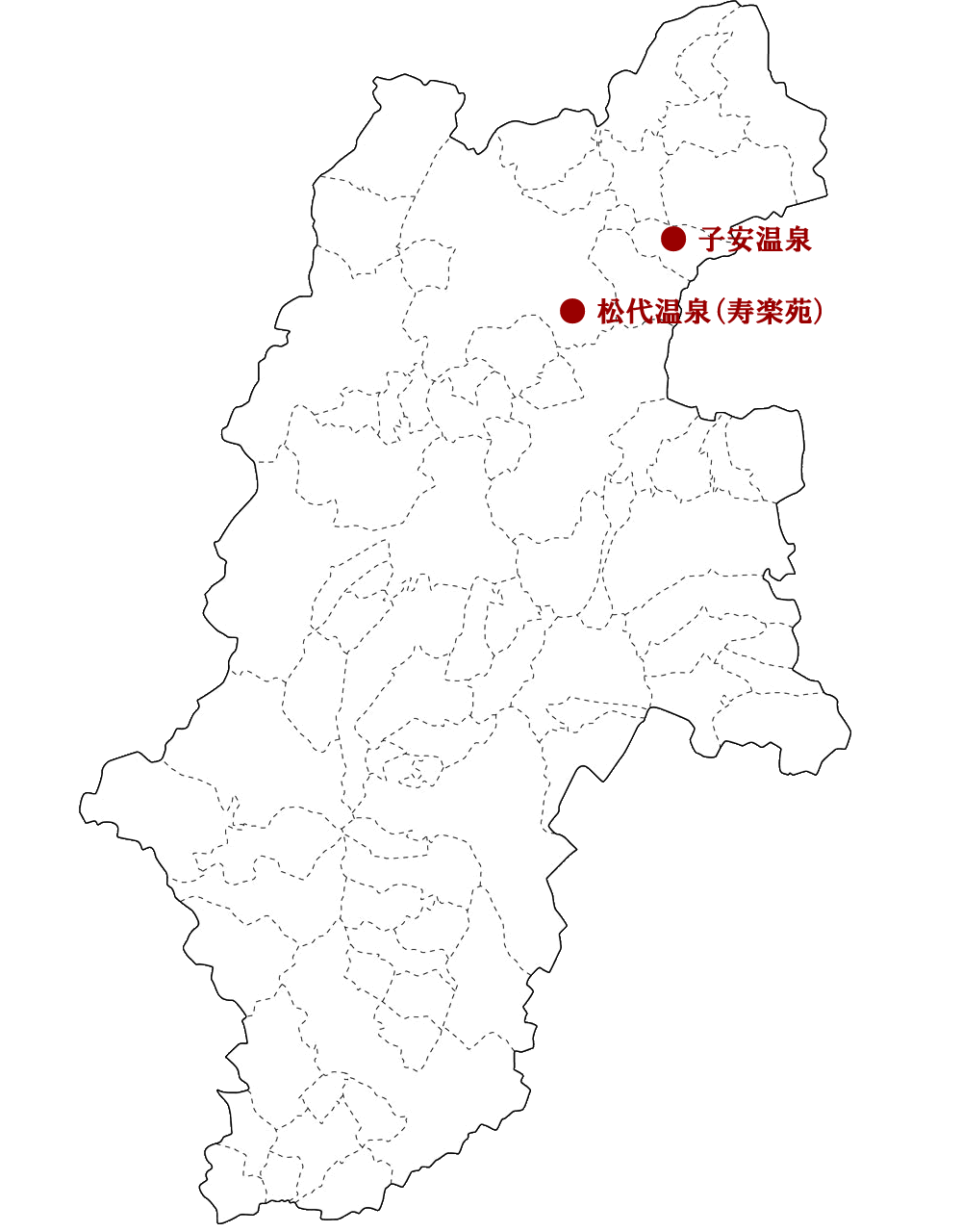
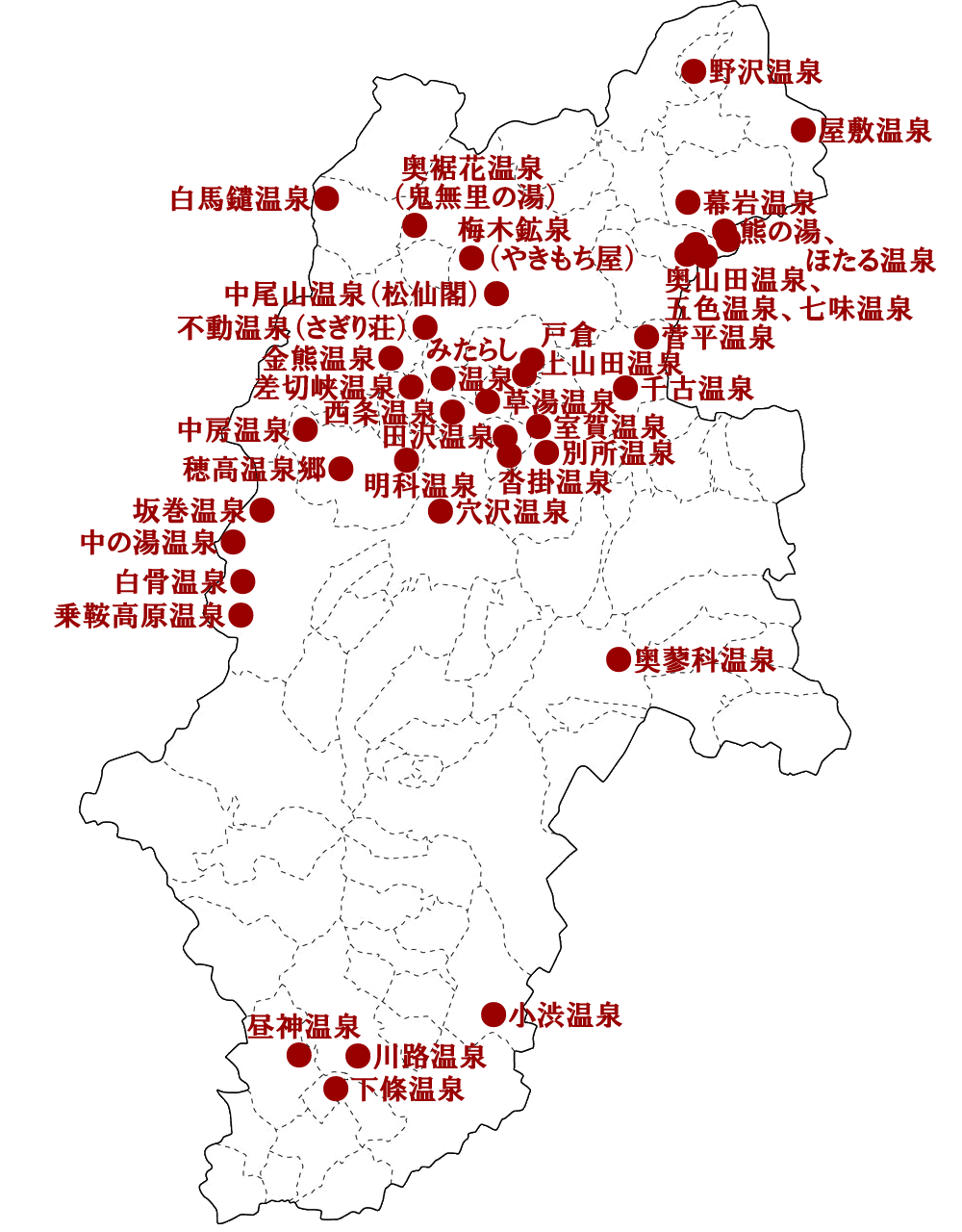
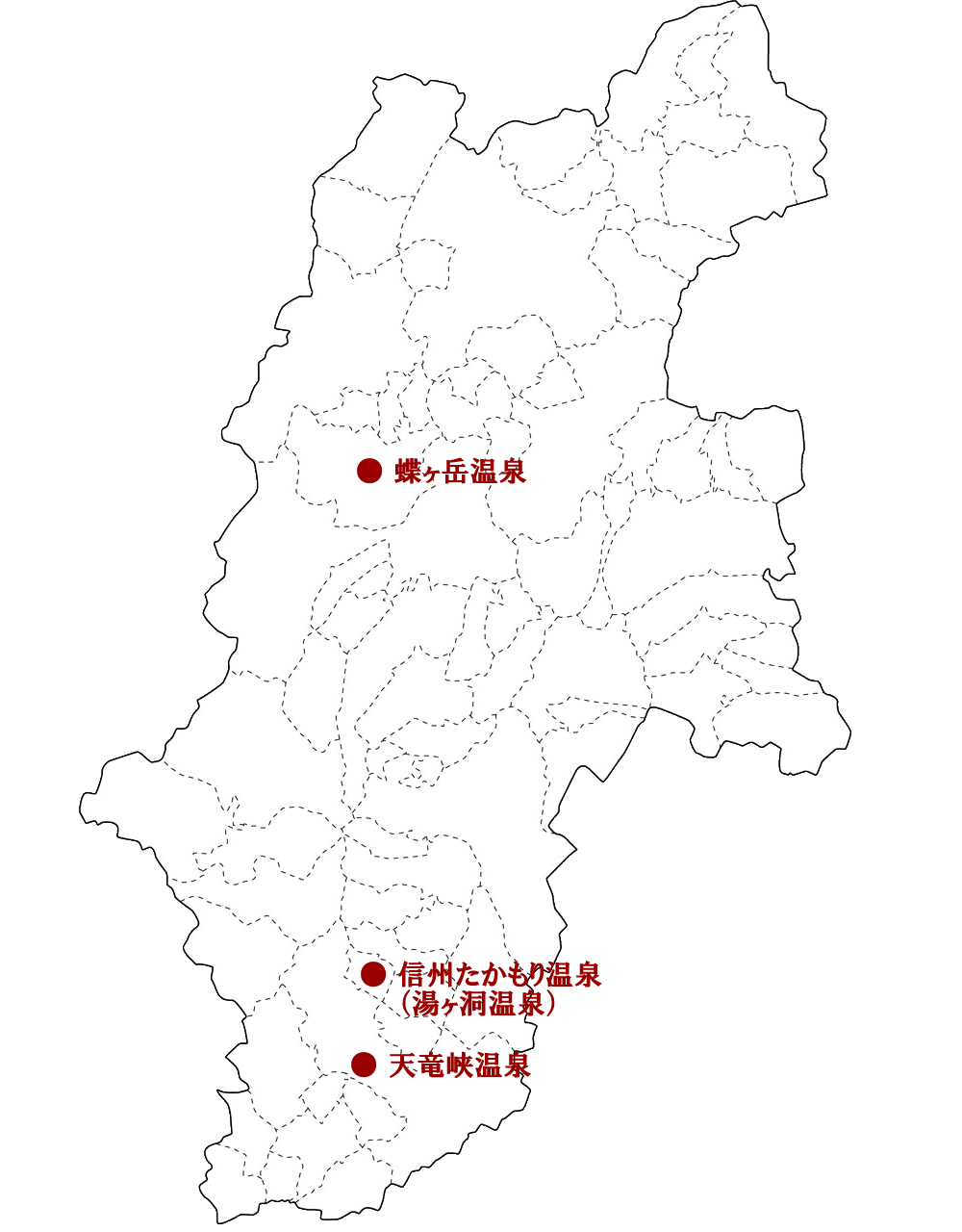
![]()