都会からリタイアして地元の田舎に戻り始めた家庭菜園、少しずつ学んだ野菜の育て方のコツをまとめてみました。
 ラッカセイ(落花生)は、マメ科(マメ亜科)の一年草の植物です。地中に出来る種子を食べますが、その生り方が、とても変わっています。その出来た種を蒔くと、芽が出て、地上に茎葉を広げ、夏には花が咲きます。受粉は自家受粉でき、花が散った後に残った子房柄が、だんだんと地面に向かって伸びていき、最後は地中に潜り込みます。そして、地中に入った子房の部分が膨らんで、やがて落花生(ラッカセイの種子)に成長します!。こうした珍しい、地下で結実する種子(実)の生り方を、”地下結実性”と言うそうです。
ラッカセイ(落花生)は、マメ科(マメ亜科)の一年草の植物です。地中に出来る種子を食べますが、その生り方が、とても変わっています。その出来た種を蒔くと、芽が出て、地上に茎葉を広げ、夏には花が咲きます。受粉は自家受粉でき、花が散った後に残った子房柄が、だんだんと地面に向かって伸びていき、最後は地中に潜り込みます。そして、地中に入った子房の部分が膨らんで、やがて落花生(ラッカセイの種子)に成長します!。こうした珍しい、地下で結実する種子(実)の生り方を、”地下結実性”と言うそうです。
原産地は南米大陸とされ、東南アジアや中国を経由して、江戸時代に日本へ伝わったと言われています。そのため、”南京豆”あるいは”唐人豆”、”異人豆”とも呼ばれています。”落花生”という名前の由来は、花が地面に落ちるようにして地中に種子(豆)が生ることから名付けられましたが、沖縄では”地豆”(ぢまめ、ジーマーミ)と呼び、英語では peanut(ピー・ナッツ=木の実のような豆)以外に groundnut(グラウンド・ナッツ=地面の木の実)とも呼ばれています(笑)。
一般的にスーパーなどの食品店では、”殻付きのラッカセイ”と、”殻を剥いたラッカセイ”が売られています。何故か理由は定かでありませんが、殻付きのラッカセイは、一般的に「落花生」と表示され売られていて、殻を剥いたラッカセイは、薄皮付きだと「落花生」あるいは「南京豆」、薄皮を剥いで味が付いたものは「ピーナッツ」という商品名が付けられていることが多いです。そのため、多くの人は、落花生と南京豆、ピーナッツは違う物と思い込んでいる様ですが、元はすべて同じラッカセイです!(笑)。
通常、食品(菓子類など)として売られているラッカセイは、大抵どの商品も、乾燥させた生のラッカセイを煎って(あるいは茹でて)あるので、そのまま食べることが出来ます。しかし、殻付きの煎り落花生と、乾燥させただけの生のラッカセイは、焼き焦げでも付いていないと、ほとんど見分けることが出来ません。煎ってあると思い込んで、生のラッカセイを食べてしまうと、大変なことになりますよ!(笑)。
ちなみに、食品分類では、”らっかせい”は豆類ではなく種子類に分類され、食品番号:05034~03045=らっかせい(大粒種/小粒種、乾/いり の違いで4分類)の他、05036=バターピナッツ、05037=ピーナッツバターと、6つに分類され、食品標準成分が表示されています。また、家庭菜園や野菜栽培の書籍では、なぜか豆類ではなく、ジャガイモや大根などと同じ”根もの野菜(根菜)”として扱われていることが多いですね(汗)。


 ラッカセイは、他のマメ科の野菜と同様に、その種子つまり落花生の豆を蒔いて育てます。しかし、念のため申し上げますが、スーパーで食品(豆菓子)として売られている、煎られた落花生の豆を蒔いても芽は出ませんよ(笑)。
ラッカセイは、他のマメ科の野菜と同様に、その種子つまり落花生の豆を蒔いて育てます。しかし、念のため申し上げますが、スーパーで食品(豆菓子)として売られている、煎られた落花生の豆を蒔いても芽は出ませんよ(笑)。
マメ科の植物は直根なので、あまり植え替えには向きません。可能であれば直播きをおすすめしますが、早蒔きしたい場合には、ポットに蒔いて保温して苗を育てます。ちなみに、鳥による被害を防止するためにポット蒔きする方もいるかもしれませんが、私は過去に、直播きした種は鳥害に合わなかったのに、ポット苗を定植したら、翌日には鳥に全部引き抜かれていたことがあります…(汗)。定植するところを鳥に見られたか、何かを察知されてしまったんでしょうね(笑)。
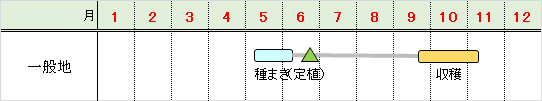
 種まきの1週間前に、多めの石灰と、控えめの肥料を撒き、耕しておきます。コガネムシの幼虫やヨトウムシによる被害が発生している圃場では、一緒に「ダイアジノン粒剤
種まきの1週間前に、多めの石灰と、控えめの肥料を撒き、耕しておきます。コガネムシの幼虫やヨトウムシによる被害が発生している圃場では、一緒に「ダイアジノン粒剤」などの殺虫剤も漉き込んでおきましょう。私はコガネムシの幼虫の発生を避けるために、敢えて堆肥ではなく化成肥料を使い、肥効切れは追肥で補うようにしています!。
種まきの数日前に黒マルチを掛けてから種(豆)を蒔くと、地温が上がり雑草予防にもなり都合が良いですが、花が咲いた頃に、破って剥ぐ必要があります。そこで、マルチが勿体ない私は、畝間に95cm幅の黒マルチを敷いて、花が咲いたら剥ぐ様にしています(笑)。
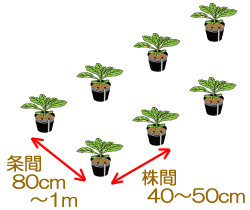 畝幅は1条植えなら60cm~70cm、2条植えなら条間を80cm~1m、株間は40cm~50cmとします。なお、一般的な半立ち種に比べて、人気の”おおまさり”は茎葉を低く広く茂らすので、半立ち種では株間・条間を狭めに、おおまさりでは株間・条間を広めに取ります!。
畝幅は1条植えなら60cm~70cm、2条植えなら条間を80cm~1m、株間は40cm~50cmとします。なお、一般的な半立ち種に比べて、人気の”おおまさり”は茎葉を低く広く茂らすので、半立ち種では株間・条間を狭めに、おおまさりでは株間・条間を広めに取ります!。
 種(豆)は、外殻を割り、薄皮を残した状態で蒔きます。種に余裕があれば、1か所に2~3粒蒔いて後で間引けばいいですが、購入した種では勿体ないので、1か所に1粒蒔きとして、予備に幾つかポット蒔きしておいて、後で抜けた所に植えるのが賢い方法かと思います(笑)。”おおまさり”を自家採種しながら栽培している私は、1か所に2粒ずつ蒔き、抜けた所は追加で種まきをして、最終的に2本立ちで栽培しています!。2本立ち栽培の方が、収量の増加が期待できる様です。
種(豆)は、外殻を割り、薄皮を残した状態で蒔きます。種に余裕があれば、1か所に2~3粒蒔いて後で間引けばいいですが、購入した種では勿体ないので、1か所に1粒蒔きとして、予備に幾つかポット蒔きしておいて、後で抜けた所に植えるのが賢い方法かと思います(笑)。”おおまさり”を自家採種しながら栽培している私は、1か所に2粒ずつ蒔き、抜けた所は追加で種まきをして、最終的に2本立ちで栽培しています!。2本立ち栽培の方が、収量の増加が期待できる様です。
種まきで一番の注意点は、何と言っても水やり!。枝豆やエンドウ豆、インゲン豆等では、発芽率を高めるために、事前に水に浸けて発根させてから種を蒔くことがありますが、ラッカセイは事前の水浸けは厳禁です!。直播きする場合は、前日に雨が降ったら一日先延ばしにし、よっぽど乾燥していない限り、種まき前後の灌水も不要です。日照りが続いている場合は、前日に灌水しておくと、ちょうど良さげ。ポット蒔きの場合は、種まき時に灌水したら、後は基本的に発芽まで水やりは不要です。ちなみに私は、ポット蒔きしておいた種を、なんと野ネズミに食べられてしまったことがあります!。直播きした種を鳥に食べられる心配をするより、ポット蒔きした種をネズミに食べられないか心配する方が先かもしれませんよ(汗)。なんとネズミは、落花生が大好物なんだそうです…。
ラッカセイは、芽出しにさえ成功すれば、あとは10月~11月の収穫期まで、ほとんど手が掛かりません!。

必要な管理作業は、草取りと、花が咲いた時にマルチを剥いだり、追肥して中耕する作業くらいです。花が咲き終わると、子房柄が伸びて地中に潜り込みますが、地面が固いと問題です(汗)。マルチをしていた場合は、花が咲き出したらマルチを剥ぐと、その下の地面はフカフカしているので問題ありませんが、雨に打たれ草の根が張って硬くなってしまった場合は、草取りを兼ねて中耕し、ついでに追肥もしておきましょう(笑)。
ラッカセイの種子は地中に出来るので、収穫時期の見極めがとても難しい野菜のひとつです!。大根やニンジンは、地上に出た首の太さや、葉の大きさで判断できますが、ラッカセイはそれが出来ません…(汗)。
 収穫の適期は、花が咲いてから85日前後だそうですが、私の様なズボラは、たいていラッカセイの花が何時咲いたかなんて、すっかり忘れています…(汗)。それに、年ごとの天気の違いも多大に影響を及ぼします。私の経験では、長野盆地で5月20日頃に種まきした場合、収穫時期は10月中旬以降、実入りをよくしたい場合は、10月下旬から11月上旬が収穫の目安と判断しています。10月になると、地上の葉が黄変してきますので、いち早く黄変した株から順番に、一株ずつ試し掘りして、殻の縞模様を観察して、収穫時期を探ります!。
収穫の適期は、花が咲いてから85日前後だそうですが、私の様なズボラは、たいていラッカセイの花が何時咲いたかなんて、すっかり忘れています…(汗)。それに、年ごとの天気の違いも多大に影響を及ぼします。私の経験では、長野盆地で5月20日頃に種まきした場合、収穫時期は10月中旬以降、実入りをよくしたい場合は、10月下旬から11月上旬が収穫の目安と判断しています。10月になると、地上の葉が黄変してきますので、いち早く黄変した株から順番に、一株ずつ試し掘りして、殻の縞模様を観察して、収穫時期を探ります!。

おおまさりなどラッカセイを茹でて食べる場合には、茹でると日持ちがせず、一度に収穫しても食べきれないので、早め早めに1~2株ずつ収穫して、先に食べ始めると良いでしょう。それに、売り物にするならちゃんと熟す必要がありますが、自家用であれば少し若いくらいの方が柔らかいので、特におおまさりなどの茹で落花生は、早取りするのもおすすめです!。実入りが悪い未熟なラッカセイは「しなす」と呼ばれ、売り物や人様におすそ分けするには値しませんが、家で食べる分には茹でると殻ごと食べられて甘いため、人によっては『しなすの方が大好き』と珍重さるほどです(笑)。
なお、一層の実入りを期待し過ぎて、収穫が遅れてしまうと、秋の長雨にあってラッカセイの種子が地中で発芽してしまったり、コガネムシの幼虫や野ネズミの食害による被害に合うことがあります!。また、莢が子房柄(ヒモ)から外れて地中に残ってしまい、収穫作業が大変になることも…(汗)。
 ラッカセイの収穫は、茎葉を掴んでゆっくり揺らしながら、子房柄の先に着いたラッカセイの種子を出来るだけ落とさない様に、地面から引き抜いて収穫します。地中にラッカセイの種子を沢山残してしまうと、後でスコップで土を掘り起こしながら拾わないとならないので、大変です(汗)。そのためにも、収穫遅れは避けたいところ!。
ラッカセイの収穫は、茎葉を掴んでゆっくり揺らしながら、子房柄の先に着いたラッカセイの種子を出来るだけ落とさない様に、地面から引き抜いて収穫します。地中にラッカセイの種子を沢山残してしまうと、後でスコップで土を掘り起こしながら拾わないとならないので、大変です(汗)。そのためにも、収穫遅れは避けたいところ!。
千葉県などラッカセイの特産地では、収穫した株は、逆さにして地面に置くか、野積み(ぼっち)にしてビニールシートを掛け、1~2か月間も乾燥させながら、追熟を図るそうです。その間に落花生は、中のデンプンが糖化して甘みが増し、渋みが抜けてコクが出ると言われています。ただし、茹でラッカセイにする”おおまさり”は、収穫後すぐに茹でた方が美味しいそうですよ!。
 しかし、我が家の粘土質の畑で栽培したラッカセイは、干しただけでは、そう簡単に土が落ちません(汗)。そこで、収穫したら直ぐに莢を外し、屋外の水道で水洗いして、土(泥)を洗い落とします。その後、縁側などに並べて、天日乾燥させます。乾かす前に土を洗い流しておかないと、乾いてからでは土を落とすのが大変ですから…(汗)。
しかし、我が家の粘土質の畑で栽培したラッカセイは、干しただけでは、そう簡単に土が落ちません(汗)。そこで、収穫したら直ぐに莢を外し、屋外の水道で水洗いして、土(泥)を洗い落とします。その後、縁側などに並べて、天日乾燥させます。乾かす前に土を洗い流しておかないと、乾いてからでは土を落とすのが大変ですから…(汗)。
まず調理する前に、来年の種とする、大粒で形の良い落花生を選び、乾燥保存して取っておきましょう!(笑)。
乾燥させたラッカセイは、主に煎って頂きます。殻つきのまま、あるいは殻を剥いてから煎る方法もありますが、いずれもフライパンで焦げない様に煎るには、時間と手間が掛かります(汗)。そこで、オーブンで調理するのが手っ取り早いのですが、調理時間の設定が問題…。こればかりは、自宅のオーブンに合った調理時間を、経験で学んでいただくしかありません(笑)。
一方、「おおまさり」品種は、茹でて食べるのがおすすめです。収穫したら直ぐに水洗いし、水から30~40分ほど塩茹でして頂きます。塩加減や茹で時間などは、これまた経験で好みを探ってください(笑)。食べきれず残った茹でラッカセイは、冷蔵だと数日しか持ちませんので、冷凍保存してください。解凍は、自然解凍でもチンでも構いません。ちなみに、おおまさりは”茹で専用”と言う人もいますが、私は乾燥さえて煎って食べても美味しい思います!。試しに、全部を茹でてしまわずに、食べきれない分の半部くらいは乾燥保存し、お正月にでも煎って食べてみてください(笑)。
「おおまさり」は、茹でて食べるのがおすすめ!。我が家流のおおまさり落花生の茹で方レシピを紹介しておきましょう。ただし、乾燥させて煎っても美味しいですよ(笑)。
茹で時間は、塩を入れて水から35~45分くらい。火力や食べる人の好みによって固さを茹で時間で調整します。圧力鍋を使う場合は、圧力時間は10分が目安ですが、前後の加圧・減圧時間と、圧力鍋を出して洗って仕舞っての手間を考えたら、鍋で茹でた方が良さげです(笑)。電子レンジだと、水を張った耐熱皿に、殻付きのままの落花生を平らに並べて、ラップをして600Wで10分程度チンします。手っ取り早いですが、一度に大量には作れないので、やっぱり水茹でがおすすめですね(笑)。
おおまさりは、収穫してすぐに茹でて食べるのが、美味しく頂く秘訣です。ただし、茹でラッカセイは、冷凍保存しないと日持ちがしません。冷蔵保存して、2-3日で食べきりましょう。そこで、食べる都度、必要な量を収穫して、すぐに茹でて食べるのがおすすめです!。自分で栽培しているからこそ出来る、最高の贅沢ですね(笑)。

栽培地域や播種の時期にもよりますが、長野辺りでも10月に入ると、そろそろラッカセイの収穫可能な時期がやってきます。葉の色が変わり出している株から順番に、実(豆)の付き方や熟し状況を探るため、試し掘りを始めましょう。株の端を移植ゴテで掘り、出てきたラッカセイの殻の網目模様がはっきりしていれば、収穫適期です。10月に入ったばかりだと、まだ熟した実と未熟な実が混ざっているかもしれませんが、そこそこ食べられそうなら、試しに1株掘り上げてみましょう。数粒掘って『まだまだだな』と感じたら、丁寧に埋め戻しておきます(汗)。
試し掘りの段階だと、1株で、だいたい両手を広げてすくって零れる位の量のラッカセイが収穫できます。重量は500グラム前後。大鍋で茹でるには、1~2株分位がちょうどいい量です!。
後は、数日おきに『試し掘り』と称して1~2株ずつ収穫を繰り返せば、本格収穫の時期まで2~3週間も、長い期間、新鮮でおいしい茹でラッカセイが食べ続けられますよ(笑)。
収穫したばかりのラッカセイには土が付いているので、あれば家の外の水道で、そこそこキレイに土を洗い流します。その後、台所に移り、さらにキレイに洗います。お米を研ぐようにして、数回ほど溜め水洗いして、洗い水に砂が残らなくなればOKです。
茹でるラッカセイの量(嵩)の2倍くらいが入る鍋を用意します。
鍋にラッカセイと塩を入れ、吹きこぼれない程度にたっぷりの水を注ぎ、落し蓋をします。
入れる塩の量は、大さじ2 くらいと適当…(汗)。多めに入れても、ラッカセイ自体にはほとんど塩味は付きませんし、塩を入れなくても茹でラッカセイは美味しく食べられます!。どうしてもレシピに拘る人は、水の量に対して3%が目安だそうです(笑)。ちなみに、大さじ1杯の塩の重量は約15グラムなので、1リットルの水に対して3%だと大さじ2 ですね!。
茹で時間は、沸騰してから30~40分くらい。これまたアバウトですが、我が家は出力の弱い電気調理器を使っているので、沸騰するまでとても時間が掛かります。火力にもよると思うので、茹で上がりの硬さを試食しながら、お好みで茹で時間を調整してください。落し蓋をしない場合は、出来るだけかき混ぜながら茹でます。
茹で上がったら、ざるにあけて水を切り、そのまま頂きます。水にはさらしません。少し蒸らすと、ふっくらします。あと、温かいうちに頂く茹でたて落花生は、とても美味しいですよ!(笑)。未熟で小さな「しなす」の実は、殻ごと食べられますので、一度お試しあれ!。
![]()