都会からリタイアして地元の田舎に戻り始めた家庭菜園、少しずつ学んだ野菜の育て方のコツをまとめてみました。
一般的には、「ゴーヤ」や「ゴーヤー」と呼ばれることが多いですが、標準和名は「ツルレイシ」という、ウリ科の植物です。未熟な果実を野菜として食しますが、その果肉が苦いことから、「ニガウリ」とも呼ばれ、それが方言で訛って、ニガゴリとかトーグリ、ニガゴイなどと呼ぶ地域もあります。原産地は熱帯アジアとされ、日本へは17世紀ごろに、中国から琉球王朝を経由して渡来した様です。そのため、主に沖縄など南西諸島や、南九州で栽培が広まりました。
20年ほど前までは、沖縄に行ったことが無い本州に住む人達の多くが、ゴーヤなんて食べ物(野菜)があることすら知らず、知っていても苦くて嫌いという人がほとんどだったと思います。それが、2000年7月に「沖縄サミット」が開催され、記念して発行された二千円札の絵柄になった守礼門や、晩餐会の会場に選ばれた首里城など歴史的建造物が、全国的に知られるところとなり、沖縄への観光ブームが巻き起こります!。2001年4月からは、NHK朝の連続テレビ小説「ちゅらさん」が放送され、沖縄の長閑な小さな離島・小浜島で育った、ヒロインの恵里(国仲涼子)とおばぁ(平良とみ)らの人柄が人気を呼び、高い視聴率を記録、沖縄人気がさらに高まります。ちゅらさんには、「ゴーヤーマン」というキャラクターも登場し、ゴーヤの認知度も高まりました(笑)。そういえば、私がダイビングを始めて、年に何回も沖縄の離島を訪れる様になったのも、この頃でした…(汗)。こうして、ゴーヤは栄養価が高くて、夏バテ防止にも効く健康によい食材として注目されるようになり、今や関東のスーパーでも普通に売られるまでに広まりました。また、地球温暖化の影響で猛暑が続くと、環境にやさしい”緑のカーテン”(グリーン・カーテン)としても栽培が広まっています。

品種名が表示されたゴーヤの種を買うとなると、なぜか意外と高くて、少量の種でも400円~500円くらいします。百円ショップのダイソーでは、2袋=100円でゴーヤの種が売られていますが、品種名が書かれていないので、果たして自家採種できるのか心配です。それに、ゴーヤの種の発芽率は低く、上手に蒔かないと発芽してくれません(汗)。そこで、もしゴーヤを2~3本しか植えないなら、苗は買った方が手っ取り早いです。安ければ100円、高くても198円くらいで売られています。
植える苗の数の目安ですが、露地植えでも株間は1m位取った方がいいので、例えば幅4間の大きなサッシ窓全体に緑のカーテンを作るとしたら、6~7本くらい苗が欲しい所です。しかし、プランターでの栽培を考えているのであれば、相当大きなプランターでも、1個のプランターに植える苗は1本だけに留めましょう!。ゴーヤは、夏の猛暑や水枯れにも耐え、さほど肥料も必要とせず痩せ地でも育つ、とても優秀な野菜ですが、その分、とても太くて丈夫な根を、とても広く深く生やします。小さなプランターや、いくら大きなプランターでも2苗も植えたら、すぐに根の行き場がなくなってしまい、実がほとんど成りません(汗)。
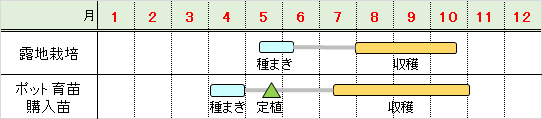
ゴーヤの種はとても硬く、上手く発芽させられずに種を腐らせてしまい、種まきに失敗するケースがとても多いです。
 上手く発芽させるコツは、なんと言っても、十分に暖かくなってから種まきをすること。しかし、一日でも早くゴーヤが食べたい、緑のカーテンを仕上げたいと思うと、どうしても年々、種まきの時期が早まってしまうのが、人の常(汗)。そこで、発芽率を高めるために、種まきをする前の一昼夜、種を布に包んで、水に浸しておきましょう!。ちなみに、ゴーヤの種を種まき前に水に浸けるのは、”休眠打破”させるためではなく、殻を柔らかくして、発芽しやすい環境を整えてあげるためです。本当の休眠打破が必要な種は、夏蒔きのレタスやホウレンソウなど、限られた一部の野菜です。しかも、特に休眠打破せずともある程度は発芽してくれます!。また、種の硬い殻が割れて芽が出やすい様に、種の尖った部分を爪切りで切ったり、殻に傷をつけたりすると良いという人もいますが、私的には、してもしなくても、結果は同じような気がします…(汗)。
上手く発芽させるコツは、なんと言っても、十分に暖かくなってから種まきをすること。しかし、一日でも早くゴーヤが食べたい、緑のカーテンを仕上げたいと思うと、どうしても年々、種まきの時期が早まってしまうのが、人の常(汗)。そこで、発芽率を高めるために、種まきをする前の一昼夜、種を布に包んで、水に浸しておきましょう!。ちなみに、ゴーヤの種を種まき前に水に浸けるのは、”休眠打破”させるためではなく、殻を柔らかくして、発芽しやすい環境を整えてあげるためです。本当の休眠打破が必要な種は、夏蒔きのレタスやホウレンソウなど、限られた一部の野菜です。しかも、特に休眠打破せずともある程度は発芽してくれます!。また、種の硬い殻が割れて芽が出やすい様に、種の尖った部分を爪切りで切ったり、殻に傷をつけたりすると良いという人もいますが、私的には、してもしなくても、結果は同じような気がします…(汗)。
 私の経験上、もっとも確実に発芽させる方法は、前作のこぼれ種から自然発芽するのを待つことです(笑)。前作の秋に自家採種した種を保存しておいて、春になってから蒔いても、なかなか上手く発芽しないのに、なぜか暖かくなれば、勝手にこぼれ種から自然に芽が出てきます(汗)。そのためにも、株が元気な早い時期に、大きくて形のよいゴーヤの実を何個か収穫せずにツルに残して、熟させて種をわざと地面にこぼします。もちろん、必要な数だけ自家採種しても構いません。ただし、長野県の様に寒い地域だと、地表面に落ちただけでは種が越冬できないので、秋に棚を撤去したら、深めによく耕し、春になったら再び耕し返してあげましょう。
私の経験上、もっとも確実に発芽させる方法は、前作のこぼれ種から自然発芽するのを待つことです(笑)。前作の秋に自家採種した種を保存しておいて、春になってから蒔いても、なかなか上手く発芽しないのに、なぜか暖かくなれば、勝手にこぼれ種から自然に芽が出てきます(汗)。そのためにも、株が元気な早い時期に、大きくて形のよいゴーヤの実を何個か収穫せずにツルに残して、熟させて種をわざと地面にこぼします。もちろん、必要な数だけ自家採種しても構いません。ただし、長野県の様に寒い地域だと、地表面に落ちただけでは種が越冬できないので、秋に棚を撤去したら、深めによく耕し、春になったら再び耕し返してあげましょう。
ゴーヤは、特に誘引しなくても、ツルから伸びた細い巻きヒゲが、勝手に近くの物や紐に巻き付いて、上へ上へと成長していきます。そのため、ツルが伸び出したら、早い時期に、ネットや紐で棚を作ってあげましょう。
ただし、ゴーヤのツルはとても長く伸び、次々に脇芽も伸びて密に茂り、さらに大きな実を付けると、とても重くなります。細い紐や、細いネットだと、その重さに耐えられず、切れたり破れてしまうことがあります。そのためにも、ある程度しっかりした資材を使って棚を張り、あまり傾斜を緩くしないのが、きれいな”緑のカーテン”に仕上げるコツです。
私は、ナイロン素材で出来た市販のキュウリネットなどで棚を作ると、撤去するときに処分に困るので、燃やしてもいいし腐らせてもいい麻で出来た、安価な「ジュート紐」(バインダー紐、麻ひも)を使って棚を作っています。ただし紐だと、基本的に縦か、せいぜい少し斜めにしか張れないので、出来るだけ本数を多くして、紐の間隔を50cm以内くらいに狭めると、ツルが勝手に横方向にも伸びて、最後にはちゃんとしたグリーン・カーテンに仕上がります!。

なお、親づるが伸びてきたら摘心せよと言いう人もいますが、私は不要だと思っています(汗)。スイカ栽培では、親づるを早めに摘心することで、数本だけ残した子づるの成長を早め、子づるに成らせる1株に2~3個の実に、確実に栄養を届けやすくします。しかし、ゴーヤは緑のカーテンを作る目的もあるので、出来るだけ脇芽は沢山伸ばしたいところですし、放任していても、ちゃんと根が張り肥料が行き届けば、1株で何十個ものゴーヤの実が収穫できます(笑)。そもそも、ゴーヤの雌花は6月下旬の夏至を迎え、短日・低温化で分化するようになるため、それ以前にいくら子づるを伸ばしても、咲く花は雄花ばかりで、ほとんど実着きは期待できません(汗)。それよりも、親づるをできるだけ早く上に伸ばして、元気で大きな株に仕立てた方が、最終的なゴーヤの収量を期待できますし、早くグリーン・カーテンが仕上がる様に感じているからです。
 実が十分成長したら、熟れ過ぎて変色し始める前に、ヘタをハサミで切って収穫します。野菜は、夜のうちに実に水分が蓄えられるので、基本的に朝方に収穫するのが良いとされています。ゴーヤも、朝方にはパンパンに張っていた実が、暑い日差しを受けて夕方になると、フンニャリとしてしまいます(笑)。ちなみに、緑のゴーヤの実も熟すと、赤く変色します。見た目的にグロテスクな色になるので、私は食べませんが、トロっと柔らかく甘くなって、熟した赤いゴーヤの方が好きっていう人も、たまにいます…(汗)。
実が十分成長したら、熟れ過ぎて変色し始める前に、ヘタをハサミで切って収穫します。野菜は、夜のうちに実に水分が蓄えられるので、基本的に朝方に収穫するのが良いとされています。ゴーヤも、朝方にはパンパンに張っていた実が、暑い日差しを受けて夕方になると、フンニャリとしてしまいます(笑)。ちなみに、緑のゴーヤの実も熟すと、赤く変色します。見た目的にグロテスクな色になるので、私は食べませんが、トロっと柔らかく甘くなって、熟した赤いゴーヤの方が好きっていう人も、たまにいます…(汗)。

ゴーヤの食べ方は、やはり一番は、「ゴーヤチャンプル」がおすすめですね!(笑)。様々なレシピが紹介されていて、豚肉やスパム(SPAM)![]() など色々な食材が混ざるとそれも美味しいのですが、私はゴーヤと豆腐だけのシンプルなチャンプルが、一番好きかもしれません(笑)。
など色々な食材が混ざるとそれも美味しいのですが、私はゴーヤと豆腐だけのシンプルなチャンプルが、一番好きかもしれません(笑)。
![]()