都会からリタイアして地元の田舎に戻り始めた家庭菜園、少しずつ学んだ野菜の育て方のコツをまとめてみました。
ナス(茄子、茄、ナスビ、那須)は、ナス科ナス属の植物の果実で、原産地はインド東部と言われていますが、日本でも1千年以上も前から栽培されている、とても古くから食べられてきた野菜のひとつです。そのため、私たちの生活や文化とも、様々な場面で深く結びついています。
例えば、『初夢は、一富士・二鷹・三茄子(なすび)』と称されるほど、ナスは縁起の良い物の代表格。その理由は、2018年正月放送の『ブラタモリ×鶴瓶の家族に乾杯 初夢スペシャル ~富士山・三保松原~』で紹介されていましたが、徳川家康も大好物だったという初モノの「折戸茄子」に由来しているそうです(笑)。また、『秋茄子は嫁に食わすな』とは、美味しい秋ナスを惜しむ姑の嫁憎さの心境とも、身体を冷やすとされる夏野菜を食べ過ぎる嫁を案じた姑の心境とも言われ、その由来は定かでありません(汗)。また当地でも、お盆にはキュウリとナスで作った「精霊馬」を仏壇に供えますが、キュウリの馬は故人があの世から早く戻って来られるように、ナスの牛はあの世に帰るのが少しでも遅くなるようにとの願いが込められたものだそうです。


 病害虫による被害は比較的少ないとされますが、連作による青枯れ病やウドンコ病、アブラムシやダニがつく場合があります。
病害虫による被害は比較的少ないとされますが、連作による青枯れ病やウドンコ病、アブラムシやダニがつく場合があります。
買ったナスの苗、特に接ぎ木苗は徒長して大きくなりやすく、倒伏防止のために支柱を立てたり棚を作ったりするのが面倒なので、私はできるだけ種から栽培するようにしています。寒冷地で早い時期に種から育てた苗は、葉や脇芽の間隔が詰まったコンパクトな樹形になるので、短い支柱を一本立てて、茎を2か所ほど縛りつけておけば、滅多に倒れることはありません。
しかし、寒冷地でナスを種から育てようとすると、どうしても収穫が遅くなってしまいます。そこで我が家では、メインの丸ナスは種から育て、サブの中長ナスの苗を1~2本だけ買って、ゴールデンウィーク明けくらいに定植するようにしています。3月中旬から下旬に種を蒔いた苗が定植できる様になるのは、5月下旬から6月上旬、買った苗より約1か月ほど遅れてしまいます。その代り、夏の更新剪定をしなくても、晩秋の遅い時期まで長く収穫し続けることが出来ますよ!。
 ナスは夏から秋にかけて収穫できる野菜ですが、種まきから収穫できる様になるまでは、4か月以上も掛かります(汗)。可能であれば2月中に種まきをしたいところですが、寒冷地ではトンネル育苗でもムリ。保温ケースに土を入れて種をまき、家の中の暖房の効いた部屋の中で育苗するしかありません。3月中旬以降であれば、長野でもトンネル内で発芽・育苗が可能となります。しかし、定植できるようになるのは、2か月以上先の5月下旬から6月上旬ごろ、収穫出来るようになるのは7月中旬以降です。
ナスは夏から秋にかけて収穫できる野菜ですが、種まきから収穫できる様になるまでは、4か月以上も掛かります(汗)。可能であれば2月中に種まきをしたいところですが、寒冷地ではトンネル育苗でもムリ。保温ケースに土を入れて種をまき、家の中の暖房の効いた部屋の中で育苗するしかありません。3月中旬以降であれば、長野でもトンネル内で発芽・育苗が可能となります。しかし、定植できるようになるのは、2か月以上先の5月下旬から6月上旬ごろ、収穫出来るようになるのは7月中旬以降です。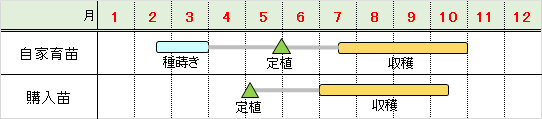
 一番花が咲く直前、本葉が7~8枚になった頃が、定植の適期。しかし、寒冷地で種から育苗した苗は、成長が遅々として、なかなかそのサイズにまで育ちません。そこで、地温を上げるために黒マルチをした畝に、早めに小さい苗を定植し、保温ポットを被せたり、肥料袋で風よけをして育てた方が、早く育つように思います(汗)。
一番花が咲く直前、本葉が7~8枚になった頃が、定植の適期。しかし、寒冷地で種から育苗した苗は、成長が遅々として、なかなかそのサイズにまで育ちません。そこで、地温を上げるために黒マルチをした畝に、早めに小さい苗を定植し、保温ポットを被せたり、肥料袋で風よけをして育てた方が、早く育つように思います(汗)。 ナスの苗を植え付ける間隔は、畝間が1.5m~2.0m、株間は50cm~60cm。買った接ぎ木苗は株が大きく育つので、株間は広めにします。種から育てた苗だと、少し狭めても大丈夫です。まだ遅霜の心配のある時期に早めに定植した場合は、保温ポットを被せましょう。また、苗が小さいうちに定植した場合は、肥料袋などを被せて風よけをした方がいいですが、それでも幼苗が強風で倒されないように、早めに支柱を立て、紐で8の字に結んでおきます。
ナスの苗を植え付ける間隔は、畝間が1.5m~2.0m、株間は50cm~60cm。買った接ぎ木苗は株が大きく育つので、株間は広めにします。種から育てた苗だと、少し狭めても大丈夫です。まだ遅霜の心配のある時期に早めに定植した場合は、保温ポットを被せましょう。また、苗が小さいうちに定植した場合は、肥料袋などを被せて風よけをした方がいいですが、それでも幼苗が強風で倒されないように、早めに支柱を立て、紐で8の字に結んでおきます。 定植後は苗が倒れないように、すぐに支柱を立てて、茎を紐で支柱に縛りつけ、誘引します。ただし、きつく縛る必要はありません。大きく傾かない程度に、緩めに紐で、茎と支柱とを8の字に括っておけば大丈夫です。
定植後は苗が倒れないように、すぐに支柱を立てて、茎を紐で支柱に縛りつけ、誘引します。ただし、きつく縛る必要はありません。大きく傾かない程度に、緩めに紐で、茎と支柱とを8の字に括っておけば大丈夫です。
株が大きくなり、枝先に大きな実をつけるナスは、とても不安定で、強い風が吹いたりすると、枝が折れてしまったりします。そこで1苗毎に2~4本の支柱を立てて、2本仕立てや3本仕立て、4本仕立てに立ち上げます。また、畝を跨ぐように棚を作り、そのこ長い横棒を載せて、ナスの枝を載せる仕立て方や、大きな支柱の上から紐で枝吊りする方法などがあります。ただし、寒冷地で時間をかけて育てた苗であれば、さほど大株にはならないので、私は細くて短い支柱を1本立てるだけです!。それでも、台風にも十分耐えられています。何年かに1回くらいは何本か倒されますが・・・(笑)。

定植後、一番花が咲いたら、花のすぐ下の側枝を1本と、花のすぐ上の側枝を1本ずつ残し、他は芽欠きして、3本仕立てを基本とします。とは言え、たくさん実を採りたいので、ついつい枝を残しがちですが、さほど気にする必要はありません(笑)。
 花が咲きだしたら、肥料好きなナスのために、2~3週間毎に追肥をします。
花が咲きだしたら、肥料好きなナスのために、2~3週間毎に追肥をします。
ナスの花を観察して、中心の雌しべが、周りの雄しべに隠れるほど短い場合(短花柱花)は、肥料切れのサインです。雌しべが元気に長く、雄しべの中からピョンと突き出ている花(長花柱花)を咲かせましょう!。
収穫が始まり、夏の暑い時期になると、だんだんと株が弱ってきます。そこで、混み合った枝や、伸びすぎた枝、元気のない枝を切り落とす、更新剪定をします。同時に、株元から20cm位離れた場所にスコップを刺して、根の先を切ってやると、後から新しい根が生えて、その後、株も元気を取り戻しますよ!。
花が咲いてから、2~3週間で収穫期を迎えます。実を大きくし過ぎると株が弱ってしまうので、最初のうちは実を若採りして、丈夫な株に育てましょう。数日おきに収穫できるようになったら、後はあまり気にする必要はありません。食べごろサイズを見計らって、順番に収穫していきます。
 ただし、全部が全部、良い形状のナスばかり収穫できるとは限りません。たまには「ボケナス」も出来てしまいます(汗)。『ボケナスとは何だ!』と叱らないでください(笑)。ボケナスの語源は、成長異常により表面が凸凹していて色ツヤがないナスの「つやなし果」のこと(諸説あります)。他にも、小さくて石のように固くて大きくならない「石ナス」や、裂果や奇形果が成る場合もあります。こうした実が成るには様々な原因が考えられますが、多くの場合は、水不足が主な原因です(変形は、害虫による食害が原因の場合もあり得ます)。
ただし、全部が全部、良い形状のナスばかり収穫できるとは限りません。たまには「ボケナス」も出来てしまいます(汗)。『ボケナスとは何だ!』と叱らないでください(笑)。ボケナスの語源は、成長異常により表面が凸凹していて色ツヤがないナスの「つやなし果」のこと(諸説あります)。他にも、小さくて石のように固くて大きくならない「石ナス」や、裂果や奇形果が成る場合もあります。こうした実が成るには様々な原因が考えられますが、多くの場合は、水不足が主な原因です(変形は、害虫による食害が原因の場合もあり得ます)。
 ナスは肥料と水が大好きなので、肥料切れ・水切れが起こらない様に、日照りが続くようであれば夕方に灌水(水遣り)してあげましょう。また、閉じた花弁や枯れた花弁は早めに取り除いてやると、実付きが良くなりますよ!。
ナスは肥料と水が大好きなので、肥料切れ・水切れが起こらない様に、日照りが続くようであれば夕方に灌水(水遣り)してあげましょう。また、閉じた花弁や枯れた花弁は早めに取り除いてやると、実付きが良くなりますよ!。
![]()