都会からリタイアして地元の田舎に戻り始めた家庭菜園、少しずつ学んだ野菜の育て方のコツをまとめてみました。
私がクウシンサイを知ったのは、東京に出て中華料理で「クウシンサイと牛肉の炒め物」を食べて美味しいと思ったのが最初だった気がします。なので、余った苗を隣近所にお裾分けしても、長野県で生まれ育ったオバチャン達は、『クウシンサイなんてハイカラな野菜は、食べたことも見たこともない』と言います(笑)。
しかし、標準和名は「ヨウサイ(蕹菜)」と言い、ウィキペディアにもヨウサイという見出しで掲載されています。元は中国で「ウォンツァイ」と発音されていた様ですが、中国語も方言が多様で、地域によって「エンツァイ(蓊菜)」とか「コンシンツァイ(空心菜)」と発音し、それが日本に伝わって「ヨウサイ」とか「エンサイ」、「エンツァイ」、「クウシンサイ」と呼ばれる様になったみたいです。
ちなみに、”空心菜”の「心」の字に「芯」を使った、カタカナで”くうしんさい”との読みは、商標登録がされており、権利者によると、『文字が違っても呼称が同じ場合(クウシンサイと読める場合)は法に抵触し違反する』とのことです。詳細は、J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で”クウシンサイ”と検索してください。1999年に登録され、2019年に10年間の更新登録が済んでいます。なお、「芯」のくさかんむりは、3画と4画の両方の登録商標があります。面倒くさい世の中になってしまいました…(汗)。
 熱帯の東南アジア原産とされ、ヒルガオ科サツマイモ属のつる性多年草です。茎葉はサツマイモに似ていますが、その名のとおり、茎の中が空洞になっています。湿地帯や水辺でも育つ野菜ですが、猛暑日が続く夏の暑さにもとても強く、日照りで他の野菜が元気がなくても、畑ではクウシンサイとツルムラサキだけは、緑々と元気に育ちます!(笑)。また、秋になると、アサガオにそっくりの花が咲きます。ツルムラサキやオカワカメなどと同様に、とても栄養価が高い野菜で、ビタミンやミネラルが豊富に含まれています。特に鉄分が多いことから、疲労回復にも効果があるとか。ツルムラサキなどの様なネバネバ感はほとんど感じないので、ネバネバが嫌いな人には、夏の健康野菜には最適かもしれません。ただし、ちょっとエグミを感じるので、人によっては好き嫌いがありそうです。
熱帯の東南アジア原産とされ、ヒルガオ科サツマイモ属のつる性多年草です。茎葉はサツマイモに似ていますが、その名のとおり、茎の中が空洞になっています。湿地帯や水辺でも育つ野菜ですが、猛暑日が続く夏の暑さにもとても強く、日照りで他の野菜が元気がなくても、畑ではクウシンサイとツルムラサキだけは、緑々と元気に育ちます!(笑)。また、秋になると、アサガオにそっくりの花が咲きます。ツルムラサキやオカワカメなどと同様に、とても栄養価が高い野菜で、ビタミンやミネラルが豊富に含まれています。特に鉄分が多いことから、疲労回復にも効果があるとか。ツルムラサキなどの様なネバネバ感はほとんど感じないので、ネバネバが嫌いな人には、夏の健康野菜には最適かもしれません。ただし、ちょっとエグミを感じるので、人によっては好き嫌いがありそうです。
この野菜も、育てるのに、ほとんど手が掛かりません(笑)。つる性ですが、支柱やネットには巻き付かないので、広めの場所で、放任栽培するのが一番です。安くタネも売られていますが、家庭菜園では1-2株もあれば十分なので、苗を買ってきて育てる方が、手っ取り早いです。ただ、種の寿命はツルムラサキよりかなり長いので、一袋買って、何年か蒔き続けるのもアリです。また、ツルムラサキの様に、こぼれ種からの自然発芽は期待できません。

 クウシンサイの種は 200円前後と安いので、タネから育ててもいいのですが、せいぜい2株もあれば十分なので、育った苗を安く買ってきて植えた方が、早く収穫期を迎えることが出来ます。ただし、クウシンサイの種の寿命は長いので、余った種を何年も使いまわせば、種を買った方が大分お買い得ですね(笑)。
クウシンサイの種は 200円前後と安いので、タネから育ててもいいのですが、せいぜい2株もあれば十分なので、育った苗を安く買ってきて植えた方が、早く収穫期を迎えることが出来ます。ただし、クウシンサイの種の寿命は長いので、余った種を何年も使いまわせば、種を買った方が大分お買い得ですね(笑)。
ちなみに、九州以北の露地栽培では、花は付けても種は出来ないとのことなので、自家採種は無理です。
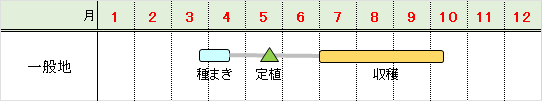
 苗を植えた後の管理作業は、ほぼ不要です!(笑)。必要なのは、草取りくらいです。
苗を植えた後の管理作業は、ほぼ不要です!(笑)。必要なのは、草取りくらいです。
私は追肥もしたことがありませんが、成長が遅いようだと追肥して、中耕・土寄せしてあげましょう。株が大きくなってからだと、どこが株元か分からないほど茎葉が繁るので、追肥は株元が見えるうちにするのが良さげです。
 株が一抱えくらいまで成長したら、収穫を開始します。早めに主枝を摘心すると、脇芽の成長が促されます。次々と生える脇芽の先端 15cm~20cmを切り取って収穫し、炒めたり和えたり、好みの食べ方で、暑い夏を乗り切りましょう!。我が家の冷蔵庫には、クウシンサイを炒める時にだけしか使わない「ナンプラー」が、必ず入っています(笑)。
株が一抱えくらいまで成長したら、収穫を開始します。早めに主枝を摘心すると、脇芽の成長が促されます。次々と生える脇芽の先端 15cm~20cmを切り取って収穫し、炒めたり和えたり、好みの食べ方で、暑い夏を乗り切りましょう!。我が家の冷蔵庫には、クウシンサイを炒める時にだけしか使わない「ナンプラー」が、必ず入っています(笑)。
暑さには強靭なクウシンサイも、寒さにはめっぽう弱く、10月に入ると収穫は滞り、気温が10度を下回る10月下旬には枯れ出します。単に、乾燥して枯れてくれればいいのですが、枯れると腐敗して、べっとりと地面に張り付いてしまい、撤去するのが大変です。収穫が滞り始めたら、思い切ってさっさと片付けた方が、後処理は楽です!。
![]()