都会からリタイアして地元の田舎に戻り始めた家庭菜園、少しずつ学んだ野菜の育て方のコツをまとめてみました。

 ソラマメ(空豆)は、マメ科の一年草または越年草です。豆果の莢(さや)が空に向かって着果することから”空豆”と呼ばれるようになったそうですが、実(豆)が熟すと莢はその重みで垂れ下がり、地面を向きます…(汗)。また、さやの形が蚕(かいこ)に似ていることから、”蚕豆”という当て字も生まれました。イスラエルの新石器時代の遺跡からも出土するほど古代から食されていた植物で、原産地は地中海周辺や西南アジアと推測されていますが定かでありません。日本にも大変早く8世紀ごろには渡来したと言われており、野良豆(のらまめ)、夏豆(なつまめ)、天豆(てんまめ)など、様々な呼び名が伝わっています。
ソラマメ(空豆)は、マメ科の一年草または越年草です。豆果の莢(さや)が空に向かって着果することから”空豆”と呼ばれるようになったそうですが、実(豆)が熟すと莢はその重みで垂れ下がり、地面を向きます…(汗)。また、さやの形が蚕(かいこ)に似ていることから、”蚕豆”という当て字も生まれました。イスラエルの新石器時代の遺跡からも出土するほど古代から食されていた植物で、原産地は地中海周辺や西南アジアと推測されていますが定かでありません。日本にも大変早く8世紀ごろには渡来したと言われており、野良豆(のらまめ)、夏豆(なつまめ)、天豆(てんまめ)など、様々な呼び名が伝わっています。
実(豆)の付き方は枝豆に似ていますが、枝豆の様に多くは収穫できないため、和食や洋食でも高級食材として扱われることが多いです。また、枝豆より栽培が面倒で収量も得られないため、家庭菜園でソラマメを栽培している人は少ないと思いますが、作り方のコツさえ掴めば比較的容易。それに、枝豆が出回る前の5~6月頃は、焼きそら豆なんか、居酒屋のビールのお供には最高!。酒好きの家庭菜園主には、欠かせない作物かと思いますよ(笑)。塩茹でしたり焼いて、中のマメを食べるのが一般的ですが、揚げて塩をふったものが”いかり豆(フライビーンズ)”。甘く煮てお多福豆にしたり、香川県では長野県民も大好きな醤油豆に加工するそうです!。また、ソラマメを発酵させた調味料が、中国料理で使われている豆板醤。なお、ソラマメに含まれる物質が体内で変化して、まれに食中毒症状「ソラマメ中毒」を起こすことが報告されていますが、日本ではほとんど報告されておらず、遺伝的な要因や生産地に起因する要因などが疑われていますが、定かでありません(汗)。貴重な生産物なので、珍重して適量を頂くのがよろしいかと…。


ソラマメの栽培は、エンドウ栽培と同様に、よほどの寒冷地を除き、幼苗が越冬できる地域では、秋に種を畑に直播きして、春に大きく育てて収穫する、”秋まき栽培”がおすすめです。長野盆地では、冬の最低気温がマイナス15度くらいまで下がることが数年に何回かありますが、なんとか耐え凌いでいます。最低気温がマイナス10度くらいまでの地域なら、問題なく越冬できると思いますよ。
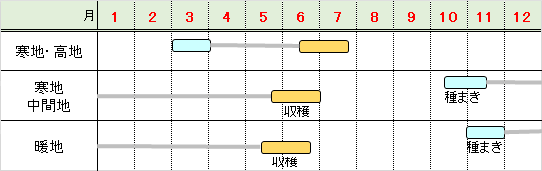
 種の蒔き方は、ソラマメの”おはぐろ”部分を下にして、発根・発芽点となる凹み部分を斜め上に向け、おはぐろの反対側のお尻部分が地上に薄く出る程度(豆の1/3くらい)に、土に挿して浅く埋めます。種まき時に灌水したら、後は水やりは不要です。種が地上に見えているので、鳥に狙われない様に、寒冷紗やネットを掛けるか、防鳥糸を張っておきましょう。
種の蒔き方は、ソラマメの”おはぐろ”部分を下にして、発根・発芽点となる凹み部分を斜め上に向け、おはぐろの反対側のお尻部分が地上に薄く出る程度(豆の1/3くらい)に、土に挿して浅く埋めます。種まき時に灌水したら、後は水やりは不要です。種が地上に見えているので、鳥に狙われない様に、寒冷紗やネットを掛けるか、防鳥糸を張っておきましょう。種まき後、ちゃんと発芽したら、第一の難関は越冬です。関東以南で、最低気温がマイナスになるかならないかといった地域なら全く問題ありませんが、長野だと、暖冬であれば最低気温もマイナス10度ほどなのに、寒い年だとマイナス15度以下になることもあります(汗)。
 そこで重要になるのが、種まきの時期!。越冬するのに、大きすぎず、小さすぎず、ちょうどよい大きさの苗で冬を迎えられるように、秋の天気の長期予報を参考にしながら、種まきの適期を外さないように、種まきの予定を立てましょう。ソラマメの種まきの適期は、エンドウとほぼ一緒です。長野盆地だと、10月中旬以降、10月20日前後が平年の目安です。
そこで重要になるのが、種まきの時期!。越冬するのに、大きすぎず、小さすぎず、ちょうどよい大きさの苗で冬を迎えられるように、秋の天気の長期予報を参考にしながら、種まきの適期を外さないように、種まきの予定を立てましょう。ソラマメの種まきの適期は、エンドウとほぼ一緒です。長野盆地だと、10月中旬以降、10月20日前後が平年の目安です。
霜が降りるようになったら、寒冷地では苗を保護するために、株元に敷きわらを掛けてあげましょう。
幼苗のまま越冬したソラマメは、春になり暖かくなると、急速に成長を始めます。一般的に、暖地では12月の年内に、中寒冷地では春先の3月に、主枝を摘心して脇芽の発育を促すよう指示されていますが、長野で寒い冬を越したソラマメは、摘心などしなくても、春になるとどんどん脇芽が出て、どれが主枝かわからないほど、発育を始めます(汗)。まぁ、大抵は摘心の作業をすること自体を忘れていて、気が付いたら脇芽がボウボウってことが多いんですけどね…(笑)。
期待どおり脇芽が沢山出て、背丈が40cmくらいになった頃、整枝の作業をします。だいたい1株の根本から、十数本の脇芽が発生しますが、細い枝は付け根から切って、太い枝だけ 7~8本 残します。
整枝の作業が済んだら、株元に発酵鶏糞などの堆肥を撒きます。私の気のせいかもしれませんが、化成肥料は発酵堆肥より、アブラムシを誘引する様な気がします。そして、脇芽の枝が安定する様に、中耕を兼ねて株元が隠れるくらいに土寄せし、撒いた堆肥に土を被せます。一般的に、豆類の栽培では肥料は控えめにするのが鉄則ですが、ソラマメは豆類の中では一番の肥料食いかもしれません(汗)。最初は控えめにしていた肥料も、花が咲き実が付き出す前に、ガツンと与えてあげましょう(笑)。
花が咲き出したら、いよいよアブラムシとの闘いが始まります!(汗)。無農薬にこだわらない方は、予防のためにこの頃、有機リン系の「スミチオン乳剤」や「マラソン乳剤
」など、ソラマメの害虫登録がある農薬を散布します。いずれも浸透移行性がある殺虫剤ですが、スミチオンの方が価格が高い分、残効が長い様です。
花が咲き揃い、モンシロチョウなどが散舞して十分受粉が確認できた頃、ソラマメの茎丈は、地上から80cm以上にも成長してきます。そこで、全部の茎を、地上から60~70cmくらいに摘心します。後からネットを掛けますので、外側の茎は短めに、中側の茎は長めにすると、まとまりが良くなります。
ネットで覆う前に、もう一度追肥をしておきます。鶏糞を株元に撒き、株の周りを軽くさくって中耕しながら鶏糞に土を掛けて埋めます。ちなみに、有機肥料を土に撒いてそのままにしておくと、タネバエやコガネムシを誘引し、思わぬ被害に繋がることがあります。施肥の効果を高めるためにも、土を掛けるか、土に漉き込みましょう。
 |
ダイオ 農園芸用 銀糸入 防虫ネット透光率 90% 1mm 2.1mx20m アブラムシ 青虫その他の害虫対策 価格:3,520円 |
摘心が済んだら、ソラマメの畝全体をトンネルで覆い、アブラムシの飛来を阻止します!。
幅は狭く、高さがあるトンネルを作りたいので、支柱にはグラスファイバーや樹脂で出来たフレキシブルな、「ダンポール」や「樹脂ポール![]() 」がオススメです。被覆資材は、アブラムシを防除するには目合いが0.8mm以下の、目の細かい防虫ネットが効果的ですが、目合いが細かくなるほど価格が高くなり、透光率が低下、ネットの上からの水やりに不便ですし、風通しが悪いため高温・防風面でのデメリットもあります。私が使っているのは、目合い1mmの銀糸入り防虫ネット。1mm目の防虫ネットが最も市場での流通量が多く値段がこなれ、防虫効果とコストパフォーマンスの両面でバランスが良く、家庭菜園で使うには使い勝手がいい様に思います(笑)。ちなみに、整枝の済んだソラマメの畝を覆うトンネルを作るためには、最低でもダンポールは長さ2.4m、防虫ネット(寒冷紗)の幅は2.1mは欲しいですね!。
」がオススメです。被覆資材は、アブラムシを防除するには目合いが0.8mm以下の、目の細かい防虫ネットが効果的ですが、目合いが細かくなるほど価格が高くなり、透光率が低下、ネットの上からの水やりに不便ですし、風通しが悪いため高温・防風面でのデメリットもあります。私が使っているのは、目合い1mmの銀糸入り防虫ネット。1mm目の防虫ネットが最も市場での流通量が多く値段がこなれ、防虫効果とコストパフォーマンスの両面でバランスが良く、家庭菜園で使うには使い勝手がいい様に思います(笑)。ちなみに、整枝の済んだソラマメの畝を覆うトンネルを作るためには、最低でもダンポールは長さ2.4m、防虫ネット(寒冷紗)の幅は2.1mは欲しいですね!。
![]() 【ご参考】マルチとトンネルを掛けよう!のページへ
【ご参考】マルチとトンネルを掛けよう!のページへ

 せっかくアブラムシの難を逃れ、大切に育て上げたソラマメ。一番美味しい状態の時に収穫して、新鮮なうちに頂きたいところですが、これがまた、意外と収穫時期の見極めが難しい…(汗)。
せっかくアブラムシの難を逃れ、大切に育て上げたソラマメ。一番美味しい状態の時に収穫して、新鮮なうちに頂きたいところですが、これがまた、意外と収穫時期の見極めが難しい…(汗)。
基本的な見極め方は、空豆のごとく、空を向いていた莢が、実が詰まって垂れ下がり、下を向いた時(笑)。しかし、莢が垂れ下がっても、まだ実の入り方には差があって、一筋縄ではいきません。後は、莢をつまんでみて、その実(豆)の大きさや硬さ・弾力から収穫適期を判断しますが、こればかりは経験から習うしかありません!。ぜひ旬のソラマメを食卓に並べ、美味しいビールと共に味わってみてください(笑)。

 なお、ソラマメの美味しさに味を占めて、来年も作りたいと思っている方は、全部の豆を収穫して、食べてしまってはいけませんよ!(笑)。ソラマメは、基本的に固定品種で継続的に生産が続けられてきているので、種(豆)の自家採種が可能です。なるべく株が元気なうちに、早めに収穫期を迎えたものから、莢も豆も大きく立派で、色つやがよい一級品を必要な数だけ選び、目印を付けて、収穫しない様に残しておきます。立派な莢から先に収穫したい衝動は誰にでもあるとは思いますが、ここは来年のために我慢のしどころ、来年も立派なソラマメを収穫するために、よい豆を来年の種に回しましょう!。
なお、ソラマメの美味しさに味を占めて、来年も作りたいと思っている方は、全部の豆を収穫して、食べてしまってはいけませんよ!(笑)。ソラマメは、基本的に固定品種で継続的に生産が続けられてきているので、種(豆)の自家採種が可能です。なるべく株が元気なうちに、早めに収穫期を迎えたものから、莢も豆も大きく立派で、色つやがよい一級品を必要な数だけ選び、目印を付けて、収穫しない様に残しておきます。立派な莢から先に収穫したい衝動は誰にでもあるとは思いますが、ここは来年のために我慢のしどころ、来年も立派なソラマメを収穫するために、よい豆を来年の種に回しましょう!。
葉が枯れ落ち、莢が黒く変色して乾燥したら、カビが繁殖する梅雨入り前に豆だけを収穫して、10月以降の種まきまで、ネット袋等に入れて風通しのよい日陰に吊るしておきます。
![]()