都会からリタイアして地元の田舎に戻り始めた家庭菜園、少しずつ学んだ野菜の育て方のコツをまとめてみました。
アスパラガス(アスパラ)は、分類学上は難しくてよく分からない複雑な種ですが、要は多年生の植物です。株によって雌雄が異なる「雌雄異株」ですが、どちらの株からもアスパラは収穫できます。葉のように見えるのは、実は細く分枝した茎で、本来の葉は退化してしまっているそうです。ますます、複雑怪奇な植物で、何やら育てるのが怖くなってきました・・・(汗)。でも、食べると美味しいので、家庭菜園には外せませんね(笑)。一度植えたら、大した手間もかからず、毎年収穫できるのですから、こんな有難い野菜はありません!。厄介なのは、収穫量の割に、広い場所を占拠してしまうこと。特に夏以降、その”茎”が伸びて繁りだすと、狭い農園では邪魔で仕方ありません(汗)。
 比較的、病害虫の心配は少ない野菜ですが、たまに立枯病(苗立枯病、茎枯病)が問題的に集中発生してしまうことがあります。土中のカビ細菌による病気で、発症すると消毒効果はあまり期待できないので、刈り取って焼却処分します。水はけが悪く、酸性度が増すと発生しやすくなるので、株間を取り、混み合った茎は間引いて風通しを確保します。また、肥料過多、特に窒素分が多いと発生しやすいので、施肥量に気を付けます。
比較的、病害虫の心配は少ない野菜ですが、たまに立枯病(苗立枯病、茎枯病)が問題的に集中発生してしまうことがあります。土中のカビ細菌による病気で、発症すると消毒効果はあまり期待できないので、刈り取って焼却処分します。水はけが悪く、酸性度が増すと発生しやすくなるので、株間を取り、混み合った茎は間引いて風通しを確保します。また、肥料過多、特に窒素分が多いと発生しやすいので、施肥量に気を付けます。 ちなみに、アスパラガスのコンパニオンプランツには、ニラが良いそうです。立枯病を予防し、ハダニなどの害虫除けにもなると、私は畝の回りをニラで囲ってしまいました(笑)。
ちなみに、アスパラガスのコンパニオンプランツには、ニラが良いそうです。立枯病を予防し、ハダニなどの害虫除けにもなると、私は畝の回りをニラで囲ってしまいました(笑)。
アスパラガスは、一度収穫が始まれば、10年以上も毎年収穫できる野菜ですが、種を蒔いてから収穫できるようになるまで、丸3年もかかります。つまり収穫は、種まきした、次の次の年、3年目以降。そんなに長く待てないという人は、株分けした苗を買ってきて春に植えつけると、翌年の春には収穫できるようになります。ただ、苗は高いし根付き難く失敗しがち…。時間は掛かりますが、タネから育てることをお勧めします。一袋のタネを全部育てたら、3年後には丸一か月間、毎日アスパラ尽くしになりますよ!(笑)。
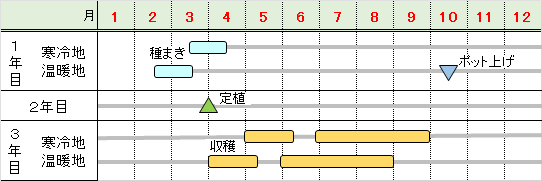
種まきしてから3年目の春、ようやく収穫が始まります。ただ、株が若いうちは、収穫できる期間は短く、徐々に長くなっていきます。しかし、年が経って株が弱ってくると、また収穫できる期間は短くなっていきます。あまり収穫できなくなってきたら、株の入れ替え時期です。
太くて若い芽を、ハサミを使って根元で切り取ります。ハサミが手元になかったりすると、つい指でつまんで折って収穫してしまいがちですが、土の上に残った茎は害虫に食害されるので、あまり残さない方がいいようです。細い茎まで全部収穫してしまうと、株が弱ってしまうので、食べ頃の、ある程度の太さ以上のものだけ収穫するようにします。
ただし、株がまだ若かったり、逆に衰えてくると、細い芽しか出て来ず、太いものだけ収穫していたのでは収量が上がりません。また、前年や暮れから年明けの追肥(お礼肥)が極端に足りなかった場合も、株が充実せず、翌年は細いアスパラガスしか採れない年があったりします(汗)。そんな時は、5月いっぱいは、食べられる太さなら、全部収穫してしまっても構いません。さすがに、焼き鳥の竹串みたいなのは残します。6月以降は、少し細いのも残して茎を伸ばし、株を充実させることで、来年の収量増加を願いましょう。お礼肥もお忘れなく(笑)。
どの位の長さになったら収穫したらよいか?、何時も迷いますが、1日置くとあっという間に大きくなり過ぎてしまうので、こればかりは経験を積むしかありません。毎朝、新鮮なうちに収穫し、収穫したアスパラは立てて保存します。アスパラは鮮度が落ちるのも早く、収穫してから1~2日で使い切りましょう。
収穫後期になると、だんだん根元が硬くなってきます。調理する際は、下の方から順番に、包丁の刃を軽く茎に当ててみると、すっと入る場所が見つかります。そこから上が、食べ頃の部分です(笑)。
収穫期間中は、ひと月ごとに、お礼肥を与えます。その後、冬の間に1回、追肥します。アスパラ専用の肥料も売られていますが、私は鶏糞を使っています。
夏ごろには、取り残した細い茎が伸びて、葉(=茎)がボウボウに茂ってきます。そうなると、雨に当って風が吹くと、すぐに茎が倒れてしまいます。そうなる前に、畝の周囲に杭を打ち、横棒を渡すか、紐を張って、倒伏を防ぐ必要があります。
 杭に、横棒や紐を張るのは、意外と手間。そこで私は、まだ茎が杭の高さまで育っていな頃に、「漁網」を杭の頭の釘に引っかけ、張ってしまいます。なぜ海なしの長野県に漁網があるかというと、むかし、リンゴ栽培での鳥除けに、安く手に入る漁網を使った名残です(笑)。どんなネットでも代用できると思いますが、漁網は丈夫で、晩秋に枯れた茎を刈り取る際に、ネットに絡んだ茎を乱暴に引き抜いても、滅多に千切れないのがイイです。漁網は、この他にも、イチゴ栽培での鳥除けや、トウモロコシ栽培でのタヌキやハクビシン対策にと、いろいろ役に立ちますよ!。
杭に、横棒や紐を張るのは、意外と手間。そこで私は、まだ茎が杭の高さまで育っていな頃に、「漁網」を杭の頭の釘に引っかけ、張ってしまいます。なぜ海なしの長野県に漁網があるかというと、むかし、リンゴ栽培での鳥除けに、安く手に入る漁網を使った名残です(笑)。どんなネットでも代用できると思いますが、漁網は丈夫で、晩秋に枯れた茎を刈り取る際に、ネットに絡んだ茎を乱暴に引き抜いても、滅多に千切れないのがイイです。漁網は、この他にも、イチゴ栽培での鳥除けや、トウモロコシ栽培でのタヌキやハクビシン対策にと、いろいろ役に立ちますよ!。
 ただし、漁網はナイロン製なので、撤収するときに厄介なことも否めません(汗)。その場合は、麻ひも
ただし、漁網はナイロン製なので、撤収するときに厄介なことも否めません(汗)。その場合は、麻ひも(ジュート紐、バインダー紐
)を張り巡らせます。毎年こうして、紐を張っては撤去することを繰り返していると、最初から丈夫な横棒を渡してしまった方が早いんじゃないかという気がしてきます…(汗)。曲がった支柱とか、使わなくなった物干し竿、廃材として出た角材や鉄筋棒など、もしタダで手に入る様なら、先に棚を作ってしまう方が賢い選択かもしれません!。
 霜が降り始めるころ、茎は黄変し、枯れてきます。
霜が降り始めるころ、茎は黄変し、枯れてきます。
茎が9割方枯れたら、根元から刈り取り、出来るだけ残渣を残さないようにして、圃場外へ処分します。枯れた茎には、立枯病(茎枯病)などの細菌が付いているので、焼却処分してしまうのがおすすめ。
さらに、病気予防のために、畝面をバーナーで焼却処理すると安心です。年が明けた頃になると、刈り取った茎の下の部分、土に残った茎の根元が、簡単に抜き取れる状態になります。そうしたら、その茎の根元を抜き取った後、茎を刈り取る際に折れたりして畝に残ってしまった茎の残渣もろとも、バーナーで焼いてしまいます。
![]()