クラシック音楽は私には難解すぎます。そこで超簡単に、超短時間でクラシックを学ぶことを目指します!
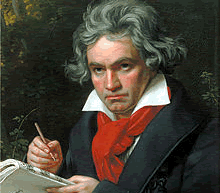
※「超いい加減なジャズ入門」のページも、併せてご覧ください。
クラシック音楽は、私には、難しくてよく分かりません…(汗)。その背景には、いろいろと難しい音楽理論や、曖昧な定義、明確には区分できない感性といった、素人が簡単には踏み込み難い高い壁が、そびえ立っているからだと推察します。
そんなド素人の私が、理論も概念もかなぐり捨てて、もっともらしい一般論だけを集めて、クラシック音楽のウンチクを語ってみることにしました。目指すのは、サルでも分かるような、超簡単で、超短時間に、クラシック音楽の全体像と概略を知ることが出来る、お話しです!。
はじめは、私自身が、そのような書籍がないかと探してみたのですが、どうしても見つかりません。当たり前です、書物として、間違ったことは読者に伝えられませんから。複雑なクラシック音楽の世界を語ろうとすると、どうしても分厚く、難しい内容にならざるを得ないのは、至極当然のことです。しかし、それを私はたった1ページで語ろうというのですから…。
したがって、ここに記されている内容は、『あまり正確ではない』か、もっと言うと、『正確には、間違っているかも』しれません(汗)。でも、とりあえずこれを読んだら、今日から初心者の私もあなたも、にわかに「なーんちゃって・クラシック音楽ツウ(通)」になれるかも!?
このページを作成するにあたり、茂木大輔氏の『拍手のルール 秘伝クラシック鑑賞術』(中公文庫)を参考にさせて頂きました。ご迷惑かもしれませんが、何卒ご容赦を m(__)m。
クラシック音楽は、1700年から1940年ごろに、中央ヨーロッパ(イタリア、フランス、ドイツ、オーストリア、チェコ、ロシア)辺りで作られた音楽です。
なお、「です」と言いきっていますが、もちろん多様な研究や学説があって、ド素人が俄かに聞きかじりして断言できるほど、甘い世界では無いことは重々承知です。日本だって、多数の著名なクラシック作曲家を輩出しています。ただ、あーだこーだ書いていると、このページの本来の目的が達せられなくなってしまうので、甚だ多くの誤解や齟齬があっても、ここでは“一説限定”で記させてもらいます(笑)。
1700年の日本はというと、まだ江戸時代で、「生類憐みの令」で有名な第5代将軍 徳川綱吉が治めていた頃です。一方1940年は、日独伊三国軍事同盟が締結された年で、ヨーロッパではナチス・ドイツが中央ヨーロッパへと侵攻し、日本は翌1941年に太平洋戦争に突入しました。
クラシック音楽(classic music)は、「クラシック」と付いていることから “古い”音楽、“古典的な”音楽と誤解されがちですが、「classic」には、“一流の,最高水準の”とか、“典雅な,高尚な”という意味もあります。ウィキペディアには、クラシック音楽とは「西洋の芸術音楽」と記されています。
クラシック音楽には、様々なタイプの音楽があり、使われる楽器や演奏形式も多種多様、さらには声楽曲(歌)まで含まれ、明確に分類するのは大変です。ウィキペディアでは、①演奏形式による分類(器楽、管弦楽、吹奏楽、室内楽、声楽曲、舞台音楽、電子音楽)と、②セールス・鑑賞上の分類(交響曲、協奏曲、管弦楽曲、室内楽曲、器楽曲、声楽曲、オペラ、音楽史、現代曲)の、2パターンが掲載されていますが、いずれも複雑すぎて覚えきれません…。
そこで、ここではエイヤー!と、「管弦楽」「室内楽」「ピアノ曲」「声楽曲」の、たった4つに分類してしまいましょう(笑)。本当は、これに「その他」を付けなければいけないのでしょうが、それは無視…。




クラシック音楽を分類したイメージ図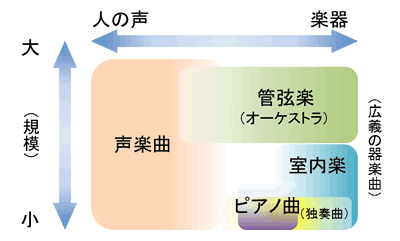
クラシック音楽の曲名は、「交響曲第5番ハ短調作品67」とか言われると、暗号みたいで覚えられないので、復習する意欲や機会が減って、ますますクラシックから遠ざかってしまいます。それでも、ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調作品67の副題は「運命」だと分かれば、『私も知っている!』と言えます。全部の楽曲に、「革命」(ショパン)とか、「新世界より」(ドヴォルザーク)なんて、印象深い“副題”があればいいのにと(笑)。また、“ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調作品125”のように、略称して「第九」で通じてしまうものも救われますが…。
こうした「副題」には、作曲家が自ら表現上の意図をもってつけた「題名」(タイトル)や「標題」(プログラム)のほかに、後世において第三者が勝手につけた「通称」(愛称、ニックネーム)が定着したものがあります。さらに、先の「第九」のような略称や、「未完成」(シューベルト:交響曲第7番ロ短調D759)のような作品の状態を呼んだものなど、様々です。
さて、副題ですべての楽曲を知ることが出来ない以上、本来の曲名を理解せざるを得ません。
クラシック音楽の曲名は、「曲のジャンル」+「番号」+「調性」+「作品番号」(もしくは学術的整理番号)+(あれば)「副題」、から構成されています。
例えば、「
① まず、正確に曲を識別するには、交響曲と言っても大勢の作曲家が作曲しているので、先頭に「作曲者の名前」を付けないと、定かに区別できません。
② 次の「曲のジャンル」は、前述のとおり。
③ 「番号」は、ベートーヴェンが作曲した交響曲のラインナップを示す番号です。例外もありますが、まぁ作曲された順番のようなものかと。
④ 「調性」は、どの調(音階)の曲かを識別します。調によって、作品の雰囲気はがらりと変わるため、作曲家にとって曲調を示すことは、とても重要なのでしょう。
⑤ 「作品番号」は、楽譜の出版に際して付された番号で、いわゆる出版社のカタログ番号に該当します。外国語表記を使って「op.125」と示す場合や、楽曲がセットで出版される場合には、「作品56の6」のように、枝番が付される場合もあります。
⑥ 作品番号が無いか、欠落している作曲家には、作品番号の代わりに、学術研究により付された「整理番号」が与えられている場合があります。モーツァルトのケッヘル番号(K.16など)や、バッハのBWV(バッハ作品主題目録番号)などが有名。
⑦ そして最後に、先述の「副題」があれば付されて、曲名が完成です。
茂木大輔氏の『拍手のルール 秘伝クラシック鑑賞術』によると、クラシック音楽が作られた年代は「1700年から1940年ごろまで」、作曲家の名前でいうと、「バッハからシェーンベルクまで」と記されています。しかし実は、「四季」などを作曲したヴィヴァルディ(伊)の方が、バッハ(独)より7歳も年上ですが、“ヨハン・ゼバスティアン・バッハ”は西洋音楽の基礎を構築した作曲家として「音楽の父」とも称される人物であることから、『クラシック音楽はバッハから始まった』という位置づけなのでしょう!。
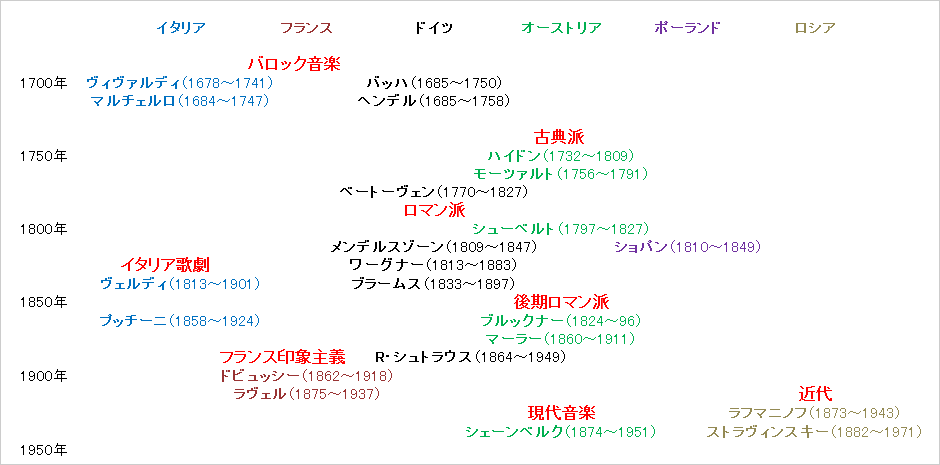






有名作曲家は、上述の「クラシック音楽の歴史」の中で挙げただけでも、数えてみると、26人も居ます。それぞれに、有名な楽曲が10くらいは有りそうなので、それぞれ例えひとつの名演奏と評判のCDだけをチョイスしても、数百枚のCDを列挙しなければなりません。
であれば、私なんぞがおススメしなくても、巷には「クラシック・ベスト100」と冠されたシリーズ物が、あまた存在していますので、そちらをご購入ください。
そこで、ここでは、せっかく先にクラシック音楽のジャンル分けと、時代の流れに沿ったクラシック音楽の変遷を紹介したのですから、それぞれのジャンルごとに、各時代の違いを感じられる代表的な楽曲を対比させながら、おススメのベストCDを紹介してみたいと思います。(ただし、ド素人の私でも既にCDを持っているような、あまりに有名なメジャータイトルは敢えて除きます。)
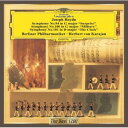









最後に、クラシック音楽(交響曲)を聞くのに欠かせない、オーケストラ(管弦楽団)のウンチクを、少しだけ学んでおきましょう。
オーケストラ(管弦楽団)とは、その名のとおり、複数の弦楽器、管楽器および打楽器の編成により、管弦楽曲を演奏するために組織された団体のことです。
オーケストラの編成や規模は、決まった形式があるわけではありません。第1ヴァイオリンからコントラバスまでの弦五部は、各部の人数が演奏者に任されていたり、管楽器は原則として楽譜に書かれた各パートを1人ずつが受け持つのですが、実際の演奏会では管楽器を2倍にしたり(倍管)、アシスタントの奏者がつくこともあります。また、楽器の配置にも、決まった形式はありません。いずれも、時代や指揮者によって、工夫が重ねられてきました。(by ウィキペディア)
ただし、その指揮者は、通常はオーケストラの一員ではありません。オーケストラは、あくまで楽器奏者の団体であり、指揮者は演奏会ごとに任じられるのが常です。ただし、多くのオーケストラは、一定の期間に渡って「常任指揮者」(あるいは首席指揮者、音楽監督)と契約を交わして、指揮者とともにオーケストラの個性を際立たせる努力をしています。
例えば、以下のような指揮者とオーケストラが組んだ楽曲が著名です。
![]()