都会からリタイアして地元の田舎に戻り始めた家庭菜園、少しずつ学んだ野菜の育て方のコツをまとめてみました。

キャベツ(甘藍)は、アブラナ科アブラナ属の多年草で、日本人がもっとも食べている野菜のひとつでしょう。トンカツの付け合わせには欠かせませんね(笑)。その起源は古代にまで遡りますが、今の様なキャベツになったのは12~13世紀のイタリアと言われ、その後アメリカに渡り品種改良されてきました。日本には幕末に伝わりましたが、品種改良され日本で広く生産されるようになったのは、明治から大正にかけてのことで、野菜としては比較的新しい部類です。
現在、日本で一年間に出荷されるキャベツの生産量は、全国で約150万トンもあります。人口一人あたりだと年間15kg、1球が1キロとすれば、一人で1年間に15球も食べている計算です!(驚)。一度、嬬恋高原のキャベツ畑を訪れてみてください。そのキャベツ畑が広がる絶景には、驚かされますよ!(笑)。これだけ人気の野菜なので、できれば家庭菜園でも、春先から晩秋まで、年間を通じて切れ間なく収穫できるようにしたいものです。しかし、春の長雨や夏場の猛暑で苗が育たなかったり、逆に天候が良すぎて後から蒔いた種の生育が早く、収穫する前に畑で裂果してしまうことも・・・(汗)。毎年、いろいろ試行錯誤しているのですが、長く食べ続けるには、とにかく小まめに時間差で種まきを続けるしか方法がありません。それでもキャベツの収穫が途切れて、スーパーで買わざるを得なくなった時の、口惜しさと言ったら・・・(泣)。


キャベツは、春から秋まで時間差で種まきを続けると、長い期間収穫できる、スグレモノの野菜です。アオムシやアブラムシに負けずに、ぜひ年間を通じた収穫を目指してください!(笑)。
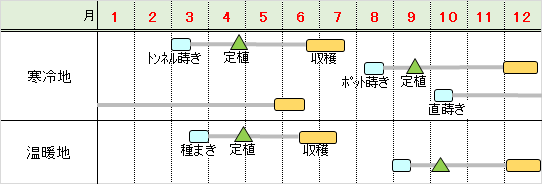
 本葉が5~6枚になった頃が、定植の適期。事前に石灰と堆肥を施した畝に、条間 60~70cm×株間 30~40cmで植え付けます。品種によって、大きく葉を広げる品種は広めに、葉の広がりがコンパクトな品種は狭めにします。アブラムシやアオムシ対策には、定植時の植穴に、オルトランやダントツなどを撒いておくと良いでしょう。
本葉が5~6枚になった頃が、定植の適期。事前に石灰と堆肥を施した畝に、条間 60~70cm×株間 30~40cmで植え付けます。品種によって、大きく葉を広げる品種は広めに、葉の広がりがコンパクトな品種は狭めにします。アブラムシやアオムシ対策には、定植時の植穴に、オルトランやダントツなどを撒いておくと良いでしょう。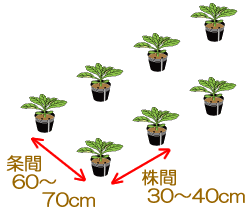
 定植したら直ぐに、防虫ネットなどでトンネル掛けし、蝶や蛾に卵を産み付けられないようにしましょう。しかし、ネットを掛けてあるからと安心してはいけません!。どんな隙間からでも蝶は入り込み、草取りの合間にも人目を盗んで蝶は卵を産み付けてしまいます(汗)。常に注意を払い、もし葉に穴が開いていたり、糞の塊を見つけたら、葉の裏側までよく観察して、アオムシ類は見つけ次第に捕殺します!。
定植したら直ぐに、防虫ネットなどでトンネル掛けし、蝶や蛾に卵を産み付けられないようにしましょう。しかし、ネットを掛けてあるからと安心してはいけません!。どんな隙間からでも蝶は入り込み、草取りの合間にも人目を盗んで蝶は卵を産み付けてしまいます(汗)。常に注意を払い、もし葉に穴が開いていたり、糞の塊を見つけたら、葉の裏側までよく観察して、アオムシ類は見つけ次第に捕殺します!。
アオムシやコナガの幼虫などが多すぎて、テデトール(手で獲る)が間に合わなくなってしまったり、アブラムシが押し寄せた場合には、農薬に頼りましょう。速攻性の高い「プレオ フロアブル
![]() 」や、収穫前日まで使える「フェニックス顆粒水和剤
」や、収穫前日まで使える「フェニックス顆粒水和剤![]() 」が、おすすめです。
」が、おすすめです。
定植後、2~3週間ごとに、草取りと中耕・土寄せを兼ねて、追肥をします。肥料好きの野菜なので、追肥はたっぷり目に!(笑)。
球の頭を手のひらで押さえてみて、大きく締まりのよいものから収穫します。収穫が遅れると、球に亀裂が入り、葉が割れてしまいます。ギリギリ裂果を逃れても、収穫後に台所で水に浸けたら、パンッと割れてしまうことも!(汗)。もちろん、裂果しても味に変わりはなく、ちゃんと食べられるのですが、葉を剥くのが難しく、傷みやすくなってしまいます。できれば、裂果する前に収穫を済ませ、食べきれなければ知人や近所におすそ分けしてしまいましょう!(笑)。
収穫後のキャベツを長く保存するには、芯の部分をくり抜き、そこに水で濡らしたキッチンペーパーなどを詰めてから全体をラップに包んで、冷蔵庫の野菜室で保存すると、比較的長持ちします。
とにかくキャベツやブロッコリー等は、切った芯の部分が、一番腐りやすいです。収穫する際も、地際から包丁で切ったまま根を残しておくと、残った根の芯の部分から腐って、悪臭を放つことがあります。そのままにしておくと、病害虫の発生原因ともなりかねません。収穫の際は、根ごと掘り起こしてから球を切り離すか、根を残したら早めに耕すようにしましょう。ただし、適期栽培では、切り残した株から脇芽が出て、小さいながらもまたキャベツが収穫できる場合もありますので、見極めが肝心です!。
![]()