自分や家族が食べる野菜なので無農薬で育てたい!でも無理しすぎず、時には減農薬でと割り切って始めてみるのがおすすめです。
家庭菜園の一番いいところは、自分や家族が食べる野菜を、自分で育てること。プランターでもいいから一度、自分で野菜を育ててみると、どれだけ野菜が病害虫に弱いか、分かりますよね!。
自分が畑で育てた葉物野菜は、台所に持ち込む前に、家の外の水道で水洗いするのが基本。それでもレタスなどは、翌日に一葉めくると、黒っぽい「あれ」が隠れていたりします(驚)。キャベツや小松菜、ブロッコリーなどアブラナ科の野菜は、葉を一枚ずつめくりながら、よく浸け洗いしないと、茹でているうちにプッカリと、「緑色の物体」が浮き上がることも…(汗)。しかし、それも慣れればご愛嬌!。自分で、どれだけの化成肥料を与え、どれだけの農薬を使ったのか、分かる範囲での収穫物です。しかし、スーパーで買ってきた野菜は、洗わずともラップを剥いで、そのまま包丁で切ったところで、虫なんぞ絶対にいないどころか、葉には虫に食われた跡さえも付いていません!。
一方、せっかく家庭菜園を始めるのだから、『無農薬で育てたい!』という気持ちも分かります。しかし、やっぱり無農薬の家庭菜園はハードルが高いです。何年か頑張って、いろいろ勉強し、毎日・朝晩とも畑に出て手入れが続けられるようになったら、チャレンジしてみてください。初心者のうちは、あまり無理をせず、時には減農薬でと割り切って、安全と思われる範囲で、農薬を使ってみることをおすすめします!。無理をして、家庭菜園そのものを諦めることになってしまったら、せっかくの健康的な趣味を、ひとつ無くすことになってしまうので、とても残念です。
ただ、全部の病害虫に効く便利な農薬は、残念ながらありません…(汗)。多くの種類の野菜を育てる家庭菜園では、駆除できる害虫や、適応する野菜ごとに、最低でも何種類かの農薬を揃える必要があります。また、農薬にはいろいろなタイプがあります。そのまま畑に撒ける粒状のものや、水で薄めてジョロや噴霧器で撒布する粉体や液体・乳剤など、様々です。噴霧器は、小型のプラスチック製のものは安価ですが、数年で劣化してダメになることが多いです。一方、ステンレス製の噴霧器は値段は高いですが、丈夫で長持ちします。家庭菜園では、それぞれの利点を生かして、2~3個の噴霧器を使い分けるのが、便利でおすすめですよ!。
※ なお、ここで紹介している農薬は、あくまで私が使ったことがある、ほんの一部の、極限られた商品でしかない点に、何卒ご留意ください。ちなみに、『日本ではどのくらいの種類の農薬があるのか?』と調べてみたところ、「農薬工業会」によると、農薬の登録数は 4,282件(平成30年9月末現在)だそうです。ただし、この中には除草剤や植物成長調整剤なども含まれていますので、殺虫剤だけだと 約1,000件ほど、殺菌剤は 約900件、殺虫殺菌剤 約500件です。それでも、ハンパない商品数です…(汗)。殺虫剤・殺ダニ剤の有効成分の分類表だけ見ても、よく聞く有機リン系とかネオニコチノイド系とか、数えると 112種類もあります!(2021年5月現在)。
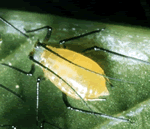 アブラムシは、1匹の個体はとっても小さくて、数匹集ったくらいでは何の影響も無いのですが、何も対処せずにいると、あれよあれよという間に、花芽や新芽の周り一帯から、果てには株全体にビッシリと広がり、それはそれは見るもおぞましい姿に・・・(汗)。
アブラムシは、1匹の個体はとっても小さくて、数匹集ったくらいでは何の影響も無いのですが、何も対処せずにいると、あれよあれよという間に、花芽や新芽の周り一帯から、果てには株全体にビッシリと広がり、それはそれは見るもおぞましい姿に・・・(汗)。
アブラムシが集団で野菜に取り付くと、大量の汁液を吸い取ってしまい、野菜の生育が急速に滞ります。特に、オクラやマメ類の苗にはアブラムシが付きやすく、幼苗のうちにビッチリ付かれると、成長が遅れるどころか、処置が遅れると、苗が枯れてしまうこともあります!。また、アブラムシが大量に発生すると、見た目的に気持ち悪いだけでなく、さらに悪いことに、アブラムシは「ウイルス病」までをも媒介します。ウイルスに感染した野菜の汁液を吸ったアブラムシが、また次に別な野菜に集って汁液を吸うことで、次々に畑中の野菜にウィルス病を拡散してしまうからです。
 アブラムシを駆除するには、無農薬で対処するなら、少ない内に、①「テデトール」(手で取る)か、②散水して水で流す、③ガムテープなど粘着テープで剥ぎ取る方法などがあります。また、④木酢や、⑤唐辛子液、⑥牛乳などを散布する方法も、よく使われています。一番手っ取り早いのは、どこのお宅の冷蔵庫にもあるであろう「牛乳」。低脂肪乳ではなく、普通の牛乳を、そのままか、臭いが気になるようなら2倍に薄めて、スプレー容器で、アブラムシめがけて噴霧します。アブラムシの体に付いた牛乳が、乾く時に収縮してアブラムシを窒息死させる仕組みを利用しています。なので、天気の良い、よく晴れた日中に行うのが効果的ですが、牛乳で駆除できるアブラムシの量には限界があります…。
アブラムシを駆除するには、無農薬で対処するなら、少ない内に、①「テデトール」(手で取る)か、②散水して水で流す、③ガムテープなど粘着テープで剥ぎ取る方法などがあります。また、④木酢や、⑤唐辛子液、⑥牛乳などを散布する方法も、よく使われています。一番手っ取り早いのは、どこのお宅の冷蔵庫にもあるであろう「牛乳」。低脂肪乳ではなく、普通の牛乳を、そのままか、臭いが気になるようなら2倍に薄めて、スプレー容器で、アブラムシめがけて噴霧します。アブラムシの体に付いた牛乳が、乾く時に収縮してアブラムシを窒息死させる仕組みを利用しています。なので、天気の良い、よく晴れた日中に行うのが効果的ですが、牛乳で駆除できるアブラムシの量には限界があります…。
そこで、農薬(殺虫剤)の登場となります。
 |
価格:1,500円 |
私のおすすめは、アブラムシには断然、「ダントツ![]() 」。水で2000倍~4000倍に希釈して使う液剤のほか、粒剤や粉剤もありますが、家庭菜園でアブラムシ駆除に使うなら、薄めて噴霧器で噴霧する「液剤」タイプが使いやすいでしょう!。液剤タイプの「ダントツ水溶剤」には、125g入り
」。水で2000倍~4000倍に希釈して使う液剤のほか、粒剤や粉剤もありますが、家庭菜園でアブラムシ駆除に使うなら、薄めて噴霧器で噴霧する「液剤」タイプが使いやすいでしょう!。液剤タイプの「ダントツ水溶剤」には、125g入りと、250g入り
があります。
農薬の薄め方は、こちらをご参考に!![]() 【農薬】混ぜ方・作り方「希釈倍率早見表」
【農薬】混ぜ方・作り方「希釈倍率早見表」
事前にアブラムシ予防をするなら、定植時の植穴処理や、生育期に株元に撒くことで防除効果を発揮する、「ダントツ粒剤![]() 」もオススメです。ただしダントツ、それほど安い農薬ではないので、アブラムシが付くか付かないか分からないのに、むやみに撒くと結構コストがかかりますので、ご注意を(汗)。アブラムシのほか、ハダニなどにも効果が期待できる「マラソン
」もオススメです。ただしダントツ、それほど安い農薬ではないので、アブラムシが付くか付かないか分からないのに、むやみに撒くと結構コストがかかりますので、ご注意を(汗)。アブラムシのほか、ハダニなどにも効果が期待できる「マラソン![]() 」も、安価で使い回しに便利ですが、私の経験では、アブラムシ駆除の効果は、ダントツの方が期待できる感じがします。
」も、安価で使い回しに便利ですが、私の経験では、アブラムシ駆除の効果は、ダントツの方が期待できる感じがします。
ちなみに、アブラムシは、何処からやって来るのでしょうか?。一概にアブラムシと言っても、何と日本には、名前が付けられたアブラムシだけで、700種類もいるそうです(驚)。体色も、緑のもいれば、黒、赤、黄色と様々です。その生態は変わっていて、雌(めす)だけで繁殖し、卵からから孵ってから10日ほどで親になり、毎日5~10個も卵を産むそうです。その増え方は、ネズミ算式どころの話ではありません…(汗)。卵の状態で越冬したものが、春になって孵化して、5月ごろに爆発的に増殖します。アブラムシには脚が生えていますが、植物に掴まるための脚で、移動することはほとんど出来ません。そのため、増えたアブラムシの移動を助けているのが、共生関係にあるアリ(蟻)。アブラムシは甘い体液を出してアリを集め、天敵であるナナホシテントウムシなどをアリに追い払って貰います。そして、集団(コロニー)が大きく成りすぎたら、アリにくっ付いて、移動します。さらにコロニーが巨大化すると、アブラムシは生き残りをかけて新天地を求め移動を余儀なくされるため、なんと羽の生えた子供を産むようになります!(驚)。自由に飛び回れるような羽ではありませんが、風に乗って移動するには十分です。そして、目的の野菜めがけて、空から舞い降ります。東南アジアに生息する羽(翅)のあるアブラムシは、なんと気流に乗って、東南アジアから日本にもやってくるそうです。ただし、日本では越冬は出来ないらしいので、ご安心あれ(笑)。
 また、アブラムシは、キラキラ光る物を避ける習性があるそうです。そこで、「シルバーマルチ
また、アブラムシは、キラキラ光る物を避ける習性があるそうです。そこで、「シルバーマルチ![]() 」をしたり、銀糸入りの寒冷紗やネット(「防虫メッシュキラリ
」をしたり、銀糸入りの寒冷紗やネット(「防虫メッシュキラリ![]() 」など)を掛けることも、アブラムシ防除には有効とされています。ただ、こうした資材は高価だし、面倒。そこで私が実践しているアブラムシ対策は、株の上方に、「キラキラテープ
」など)を掛けることも、アブラムシ防除には有効とされています。ただ、こうした資材は高価だし、面倒。そこで私が実践しているアブラムシ対策は、株の上方に、「キラキラテープ![]() 」(赤銀テープ)を張ることです!。エンドウは、支柱の先端に一本のテープを張るだけですが、ソラマメ(空豆)なんかは、倒伏防止も兼ねて、株の周りをキラキラテープでぐるぐる巻きにしています(笑)。効果のほどは定かでありませんが、少なくとも今まで大きな被害は受けたことが無いので、多少は効果があるような気が・・・(汗)。
」(赤銀テープ)を張ることです!。エンドウは、支柱の先端に一本のテープを張るだけですが、ソラマメ(空豆)なんかは、倒伏防止も兼ねて、株の周りをキラキラテープでぐるぐる巻きにしています(笑)。効果のほどは定かでありませんが、少なくとも今まで大きな被害は受けたことが無いので、多少は効果があるような気が・・・(汗)。
 その他、農薬を使わない駆除方法として、アブラムシの天敵の力を借りるという方法もあります。代表的な天敵が、「てんとう虫」。1匹のてんとう虫は、毎日10匹以上のアブラムシを食べてくれるそうです。ただし、益虫となるのは、「ナナホシテントウ」などの肉食のてんとう虫です。野菜の葉を食害する草食の「テントウムシダマシ」などに”騙されない”ように!(笑)。花壇などでナナホシテントウを見つけたら、手で捕まえて、菜園で離してあげましょう。とはいえ、てんとう虫にも羽があるので、そのうちに何処かに飛んで行ってしまうのですが・・・。そこで頭のいい日本人、なんと、飛ばないてんとう虫を人工的に作り出し、農業用商品として販売したというニュースが!。
その他、農薬を使わない駆除方法として、アブラムシの天敵の力を借りるという方法もあります。代表的な天敵が、「てんとう虫」。1匹のてんとう虫は、毎日10匹以上のアブラムシを食べてくれるそうです。ただし、益虫となるのは、「ナナホシテントウ」などの肉食のてんとう虫です。野菜の葉を食害する草食の「テントウムシダマシ」などに”騙されない”ように!(笑)。花壇などでナナホシテントウを見つけたら、手で捕まえて、菜園で離してあげましょう。とはいえ、てんとう虫にも羽があるので、そのうちに何処かに飛んで行ってしまうのですが・・・。そこで頭のいい日本人、なんと、飛ばないてんとう虫を人工的に作り出し、農業用商品として販売したというニュースが!。
そもそも、肥料過多(特に窒素分のやりすぎ)や、株が混み合い風通しが悪くなると、アブラムシが発生しやすくなります。肥料は控えめにし、欲張って狭い所で沢山野菜を作りすぎないようにしましょう!(笑)。
 キャベツなどアブラナ科の野菜を育てていて、一番悩まされるのが「アオムシ(青虫)」。言わずもがな、チョウチョウや蛾の幼虫ですが、一番多いのは、何と言ってもモンシロチョウの幼虫。春先から秋遅くまで、野菜栽培のシーズン中は毎日のように畑にやってくる、白くてかわいい「モンシロチョウ」。ひらひら舞いながら、数秒ほど野菜に止まったと思ったら、もう卵を産み付けて飛び立ってしまいます(汗)。モンシロチョウ(成虫)の寿命は2週間くらいで、その間に100個前後の卵を産むそうです。
キャベツなどアブラナ科の野菜を育てていて、一番悩まされるのが「アオムシ(青虫)」。言わずもがな、チョウチョウや蛾の幼虫ですが、一番多いのは、何と言ってもモンシロチョウの幼虫。春先から秋遅くまで、野菜栽培のシーズン中は毎日のように畑にやってくる、白くてかわいい「モンシロチョウ」。ひらひら舞いながら、数秒ほど野菜に止まったと思ったら、もう卵を産み付けて飛び立ってしまいます(汗)。モンシロチョウ(成虫)の寿命は2週間くらいで、その間に100個前後の卵を産むそうです。
 蝶たちが卵を産み付ける野菜は、ちゃんと習性で決まっていて、ほとんどがアブラナ科の野菜です。特に被害を受けやすい野菜は、キャベツ、白菜、ブロッコリー、小松菜、など。いくら種まきの段階から防虫ネット(寒冷紗)を掛けておいても、いつの間にかアオムシが付いて、葉を食害されてしまいます。どこから入るのか、ネットの中にモンシロチョウがいることも(汗)。ネットを剥いで草取りをしている間にも、そこに人がいるにも係わらず、ひらひらと背後から近付くモンシロチョウ・・・。
蝶たちが卵を産み付ける野菜は、ちゃんと習性で決まっていて、ほとんどがアブラナ科の野菜です。特に被害を受けやすい野菜は、キャベツ、白菜、ブロッコリー、小松菜、など。いくら種まきの段階から防虫ネット(寒冷紗)を掛けておいても、いつの間にかアオムシが付いて、葉を食害されてしまいます。どこから入るのか、ネットの中にモンシロチョウがいることも(汗)。ネットを剥いで草取りをしている間にも、そこに人がいるにも係わらず、ひらひらと背後から近付くモンシロチョウ・・・。
アオムシ駆除の基本は、何と言っても「テデトール」。もちろん薬剤の名前ではありません。手で取って処分することを意味する、かわいいガーデニング用語です(笑)。一般的には「捕殺」すると言いますが、物騒な動詞が付いているし、手で虫を触ることを想像しただけで気分が悪くなる人もいるので、その行為をオブラートに包んで、最近は「テデトール」という表現が人気です(笑)。
春や秋、特にアオムシが発生しやすい時期に、キャベツや白菜を育てる際は、防虫ネットを掛けるのに越したことはありません。でも、どうしても面倒だし、『まだ大丈夫だろう』なんて思っていると、思わぬ被害を受けることがあります。キャベツや白菜の葉を見て、穴が開いていたら、必ずアオムシがいます。昨日取ったはずと思っても、真新しい黒い粒々の糞の山があったら、見落としたアオムシが、まだ何処かに隠れています。最初の頃、一株で1匹2匹を見つけて潰しているうちはいいのですが、見落としたアオムシがだんだん成長し、一晩のうちに大量の葉を食害されてしまうと、苗の生育そのものも危うくなってしまいます(汗)。また、収穫間近のブロッコリーでは、アオムシは葉ではなく花蕾に入り込みます。そのため外からは見えず、収穫したブロッコリーを水を張ったボールに浸けておくと、何匹ものアオムシが水面に浮き上がってくるという、何ともおぞましい状態を目にすることに・・・。
アオムシ駆除が、「テデトール」では”手に負えなく”なってしまったら、農薬に頼りましょう。
 |
オルトラン水和剤 1g×10袋入 住友化学園芸 広範囲の害虫に効果が持続 殺虫剤 M6 価格:778円 |
私のおすすめの、アオムシ駆除の農薬(殺虫剤)は、初期段階での「オルトラン」。最も広く一般的に使われているのは、「オルトラン粒剤![]() 」です。安価で粒状なので扱いやすく、播種時や定植時の植穴処理、育苗期に株元に撒くことで、防除効果を発揮します。実は農薬にも、医薬品と同じくジェネリック(後発)品があり、「スミフェート粒剤
」です。安価で粒状なので扱いやすく、播種時や定植時の植穴処理、育苗期に株元に撒くことで、防除効果を発揮します。実は農薬にも、医薬品と同じくジェネリック(後発)品があり、「スミフェート粒剤![]() 」も成分的にはオルトラン粒剤と全く同じ、アセフェート(有機リン系)を同量含有する農薬で、少し割安に買うことが出来ます。一方、苗が成長した段階でアオムシの駆除に手が回らなくなってしまったら、オルトランの殺虫液を噴霧した方が、手っ取り早いです。その場合は、「オルトラン水和剤
」も成分的にはオルトラン粒剤と全く同じ、アセフェート(有機リン系)を同量含有する農薬で、少し割安に買うことが出来ます。一方、苗が成長した段階でアオムシの駆除に手が回らなくなってしまったら、オルトランの殺虫液を噴霧した方が、手っ取り早いです。その場合は、「オルトラン水和剤![]() 」を1000倍~2000倍の水に溶かして、噴霧器で撒きます。農家向けに売られている大袋入りの粉剤を買うのが一番安く済むのですが、水和剤は粒子が細かく素人には扱い難いので、割高ですが小分けした商品を使った方が便利です。1g×10包 と 5g×8包 入りの商品があります。1gの水和剤を1000~2000倍に薄めると1~2リットルになり、5gだと5~10リットルになります。畑の広さや一度に使う量にもよりますが、小さい噴霧器を使っているなら1g包入りを、大きな噴霧器を使っているなら5g包入りを買うとよいでしょう。
」を1000倍~2000倍の水に溶かして、噴霧器で撒きます。農家向けに売られている大袋入りの粉剤を買うのが一番安く済むのですが、水和剤は粒子が細かく素人には扱い難いので、割高ですが小分けした商品を使った方が便利です。1g×10包 と 5g×8包 入りの商品があります。1gの水和剤を1000~2000倍に薄めると1~2リットルになり、5gだと5~10リットルになります。畑の広さや一度に使う量にもよりますが、小さい噴霧器を使っているなら1g包入りを、大きな噴霧器を使っているなら5g包入りを買うとよいでしょう。
オルトランが便利で使いやすいのは、「浸透移行性剤」であるからです。普通の薬剤は、植物に吸収されても植物体内を移動することはありませんが、浸透移行性剤は、植物の根や葉から吸収されて植物体内を移動し、長期間に渡って、葉や実を食害したり吸汁する害虫を退治してくれます。しかし、デメリットもあって、浸透移行性剤であるがために、収穫間近の野菜には使えないこと。
 |
価格:972円 |
もし、キャベツや白菜などアブラナ科の野菜がだいぶ大きく生育した段階で、アオムシの被害が出てしまったら、速攻性の高い「プレオ フロアブル![]() 」や、収穫前日まで使える「フェニックス顆粒水和剤
」や、収穫前日まで使える「フェニックス顆粒水和剤![]() 」が、幅広いチョウ目害虫に高い効果が期待できて、おすすめです。ただ、そのぶん値段がちと高いのが難点ですが・・・(汗)。プレオ フロアブルは乳白色の粘性のある液体で、使用方法は水で1000倍に薄めて散布します。有機リン系など既存の殺虫剤とは異なる新しいタイプの殺虫剤で、既存剤に対して抵抗性を発達させた害虫にも高い殺虫活性を示します。経口及び経皮投与のいずれでも殺虫効果があり、降雨にも流されにくく残効性に優れています。フェニックス顆粒水和剤は、顆粒状の粒剤を2000~4000倍に薄めて散布します。こちらも、害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤とは異なる新しいタイプの薬剤で、収穫前日まで使えることと、天敵や有用昆虫への影響が少ない点でも優れた殺虫剤です。
」が、幅広いチョウ目害虫に高い効果が期待できて、おすすめです。ただ、そのぶん値段がちと高いのが難点ですが・・・(汗)。プレオ フロアブルは乳白色の粘性のある液体で、使用方法は水で1000倍に薄めて散布します。有機リン系など既存の殺虫剤とは異なる新しいタイプの殺虫剤で、既存剤に対して抵抗性を発達させた害虫にも高い殺虫活性を示します。経口及び経皮投与のいずれでも殺虫効果があり、降雨にも流されにくく残効性に優れています。フェニックス顆粒水和剤は、顆粒状の粒剤を2000~4000倍に薄めて散布します。こちらも、害虫の筋肉を収縮させるという従来の殺虫剤とは異なる新しいタイプの薬剤で、収穫前日まで使えることと、天敵や有用昆虫への影響が少ない点でも優れた殺虫剤です。
農薬の薄め方は、こちらをご参考に!![]() 【農薬】混ぜ方・作り方「希釈倍率早見表」
【農薬】混ぜ方・作り方「希釈倍率早見表」
 ナス科の野菜とは、ナスはもちろん、ジャガイモ(馬鈴薯)もナスと全く同じ、”ナス科ナス属”の野菜です。”ナス科トウガラシ属”には、トウガラシ(ピーマンやパプリカ)などがあります。こうしたナス科の野菜の葉が、気が付くと、小さな穴が無数にあけられていて、光合成が十分に出来なくなり、成長が滞り始めることがあります。被害がひどくなると、株が枯れてしまうこともあります。小さな穴が沢山開いているのを見つけたら、出来るだけ早く対処しないと手遅れになってしまいますよ(汗)。
ナス科の野菜とは、ナスはもちろん、ジャガイモ(馬鈴薯)もナスと全く同じ、”ナス科ナス属”の野菜です。”ナス科トウガラシ属”には、トウガラシ(ピーマンやパプリカ)などがあります。こうしたナス科の野菜の葉が、気が付くと、小さな穴が無数にあけられていて、光合成が十分に出来なくなり、成長が滞り始めることがあります。被害がひどくなると、株が枯れてしまうこともあります。小さな穴が沢山開いているのを見つけたら、出来るだけ早く対処しないと手遅れになってしまいますよ(汗)。
 ナス科の野菜の葉に穴をあける、一番やっかいな害虫が、「ナスノミハムシ」(ナストビハムシ、ナスナガスネトビハムシ)です。成虫は、体長が1~2ミリの小さな黒い虫で、捕まえようと手を近づけると、ピョーンと飛び跳ねて逃げてしまい、まず手で捕まえることは出来ません。もちろん数も多く発生するので、テデトールでは対抗できませんので、さっさと農薬のお世話になるのが賢い選択かと(汗)。また、ナスノミハムシは土中に卵を産み、その幼虫がジャガイモ(塊茎)を食い荒らすので、ジャガイモにも醜い小さい虫食い後がいっぱい付いてしまいます(泣)。
ナス科の野菜の葉に穴をあける、一番やっかいな害虫が、「ナスノミハムシ」(ナストビハムシ、ナスナガスネトビハムシ)です。成虫は、体長が1~2ミリの小さな黒い虫で、捕まえようと手を近づけると、ピョーンと飛び跳ねて逃げてしまい、まず手で捕まえることは出来ません。もちろん数も多く発生するので、テデトールでは対抗できませんので、さっさと農薬のお世話になるのが賢い選択かと(汗)。また、ナスノミハムシは土中に卵を産み、その幼虫がジャガイモ(塊茎)を食い荒らすので、ジャガイモにも醜い小さい虫食い後がいっぱい付いてしまいます(泣)。
ナス科の野菜の葉に穴をあける害虫には、ナスノミハムシ(ナストビハムシ、ナスナガスネトビハムシ)以外にも、ウスラミドリカメムシやニジュウヤホシテントウ、ハスモンヨトウなどもいます。
 |
価格:847円 |
ナスやジャガイモ、ピーマン等の葉っぱに、小さい虫食いの穴を見つけたら、速攻で農薬を撒きましょう!。ナスノミハムシなどからナス科の葉を守るのに、おすすめの農薬(殺虫剤)は、「アクタラ顆粒水溶剤![]() 」。100gの容器入りと500gの袋入りなどありますが、家庭菜園で使うには容器入りで十分。小さい顆粒状で、水で 2000~3000倍に溶かして散布します。例えば2000倍で2リットルの農薬を作るには、1g使用します。
」。100gの容器入りと500gの袋入りなどありますが、家庭菜園で使うには容器入りで十分。小さい顆粒状で、水で 2000~3000倍に溶かして散布します。例えば2000倍で2リットルの農薬を作るには、1g使用します。
 |
価格:979円 |
なお、春から夏にかけて畑(圃場)に飛来したナスノミハムシ(ナストビハムシ、ナスナガスネトビハムシ)は、株元に卵を産み付けると、土中で孵化した幼虫がバレイショ塊茎などを食害し、冬には休眠して越冬、翌春に成虫になって、再び大量発生してしまい兼ねません。こうした大量発生の被害を防ぐには、事前の農薬による土壌処理が不可欠になります。ジャガイモを植付ける前や、ナスやピーマンの苗を定植する際に、「アクタラ粒剤![]() 」を株穴に撒いて、作条混和もしくは植穴処理をするのがおすすめ。アクタラ粒剤は1kg入りで1千円ほど、3kg入りもあります。1株あたり1~2gが標準使用量です。
」を株穴に撒いて、作条混和もしくは植穴処理をするのがおすすめ。アクタラ粒剤は1kg入りで1千円ほど、3kg入りもあります。1株あたり1~2gが標準使用量です。
 ナス科の野菜と同様に、ダイコンや小松菜など、アブラナ科の野菜の幼苗の葉を穴だらけにしてしまう、厄介なハムシもいます。その代表格が、「キスジノハムシ」と「ダイコンハムシ」。幼苗のうちに葉に小さな穴を沢山あけられると生育が滞り、被害がひどくなると、苗が枯れてしまうこともあります。体長は2ミリ程度と小さく、黒色で2本の黄色い筋があるのが特徴で、触るとノミの様に飛び跳ねるため、手で捕まえるのは困難です(汗)。さらに迷惑なことに、株元に卵を産み付け、ふ化した幼虫が根を食害し、ダイコンの表面が傷だらけになってしまいます…(泣)。
ナス科の野菜と同様に、ダイコンや小松菜など、アブラナ科の野菜の幼苗の葉を穴だらけにしてしまう、厄介なハムシもいます。その代表格が、「キスジノハムシ」と「ダイコンハムシ」。幼苗のうちに葉に小さな穴を沢山あけられると生育が滞り、被害がひどくなると、苗が枯れてしまうこともあります。体長は2ミリ程度と小さく、黒色で2本の黄色い筋があるのが特徴で、触るとノミの様に飛び跳ねるため、手で捕まえるのは困難です(汗)。さらに迷惑なことに、株元に卵を産み付け、ふ化した幼虫が根を食害し、ダイコンの表面が傷だらけになってしまいます…(泣)。
基本的には、殺虫剤の撒布をおすすめしますが、ダイコンのタネを蒔いたら、すぐに防虫ネットを掛けるのが得策です!。わざわざトンネルにしなくても、穴があいたり破れた不織布などを、「べた掛け」しただけでも効果が期待できます。株が大きくなったら、ネットを剥いでも、後は葉に多少穴を開けられたところで、株が枯れるようなことにはなりません。
ダイコンのキスジノミハムシ駆除に効果があるのは、「アタブロン乳剤![]() 」。100ml入りなら1千円くらいで、ダイコンをはじめキャベツなどアブラナ科の野菜につくアオムシやヨトウムシ、コナガなどにも効果があるので、家庭菜園では一本あると便利な薬剤です!。
」。100ml入りなら1千円くらいで、ダイコンをはじめキャベツなどアブラナ科の野菜につくアオムシやヨトウムシ、コナガなどにも効果があるので、家庭菜園では一本あると便利な薬剤です!。
 一方、スイカやメロン、カボチャ、キュウリなどのウリ科の野菜に群がる茶色い虫は「ウリハムシ」で、こちらは穴を開けるのではなく網目状に歯をボロボロに食い荒らします。土に卵を産み、その幼虫が根を食い荒らし、春から夏にかけて成虫となって葉を食い荒らした挙句、成虫自身も浅い土中で越冬するので、放っておくとますます増殖して大変なことになります…(汗)。
一方、スイカやメロン、カボチャ、キュウリなどのウリ科の野菜に群がる茶色い虫は「ウリハムシ」で、こちらは穴を開けるのではなく網目状に歯をボロボロに食い荒らします。土に卵を産み、その幼虫が根を食い荒らし、春から夏にかけて成虫となって葉を食い荒らした挙句、成虫自身も浅い土中で越冬するので、放っておくとますます増殖して大変なことになります…(汗)。
ウリハムシ駆除の基本的な第一歩は、補殺です。日中は活動が活発で、手を近づけるとパッと飛び立ってしまうため捕まえるのは困難ですが、朝早くだと動きが鈍いので簡単に手で捕まえられます。指でつまんで潰してしまうのが手っ取り早いですが、そんなおぞましいことは出来ないという方は、ペットボトルの口を葉に当てて捕獲すると良いでしょう!。
しかし、“テデトール”では追い付かなくなってしまったら、農薬に頼るしかありません。ウリハムシに効果がある農薬(殺虫剤)は、マラソン乳剤![]() やダントツ水溶剤
やダントツ水溶剤![]() 、モスピラン顆粒水溶剤
、モスピラン顆粒水溶剤![]() などですが、家庭菜園で使うには汎用性が高く安価な「マラソン乳剤」がおすすめです。かぼちゃ、きゅうり、すいか、メロン、うり類(漬物用)に適用登録されていて、1000倍に薄めて散布します。収穫前日まで(3回)使用できるのも助かります!。
などですが、家庭菜園で使うには汎用性が高く安価な「マラソン乳剤」がおすすめです。かぼちゃ、きゅうり、すいか、メロン、うり類(漬物用)に適用登録されていて、1000倍に薄めて散布します。収穫前日まで(3回)使用できるのも助かります!。
なお、農薬を撒く噴霧液を作る際には、「展着剤」も一緒に混ぜると、野菜の葉や実に薬剤が付着しやすくなり、その効果が高まります。特に、葉の表面が水をはじきやすい、キャベツやネギなどに液状の農薬を散布する際には、展着剤は不可欠です。
 |
ダイン 100ml 住友化学園芸 薬剤の効果を高める 展着剤 価格:313円 |
展着剤の価格はピンキリで、小瓶で200~300円のもあれば、1千円、2千円とするものまであります。展着剤の基本となる有効成分は、植物に付着しやすくするための、いわゆる”界面活性剤”なのですが、薬剤の吸収率を高めたり、雨が降っても流れにくくしたりする効能や、薬剤との相性もあって、多種多様です。非イオン系とか、シリコーン系とか、正直よく分かりません・・・(汗)。
そこで私がよく使っている展着剤は、一番安くて汎用的な、「ダイン![]() 」。小瓶なら2~3百円で買えて、数年間はひと瓶あれば事足ります(ただし、有効期間内にお使い下さい)。
」。小瓶なら2~3百円で買えて、数年間はひと瓶あれば事足ります(ただし、有効期間内にお使い下さい)。
堆肥や肥料、石灰を撒いて耕し、畝を立てて、種を蒔いてから2~3週間、せっせと水遣りをして、ようやく芽が出て育ち始めたころ。朝起きて、小さな苗を見てみると、根元からポッキリと折れ、倒れてしまっていることがあります。土の表面の茎の生え際をよく見てみると、何かにかじられた痕が・・・(汗)。「ネキリムシ」の仕業です!(怒)。
 ネキリムシとは、ヨトウガやカブラヤガなど「ヤガ」(夜飛ぶ蛾)の幼虫の総称で、その幼虫も昼間は土の中に潜っていて、夜になると地表へ出てきて、生え際の野菜の茎を食害します。代表的なのが、ヨトウガの幼虫の「ヨトウムシ」。ヨトウムシは、幼苗の茎だけでなく、生育中の野菜の葉や花までも食害してしまう、害虫中の害虫で、その悪行から”夜盗虫”という名前が付けられたそうです。
ネキリムシとは、ヨトウガやカブラヤガなど「ヤガ」(夜飛ぶ蛾)の幼虫の総称で、その幼虫も昼間は土の中に潜っていて、夜になると地表へ出てきて、生え際の野菜の茎を食害します。代表的なのが、ヨトウガの幼虫の「ヨトウムシ」。ヨトウムシは、幼苗の茎だけでなく、生育中の野菜の葉や花までも食害してしまう、害虫中の害虫で、その悪行から”夜盗虫”という名前が付けられたそうです。
ネキリムシの対処も、基本はテデトール(捕殺)です。昼間は土の中に潜伏していますが、食害された株の周りを丁寧に掘り起こすと、たいていは見つけることができます。
ただし、テデトールでネキリムシを捕まえるには、株が食害されるのを待たなければなりません(汗)。タマネギや長ネギなどの様に、苗を必要以上に大量に育苗している時なら、数本倒されたところで大した影響はありませんが、せっかく買ってきて定植した苗をかじられた日には、目も当てられません(泣)。
そこで、農薬(殺虫剤)の登場となります。
 |
エムシー緑化 殺虫剤 ネキリエースK(ネキリムシ類、コオロギ類などに) 600g 価格:705円 |
私のおすすめは、ネキリムシ駆除には、「ネキリエース![]() 」か「ガードベイトA」。種まきや定植する前、畝立て時に土中に「ダイアジノン
」か「ガードベイトA」。種まきや定植する前、畝立て時に土中に「ダイアジノン![]() 」などの殺虫剤を鋤き込むことで、ネキリムシやコガネムシの幼虫など、土中に潜む害虫を広範囲に駆除する方法もありますが、土中に滞留し分解まで長い日数を要する土中殺虫剤は、出来ればあまり使いたくありません。
」などの殺虫剤を鋤き込むことで、ネキリムシやコガネムシの幼虫など、土中に潜む害虫を広範囲に駆除する方法もありますが、土中に滞留し分解まで長い日数を要する土中殺虫剤は、出来ればあまり使いたくありません。
その点、ネキリエースやガードベイトAは誘引殺虫剤なので、数ミリ大の赤い粒剤を株の周りに数粒ずつパラパラと撒いておけば、夜に表に出てきたネキリムシが、勝手に殺虫剤を食べてお亡くなりになります(笑)。残ったネキリエースは、雨に流され、土中で分解されて、10~20日ほどかけて徐々に薬効力を消失していきます。その間の植物への吸収性も、基本的に無いとされているので、私は安心して使っています。
なんか最近、キュウリやオクラが元気がない、そのうち枯れちゃったなんてことはありませんか?。また、落花生を収穫しようと掘り起こしたら、ほとんどの実がかじられていたなんてことは?。「コガネムシの幼虫」の仕業です!(怒)。
 コガネムシの幼虫は、乳白色したイモムシ状の個体で、カブトムシの幼虫によく似ていますが、カブトムシの幼虫よりちょっと小ぶり。成虫になるまでの1~2年間、土中に生息し、植物の根や土中に出来た落花生の実などを食害してしまいます。コガネムシの幼虫の駆除方法も、やはり基本は、見つけ次第の捕殺です。しかし鍬で鋤いて、土の中から1匹2匹出てくるなら大してビックリしませんが、酷い時には、一株の落花生の周囲から、10匹も20匹も出てくることがあり、その大群を見ると、結構ゾ~ッとします(汗)。
コガネムシの幼虫は、乳白色したイモムシ状の個体で、カブトムシの幼虫によく似ていますが、カブトムシの幼虫よりちょっと小ぶり。成虫になるまでの1~2年間、土中に生息し、植物の根や土中に出来た落花生の実などを食害してしまいます。コガネムシの幼虫の駆除方法も、やはり基本は、見つけ次第の捕殺です。しかし鍬で鋤いて、土の中から1匹2匹出てくるなら大してビックリしませんが、酷い時には、一株の落花生の周囲から、10匹も20匹も出てくることがあり、その大群を見ると、結構ゾ~ッとします(汗)。
コガネムシは、未熟な有機物資材(魚粕やだいず粕、鶏糞堆肥など)が分解する時に発生する発酵臭に誘引され集まってきやすいので、未熟堆肥の多用を避け、堆肥を畑に撒く際は、土の表面に出ない様に、穴を掘って埋めるか、土中内に鋤き込むようにしましょう。また、畑の周りにコガネムシが好む樹木が植えられていると、どうしても発生しやすくなります。圃場内でコガネムシが飛来するのを見つけたら、即、テデトール処置をしてください!(笑)。コガネムシが好む樹木には、栗やブドウ、柿の木などの果樹のほか、カシやマキ類、ヤナギなどの庭木もあり、さすがに切るのは忍びないので、コガネムシの幼虫に悩まされたら、農薬散布に頼りましょう。
 |
価格:1,360円 |
コガネムシの幼虫の駆除には、私はもっぱら「ダイアジノン粒剤![]() 」を散布しています。
」を散布しています。
ダイアジノンは、有機リン系殺虫剤の一種で、稲作でも広く用いられ、犬や猫のペット用ノミ取り首輪にも使われています。ネキリムシ類、タネバエ、ケラ、コガネムシ類の幼虫など、多くの土壌害虫に速効的な殺虫効力があり、適用作目の種類が60以上と幅広く使える、便利な農薬です。
コガネムシは、初夏から夏にかけて産卵し、孵化した幼虫は土の中で越冬し、春になってサナギになり、数週間で成虫へと脱皮します。したがって、ダイアジノンを撒くには、夏から秋にかけて撒くと効果的ですが、あまり野菜の収穫時期近くになってからは、撒きたくありません。基本的な使用方法は、播種前に、畑に必要量の粒剤を撒いて、土の中に鋤き込みます。なお、コガネムシの幼虫などは、土の表面近くにいますので、あまり深く鋤き込むのではなく、浅めに混和した方が効果的です。なお、小松菜やミズナ、オクラなどの土壌表面散布の登録がある作物では、混和しなくても使用できます。
ここまで紹介した私が家庭菜園での使用におすすめする農薬(害虫防除剤、殺虫剤)について、成分系と剤型別に分類して一覧表にしておきます。害虫も生きるためには必死で、徐々に農薬に対して対抗性を持つようになります。そのため害虫駆除を徹底するためには、異なる成分系から成る適用表(適用作物名ならびに適用病害虫名)が該当する農薬を交互に使うなどすると、より効果が期待できる場合があります。
野菜を栽培していると、害虫だけでなく、病気による被害も受けます。カビや細菌、ウイルスによる病気など、多種多様です。主なものでは、キュウリやカボチャに発生しやすい「うどんこ病」や、ダイコンなどのアブラナ科の野菜で発病する「根こぶ病」。梅雨の長雨など高温多湿により発生しやすいカビによる「カビ病」や「ベト病」、「根腐れ病」や、アブラムシが媒介するウイルスによる「モザイク病」などがあります。
 野菜苗が病気に侵された場合の対処の基本は、圃場外撤去と、焼却です。しかし、生産のために多くの苗を育てているのであればいいでしょうが、家庭菜園で、数株しか育てていない野菜の苗が病気にかかってしまうと、ダメージが結構大きいです(泣)。そこで、早期発見、早期処置に徹して、なんとか病気を治したいものです。でも、病気の治療は、さすがに自然治癒を期待するのは難しいので、薬剤に頼るしかありません。
野菜苗が病気に侵された場合の対処の基本は、圃場外撤去と、焼却です。しかし、生産のために多くの苗を育てているのであればいいでしょうが、家庭菜園で、数株しか育てていない野菜の苗が病気にかかってしまうと、ダメージが結構大きいです(泣)。そこで、早期発見、早期処置に徹して、なんとか病気を治したいものです。でも、病気の治療は、さすがに自然治癒を期待するのは難しいので、薬剤に頼るしかありません。
野菜の病気への処置は、その原因と種類によって対応すべきですが、たいていは病原菌による病気なので、まずは「殺菌剤」を使用するのが、手っ取り早い対処法です。
 |
価格:878円 |
私が普段使っている殺菌剤は、扱いやすい液体で、安価で汎用性のある「ダコニール1000![]() 」。広範囲の病害に有効で、発売以来、耐性菌の出現事例が無いという優れものです。そのうえ、小瓶(250ml)なら1千円以内と殺菌剤では安価なことも助かります。標準的な希釈倍率は1,000倍なので、250リットルもの撒布溶液が作れます。4Lずつ作っても、60回分以上…。
」。広範囲の病害に有効で、発売以来、耐性菌の出現事例が無いという優れものです。そのうえ、小瓶(250ml)なら1千円以内と殺菌剤では安価なことも助かります。標準的な希釈倍率は1,000倍なので、250リットルもの撒布溶液が作れます。4Lずつ作っても、60回分以上…。
ダコニールが効かない場合は、少々お高いですが、新規有効成分クレソキシムメチルにより、従来の殺菌剤とは異なる新しい作用効果が期待できるという、「ストロビー![]() 」を使います。予防効果も高いので、病気が発生しやすいキュウリやスイカ、メロンなどには、事前にストロビーを撒いておくのも一考ですね。
」を使います。予防効果も高いので、病気が発生しやすいキュウリやスイカ、メロンなどには、事前にストロビーを撒いておくのも一考ですね。
滅多に使用しない殺菌剤を買うのは勿体ないという人は、野菜や果樹、稲作農家が知り合いにいれば、水溶剤(粉剤)の殺菌剤を分けてもらうというのも手です。長野では、近隣に田んぼやリンゴ農家が多く、たいていは「トップジンM水和剤![]() 」や「ベンレート水和剤
」や「ベンレート水和剤![]() 」など、汎用的な殺菌剤を大量にストックしています。500g入りの袋から、10gほども拝借すれば、家庭菜園なら2~3年は使えますよ!(笑)。水和剤(粉剤)は、液剤に比べて少量を扱うには不便なので、小分けした少量の小袋入りも売られていますが、割高感が否めません(汗)。
」など、汎用的な殺菌剤を大量にストックしています。500g入りの袋から、10gほども拝借すれば、家庭菜園なら2~3年は使えますよ!(笑)。水和剤(粉剤)は、液剤に比べて少量を扱うには不便なので、小分けした少量の小袋入りも売られていますが、割高感が否めません(汗)。
なお、野菜栽培で、まず病気の発症を無くすためには、①連作障害の出やすい作物を同じ場所で続けて栽培しなこと、②密植を避けて風通しをよくすること、③水はけの悪い土地では高畝にすること、などの注意が必要です。
| 分類 | 作物名 | ダコニール 1000 | トップジン M水和剤 | ベンレート 水和剤 |
|---|---|---|---|---|
| 野菜 | ||||
| あしたば | ○ | |||
| あずき | ○ | |||
| アスパラガス | ○ | ○ | ○ | |
| いちご | ○ | ○ | ○ | |
| いんげんまめ | ○ | ○ | ||
| うど | ○ | ○ | ||
| うり類(漬物用) | ○ | ○ | ○ | |
| えだまめ | ○ | ○ | ||
| えんどうまめ | ○ | ○ | ||
| オクラ | ○ | ○ | ○ | |
| かぼちゃ | ○ | ○ | ||
| カリフラワー | ○ | ○ | ○ | |
| キャベツ | ○ | ○ | ○ | |
| きゅうり | ○ | ○ | ○ | |
| ごぼう | ○ | |||
| さといも(葉柄) | ○ | ○ | ||
| さやいんげん | ○ | ○ | ||
| さやえんどう | ○ | |||
| ししとう | ○ | |||
| しそ | ○ | ○ | ||
| しょうが | ○ | ○ | ○ | |
| すいか | ○ | ○ | ○ | |
| ズッキーニ | ○ | ○ | ||
| せり | ○ | |||
| セルリー | ○ | ○ | ||
| だいこん | ○ | |||
| だいず | ○ | ○ | ||
| たまねぎ | ○ | ○ | ○ | |
| チンゲンサイ | ○ | |||
| つるむらさき | ○ | |||
| とうもろこし | ○ | |||
| トマト | ○ | ○ | ○ | |
| なす | ○ | ○ | ||
| なばな | ○ | |||
| にがうり | ○ | ○ | ||
| にら | ○ | |||
| にんじん | ○ | |||
| にんにく | ○ | |||
| ねぎ | ○ | ○ | ○ | |
| はくさい | ○ | ○ | ○ | |
| パセリ | ○ | |||
| ばれいしょ | ○ | ○ | ○ | |
| ピーマン | ○ | ○ | ○ | |
| ふき | ○ | ○ | ||
| ブロッコリー | ○ | ○ | ○ | |
| ほうれんそう | ○ | |||
| みずな | ○ | ○ | ||
| みつば | ○ | ○ | ○ | |
| ミニトマト | ○ | ○ | ○ | |
| みょうが | ○ | ○ | ||
| メロン | ○ | ○ | ○ | |
| やまのいも | ○ | ○ | ||
| ゆうがお | ○ | |||
| らっかせい | ○ | ○ | ○ | |
| らっきょう | ○ | ○ | ○ | |
| リーフレタス・非結球レタス | ○ | ○ | ||
| レタス | ○ | ○ | ○ | |
| わけぎ | ○ | ○ | ||
| 果樹 | ||||
| あけび(果実) | ○ | |||
| あんず | ○ | |||
| いちじく | ○ | |||
| うめ | ○ | |||
| おうとう(サクランボ) | ○ | ○ | ||
| かき | ○ | ○ | ||
| キウイフルーツ | ○ | ○ | ○ | |
| くり | ○ | ○ | ||
| さくら | ○ | |||
| たらのき | ○ | ○ | ||
| なし | ○ | ○ | ○ | |
| ネクタリン | ○ | ○ | ||
| びわ | ○ | ○ | ||
| ぶどう | ○ | ○ | ||
| みかん | ○ | ○ | ||
| もも | ○ | ○ | ○ | |
| りんご | ○ | ○ | ○ | |
| 稲麦 | ||||
| 稲・水稲 | ○ | ○ | ○ | |
| 小麦 | ○ | ○ | ||
| 花き | ||||
| カーネーション | ○ | |||
| きく | ○ | ○ | ○ | |
| きんせんか | ○ | |||
| けいとう | ○ | |||
| さくらそう | ○ | |||
| シクラメン | ○ | ○ | ||
| つつじ類 | ○ | ○ | ||
| トルコキ゛キョウ | ○ | |||
| チューリップ | ○ | ○ | ○ | |
| ばら | ○ | ○ | ○ | |
| ほおずき | ○ | |||
| ぼけ | ○ | |||
| ぼたん | ○ | |||
| ゆり | ○ | ○ | ||
| りんどう | ○ | ○ | ○ | |
| 観葉植物 | ○ | ○ | ||
| 西洋芝 | ○ | |||
※ 適用作物は全部ではありません(私が栽培していない、あるいは栽培に関わらない作物は除いています)。野菜のうち、黄色く塗った作物は殺菌剤の散布が必要になることが多そうな野菜、空色の作物は殺菌剤の撒布が場合によってあり得そうな野菜を挙げてみました。
複数の薬剤を混ぜて使うことを、「混用」と言います。野菜農家や果樹農家など、広大な面積の作物を栽培している農家では、大きな機械で効率的に農薬を撒布しないと作業が間に合わないので、複数の殺虫剤や殺菌剤を混ぜて、一度に撒布しています。ただし、農薬を混用するには、混ぜていい農薬や混ぜてはいけない農薬などがあり、専門知識が必要です。また、知識の乏しい素人が、同じ有効成分の入った複数種類の農薬を混用してしまったら、薬効成分が基準値の複数倍もの濃度になってしまい、人体に害を与えかねません…(汗)。家庭菜園で農薬を使用する際は、できれば「混用」は避けた方が無難です。ちょっと手間にはなりますが、撒布液を調合する際には、できるだけ短期間で使い切れるよう、少量ずつ作りましょう。
ちなみに、住友化学園芸のホームページによると、特に、石灰硫黄合剤や強アルカリ性の薬剤は混用には不向きだそうです。また、住友化学の「i-農力」のページには、農薬を混用する際の順番も記されています。混用する際には、水になじみやすい①展着剤、②液剤・水溶剤、③乳剤・フロアブル、④水和剤 の順番で混ぜるそうです。やっぱ、素人には難しそうですね…(汗)。
![]()