都会からリタイアして地元の田舎に戻り始めた家庭菜園、少しずつ学んだ野菜の育て方のコツをまとめてみました。
ジャガイモ(馬鈴薯)は、ナス科ナス属の多年草で、南アメリカのアンデス山脈が原産地とされています。日本には、1598年にオランダ人によって、ジャワ島のジャガタラを経由して伝来したとされ(諸説あり)、ジャガタライモと呼ばれていたのが後にジャガイモになったとか。ちなみに、ジャガイモは地下に出来た実か、根の一部が巨大化したモノだと思っていたら、実は茎(地下茎)の一部(塊茎)なんだそうです!。サトイモも同じ塊茎ですが、サツマイモは根(塊根)なんだそうです。見分け方は、サツマイモはあちこちから根の先に当たるヒゲ根が生えていますが、ジャガイモやサトイモには生えていません。日本テレビ『クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?』で、問題に取り上げられていました。小学3年生の理科で習うそうですよ…(汗)。
ジャガイモの栽培は、ジャガイモそのものを種芋として植え付け、増やして栽培しますが、自家採取した(前年に収穫した)ジャガイモは病気になりやすいので、種芋には向きません。必ず購入した、無病検査済みか殺菌済みの種芋を使いましょう!。とは言え、去年収穫して貯蔵しておいた、芽が出て萎びたジャガイモでも、埋めればそこそこ収穫できます!(笑)。ただし、ダメになる株も多いので、『労多くして功少なし…』(汗)。結局、種イモは買った方が早かったということに成りがちなのですが、種イモを買いそびれとか、ちょっと買い足りなかったという場合には、予備に古芋を植えてみるのも、一つの手です!。
栽培時期は、3月~4月に植え付ける春栽培と、8月下旬~9月に植え付ける秋栽培とがありますが、作りやすい春栽培が一般的です。よっぽど暖かい地域でないと、秋栽培では寒くなるまでに収穫が間に合わず、あまり収量が得られません。ジャガイモは長期保存が可能で、特に長野県あたりだと、春栽培で初夏に収穫したジャガイモでも、冬の間中は貯蔵しておけますので、あえて秋栽培をする必要性がありません。どうしても、秋に新ジャガが食べたいとか、畑が狭くて春栽培だけでは冬を越すのに必要なジャガイモの量が収穫できないという場合には、秋栽培に向いた品種を選んで、チャレンジしてみてください。
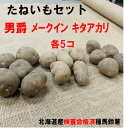

ジャガイモは、春栽培と秋栽培がありますが、春栽培が一般的。特に長野県の様に冬が早くやってくる寒冷地では、夏の気温が下がりだしてから種芋を植え付けたのでは、霜が降りるまでに成熟がなかなか間に合いません。ここでは主に春栽培を前提に、栽培方法を紹介します。
私の経験上、春栽培だと、1kgの種芋から、大き目の段ボール箱にいっぱいのジャガイモが収穫できます(男爵の場合)。重さだと、約15kgくらいでしょうか。
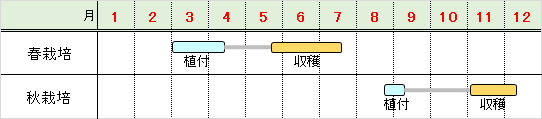
植えるジャガイモの品種と量が決まったら、植え付ける2週間ほど前に、よい種芋を早めに入手するようにしましょう。業者は、他の店より少しでも早く多く売りたいので、結構早い時期から種芋は店頭に並び始めます。すると、気の早い農家が、良い種芋を我先にと購入するので、種芋の発売時期が年々ますます早まっています…(汗)。ただし、早い時期の種芋は、ほとんど芽が出ていません。そこで、2週間ほど前から室内の日の当たる場所に置いて発芽を促し、植え付ける前までに、大きな出べそくらいまで発芽させておきます。発芽が不十分のまま植え付けると、芽が出る前に種芋が腐ってしまうことがあります。逆に、発芽しすぎた種芋からは、丈夫な苗が育たたないので、売れ残りの種芋を買う際には注意してください。
さて、種芋選びで毎年悩むのが、種芋の大きさ。種芋が鶏卵より大きいと、芽がたくさん出すぎるので、2~3等分に切り分けますが、切り分けると種芋が腐る原因になりやすいので、切り分ける必要のない、小さめの種芋が数多く入っている袋を選んで買う人が多いです。種芋は、通常はキログラム単位で売られていますので、小さければ数が増え、大きければ数は少なくなります。しかし、私の信条は、『小さい種から、大きな実は育たない』という考え方!。そこで私は、人とは逆に、できるだけ大きな種芋を買うようにしています(笑)。
 大きな種芋は、切り分ける必要があります。切り分ける目安は、大きさだと鶏卵より大きなもの、重さでは50~60g以上のもの。1片が30~40g前後になるように、2~3等分します。ジャガイモの頭は、芽がたくさん集まっている所ですが、そこを頂点に、左右に芽の数が大よそ均等になるように切り分けます。さてここで、何時切り分けるか?。大抵の書物では、『植え付ける数日前に切り分け、切り口には草木灰を擦り込み、陽に当てて切り口を乾かせ』と書かれていますが、私は絶対にそんなことしません!。草木灰なんて雑菌だらけ、さらに小分けした種芋を乾かし過ぎたら、養分が減ってしまい、よい種芋になんてなるわけがありません(汗)。
大きな種芋は、切り分ける必要があります。切り分ける目安は、大きさだと鶏卵より大きなもの、重さでは50~60g以上のもの。1片が30~40g前後になるように、2~3等分します。ジャガイモの頭は、芽がたくさん集まっている所ですが、そこを頂点に、左右に芽の数が大よそ均等になるように切り分けます。さてここで、何時切り分けるか?。大抵の書物では、『植え付ける数日前に切り分け、切り口には草木灰を擦り込み、陽に当てて切り口を乾かせ』と書かれていますが、私は絶対にそんなことしません!。草木灰なんて雑菌だらけ、さらに小分けした種芋を乾かし過ぎたら、養分が減ってしまい、よい種芋になんてなるわけがありません(汗)。
 切り分けるのは、植え付ける直前。そして切り口には、「有機石灰
切り分けるのは、植え付ける直前。そして切り口には、「有機石灰」をまぶし、伏せる際にも種芋を置く場所の土に有機石灰を撒いておきます。これで種芋が腐ったなんてことは、まずありません!(笑)。ただし、ジャガイモを切り分けるためだけに有機石灰を買うのは勿体ないです。家庭菜園で使う石灰と言えば、苦土石灰が一般的ですが、苦土石灰は土を固くしてしまいますが、有機石灰は土を柔らかくします。有機石灰は苦土石灰より値段は高めですが、両方を買っておいて、うまく使い分けるのがミソです(笑)。
 堆肥を漉き込み、深く耕してから、クワで5cm~10cmの深さのまき溝を掘ります。特に畝を立てる必要はありません。ここで注意したいのが、まき溝の深さ、つまり種芋を植える深さです。ジャガイモは湿気を嫌うので、できるだけ浅植えが好ましいのですが、浅く植えるとその後の土寄せ作業が大変。特に固い粘土質の土だと、一苦労です(汗)。そこで私は、水捌けの悪い粘土質なのに、逆に深植えを心がけています。本当は良くないのですが、土寄せの苦労を考えると、品質に贅沢は言えません。まき溝の条間(畝間)は、70~80cm。浅植えするほど、土寄せに沢山の土が必要となるので、条間を広めに取ります。
堆肥を漉き込み、深く耕してから、クワで5cm~10cmの深さのまき溝を掘ります。特に畝を立てる必要はありません。ここで注意したいのが、まき溝の深さ、つまり種芋を植える深さです。ジャガイモは湿気を嫌うので、できるだけ浅植えが好ましいのですが、浅く植えるとその後の土寄せ作業が大変。特に固い粘土質の土だと、一苦労です(汗)。そこで私は、水捌けの悪い粘土質なのに、逆に深植えを心がけています。本当は良くないのですが、土寄せの苦労を考えると、品質に贅沢は言えません。まき溝の条間(畝間)は、70~80cm。浅植えするほど、土寄せに沢山の土が必要となるので、条間を広めに取ります。
 掘ったまき溝に、種芋を伏せていきます。『伏(ふ)せる』という言い方は、切った種芋の切り口が下になるように置くからでしょうか?。もしかしたら、当地だけの方言かもしれません(汗)。切り口を下に向けるのは、上から滲みてくる雨水が切り口に滞留しないようにするためです。種芋を伏せる間隔は 30cm、ちょうど大人の男性の長靴の長さ一つ分程度。まき溝に入って歩きながら、種芋を伏せていきます。
掘ったまき溝に、種芋を伏せていきます。『伏(ふ)せる』という言い方は、切った種芋の切り口が下になるように置くからでしょうか?。もしかしたら、当地だけの方言かもしれません(汗)。切り口を下に向けるのは、上から滲みてくる雨水が切り口に滞留しないようにするためです。種芋を伏せる間隔は 30cm、ちょうど大人の男性の長靴の長さ一つ分程度。まき溝に入って歩きながら、種芋を伏せていきます。
種芋を伏せ終わったら、種芋と種芋の間に、ハンドスコップ1杯の鶏糞か菜種粕を置いていきます。上にかける土の厚さは、種芋の頭から5cm程度。土を厚くかけすぎると、発芽までの時間がかかり過ぎ、種芋を腐らせる原因にもなりかねません!。
ジャガイモ栽培で、何が一番大変かといえば、土寄せ作業。特に、我が家のように粘土質の固くて重い土だと、なおさらです(泣)。そこで、土寄せが大変という人には、土寄せする必要がない、マルチ(黒マルチシート![]() )を使った栽培方法がおすすめ!。
)を使った栽培方法がおすすめ!。
 そもそも、ジャガイモ栽培で土寄せをするのは、ジャガイモの緑変を防止するため。新しくできる子芋は、種芋の上に上にと出来ますが、その子芋の表面が土の外に出てしまうと、日光に当たって緑色に変色してしまいます。これは、天然毒素のソラニンという物質が生成されてしまうためで、緑色に変色したジャガイモは、食べられません。そこで、ジャガイモの成長に合わせて、3回くらい土寄せをして、子芋が土の外に出るのを防ぎます。しかし、日光を通さない黒マルチシートを被せてしまえば、子芋の緑変は防げますので、土寄せする作業が必要無くなります!。
そもそも、ジャガイモ栽培で土寄せをするのは、ジャガイモの緑変を防止するため。新しくできる子芋は、種芋の上に上にと出来ますが、その子芋の表面が土の外に出てしまうと、日光に当たって緑色に変色してしまいます。これは、天然毒素のソラニンという物質が生成されてしまうためで、緑色に変色したジャガイモは、食べられません。そこで、ジャガイモの成長に合わせて、3回くらい土寄せをして、子芋が土の外に出るのを防ぎます。しかし、日光を通さない黒マルチシートを被せてしまえば、子芋の緑変は防げますので、土寄せする作業が必要無くなります!。
堆肥を漉き込み、深く耕したら、マルチ栽培では畝を立てます。畝の高さは5~10cm、水捌けが悪い圃場ほど、高畝にします。畝幅は、95cm幅のマルチシートを使うなら70cm程度まで、ギリギリ2条植え出来ます。
 30cm間隔で、有機石灰をまぶした種芋を伏せていきます。マルチ栽培では、深く植え付ける必要がないので、まき溝は掘りません。覆土厚が2~3cm程度になる深さに、種芋を植え付けます。覆土は必要無いという人もいますが、日が当たると黒マルチシートの下は結構な高温になるので、焼けつき防止に、多少は覆土した方がいいと私は思います。なお、マルチ栽培をする場合は、上から雨水が滲み込んでくる心配がないので、種芋の切り口は上を向けます。そうすると、種芋の芽は下を向き、その芽が地上に出てくるまでには、相当のストレスがかかります。それにより、丈夫な芽のみを残すことが出来るそうです!。ただし、それが本当かどうかは、誰も知りません(笑)。
30cm間隔で、有機石灰をまぶした種芋を伏せていきます。マルチ栽培では、深く植え付ける必要がないので、まき溝は掘りません。覆土厚が2~3cm程度になる深さに、種芋を植え付けます。覆土は必要無いという人もいますが、日が当たると黒マルチシートの下は結構な高温になるので、焼けつき防止に、多少は覆土した方がいいと私は思います。なお、マルチ栽培をする場合は、上から雨水が滲み込んでくる心配がないので、種芋の切り口は上を向けます。そうすると、種芋の芽は下を向き、その芽が地上に出てくるまでには、相当のストレスがかかります。それにより、丈夫な芽のみを残すことが出来るそうです!。ただし、それが本当かどうかは、誰も知りません(笑)。
種芋を伏せ終わったら、上からマルチを掛けますが、この時つい、肥料を撒くのを忘れがち!。土の上に、鶏糞か菜種粕を撒いておきましょう。私は何度、一度掛けたマルチを剥いだことか・・・(汗)。
 種芋を植えてから、約20日ほどで芽が出てきます。マルチシートがピコっと突き出た場所を見つけたら、その上に手のひらを当ててみると、下に弾力のある芽が出てきているかどうか、誰にでもすぐ分かります。ただし、スギナの芽の場合もあるので、ご注意を…(汗)。ジャガイモの芽だと分かったら、その部分のマルチを指先で破って、芽をマルチの外に出してあげます。
種芋を植えてから、約20日ほどで芽が出てきます。マルチシートがピコっと突き出た場所を見つけたら、その上に手のひらを当ててみると、下に弾力のある芽が出てきているかどうか、誰にでもすぐ分かります。ただし、スギナの芽の場合もあるので、ご注意を…(汗)。ジャガイモの芽だと分かったら、その部分のマルチを指先で破って、芽をマルチの外に出してあげます。
穴を開ける数、つまり残す芽の数は、1つの種芋につき基本は2つまで。穴を開けてやらないと、後から出てきた芽は枯れるか、曲がって先に開けた穴から出てこようとしますが、その場合は引き抜いて間引き、2本立ちとします。もちろん好みに応じて、1本立てでも、3本立てでも栽培も可能ですよ(笑)。
マルチ栽培の場合は、土寄せ作業も追肥も不要なので、芽欠きだけしたら、そのまま収穫期まで見守りましょう(笑)。ただし、草がボウボウに伸びてきたら草刈りをし、テントウムシダマシやナスミノハムシなどの害虫が付いたら、「アクタラ顆粒水溶剤![]() 」などの農薬を撒きます。
」などの農薬を撒きます。
発芽したジャガイモの茎の長さが10cm位になったら、「芽欠き」をします。残す芽の数は、1個の種芋毎に2本が一般的。そんなに収量は要らない、とにかく大きいジャガイモが欲しいという人は1本立ちに、小芋が沢山欲しいという人は3本立ちにしてみましょう(笑)。あまり茎が長く成長してからだと、どれが別の芽で、どれが分かれた茎かが分かり難いので、芽欠き作業は早めにした方がいいです!。
芽欠きの方法は、残す芽の土元を片手で押さえながら、反対の手で芽欠きする芽をつかんで、途中で切れないように注意しながら抜き取ります。途中で千切れると、また芽が生えてきてしまいますが、その場合はまた芽欠きをすればOKです。
一通り芽欠きが済んだら、1回目の追肥と土寄せをします。以後、2週間毎くらいに計2~3回、追肥と土寄せを繰り返します。土寄せ作業をすることで、雑草も同時に除去できます。
種芋を伏せてから約3ヶ月も経てば、新ジャガが収穫できます。まずは試し掘りで、一株ずつ掘り起し、新ジャガを美味しく頂きましょう!(笑)。
 ジャガイモの茎や葉が枯れ、ほぼ全部倒れたら、ジャガイモの収穫の適期。収穫が早すぎると、貯蔵性が悪くなり、遅すぎると、芽が出たり傷んだりしてしまうので、収穫時期の見極めが重要です。最初のうちは、近所のベテランの人の作業を見ていて、そのタイミングを真似るのが一番!(笑)。
ジャガイモの茎や葉が枯れ、ほぼ全部倒れたら、ジャガイモの収穫の適期。収穫が早すぎると、貯蔵性が悪くなり、遅すぎると、芽が出たり傷んだりしてしまうので、収穫時期の見極めが重要です。最初のうちは、近所のベテランの人の作業を見ていて、そのタイミングを真似るのが一番!(笑)。
しかし、その収穫作業に影響を及ぼす厄介者が、天気!。ちょうど梅雨の時期と重なってしまうからです。表面が湿った状態のまま、ジャガイモを貯蔵すると、傷んでしまいますので、晴れの日が3日間くらい続く期間を見定め、3日目の朝にジャガイモを掘り起こしたら、畑に並べて乾かします。午後には表面が乾くので、軽く土を落とし、紙の米袋か段ボール箱に入れ、物置や土蔵など、湿気が少ない涼しい場所で貯蔵します。
なお、猛暑日の強い日差しの下で収穫作業をする場合は、天日干しの時間にご注意あれ!。私は一度、梅雨の長雨続きで収穫が遅くなり、めちゃくちゃ暑い炎天下で収穫し、収穫したジャガイモを畑に並べて置いていたら、数時間でジャガイモが焼け付いてしまいました(汗)。日焼けしたジャガイモは、そこから直ぐに傷んでしまうので、貯蔵することが出来ません(泣)。
また、ジャガイモを収穫する際には、クワやマンノウを使って周りから丁寧に掘り起し、ジャガイモを傷つけないように注意しましょう。この時、どんな小さな芋でも、できるだけ全部取り除くことが重要!。畑に残してしまうと、来年になって土の中から芽が出てしまい、厄介です(汗)。
 土が固い畑だと、ジャガイモを掘る収穫作業も大変です。しかし、マルチ栽培であれば、浅い場所にジャガイモが成っているので、さほど土を掘らずに済みます(笑)。芽を出すために開けたマルチの穴から光が入って、芋が緑変しないか心配でしたが、緑変したのは数個のみで、土寄せ栽培の場合より少ないくらいでした。
土が固い畑だと、ジャガイモを掘る収穫作業も大変です。しかし、マルチ栽培であれば、浅い場所にジャガイモが成っているので、さほど土を掘らずに済みます(笑)。芽を出すために開けたマルチの穴から光が入って、芋が緑変しないか心配でしたが、緑変したのは数個のみで、土寄せ栽培の場合より少ないくらいでした。
![]()