都会からリタイアして地元の田舎に戻り始めた家庭菜園、少しずつ学んだ野菜の育て方のコツをまとめてみました。
カボチャ(南瓜)は、ウリ科の一年草で、その果実を食用します。原産はアメリカ大陸とされ、トウモロコシや豆の栽培より遥に昔、今から8千年以上も前に栽培されていた痕跡が中央アメリカで発見されたとか!。日本には、16世紀前半、鉄砲やキリスト教が日本に伝来したのと時を同じくして、やはりポルトガル人がカンボジアからカボチャを持ち込み、豊後(大分)の大名に献上したのが最初と言われています。カボチャという名前も、その由来は諸説ありますが、カンボジアのポルトガル語(カンボジャ)から付いたとされています。
実は、カボチャの栽培では、キモもコツも、書くことがほとんどありません(汗)。草にだけ負けなければ、あとは放任栽培でも、ちゃんと実が生ります!。ただし、本当に全く何もしないと、梅雨明けの日差しで焼け付いたり、虫に齧られてイボやアザだらけの表皮になってしまうので、最低限の気配りだけは必要です(笑)。




カボチャの種の発芽率は高いため、気温が上昇してから畑に直播きする方が、育苗する手間が省け、楽です。長野盆地でも、5月以降になれば、畑への直播きも可能です。
ただし、信州では、お盆には天ぷらを揚げて仏壇に供える風習があり、カボチャの天ぷらも欠かせません!。カボチャは、収穫してから1~2週間ほど追熟させた方が美味しくなるので、8月初旬には初収穫を迎えたいため、3月下旬~4月上旬にポットに種を蒔いてビニールトンネルで保温育苗し、5月上旬に定植します。
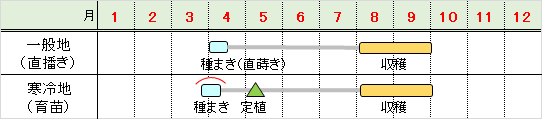
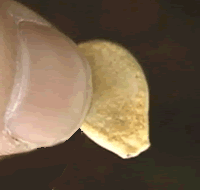 ポット種まきの場合も、畑に直播きする場合も、私は種が勿体ないので、1か所に1粒蒔きします(笑)。ただし、新しく購入した種なら相当な高確率で発芽しますが、2年目はまだしも、3年目となると発芽が結構怪しくなりますので、ご注意ください(→【種の寿命】買った種は何年目まで芽が出るのか?)。カボチャの種を土に埋める際には、ヘソ(尖った方)を下に向けて、1センチほど覆土し、軽く手で押さえてから潅水します。
ポット種まきの場合も、畑に直播きする場合も、私は種が勿体ないので、1か所に1粒蒔きします(笑)。ただし、新しく購入した種なら相当な高確率で発芽しますが、2年目はまだしも、3年目となると発芽が結構怪しくなりますので、ご注意ください(→【種の寿命】買った種は何年目まで芽が出るのか?)。カボチャの種を土に埋める際には、ヘソ(尖った方)を下に向けて、1センチほど覆土し、軽く手で押さえてから潅水します。
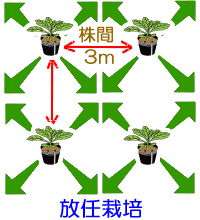 育苗した苗は、本葉が4~5枚になった頃に、畑に定植します。
育苗した苗は、本葉が4~5枚になった頃に、畑に定植します。
カボチャは、スイカとは比較にならないほど枝葉が広がるので、露地栽培では、株間は3m以上開けて、放射状につるを伸ばして放任栽培にするのが基本です。
しかし、都会で広いスペースが確保できない場合は、支柱でトンネルを作ってネットを張り、「空中栽培」にします。しかし、そこまで資材と手間を掛けるとなると、スイカならいざ知らず、カボチャだと買った方が安いということになり兼ねません…(汗)。
そもそも、カボチャの栽培で管理が必要か否か?。もちろん、最低限の管理は必要だし、した方が良いに決まっているのですが、4~5本も株を植えたなら、全部の株の整ツルや芽欠き、人口受粉までするのは、相当な手間です…(汗)。畑がスペース的に余裕があるなら、私は放任栽培で構わないと思っています。畑の周りに広い土手や畔(あぜ)があるなら、その脇に苗を植えて、伸びてきたツルを土手の方に蹴飛ばしておけば、勝手に土手を覆いつくしてくれます(笑)。特に丈夫な在来種や固定種であれば、草にも負けません!。人口受粉などしなくても、必要な数の実はちゃんと成りますし、逆に成りすぎることもありません!。中には、病気にかかってしまう株も出てきますが、数は沢山採れるので、態勢に大きな影響も与えません(笑)。品種改良された高い種のカボチャだと、草に負けてしまうので、藁マルチを敷いたり段ボールを広げるなどして、草除けは最低限必要ですね。
しかし、都会の家庭菜園では、さすがにそうはいきません(汗)。貴重な1苗か2苗を、ちゃんと育てて、確実に美味しいカボチャを収穫したいと思うと、ちゃんと管理した方が良いに決まっています!。
出来るだけコンパクトに栽培したいなら、西洋カボチャは、親づると1本の子づるの2本仕立てにします。日本カボチャは、親づるを4-5節で摘芯して、子づるのみ4-5本仕立てにします。坊ちゃんなどのミニカボチャは、放任栽培にします。なお、畑のスペースに余裕があり、複数以上の株を栽培するなら、西洋カボチャや日本カボチャも、放任栽培で特に問題はないと思います…(汗)。
まず、つるが1メートルも伸びないうちに着果した実は、勿体ないですが摘んでしまいましょう。まずは、株を大きく育てるのが先決です。したがって、つるが2メートル以上に伸びてきたら、人口受粉の作業を始めます。
 受粉作業は、通常は昆虫たちがしてくれますが、放っておくと、どうしても着果せずに、小さい実のまま黄色くなって落ちたり、茶色く腐ってしまう果が出てきます。株数が多ければ、それでも最終的に収穫数は合うのですが、株数が少ないと余計に受粉に失敗しやすいので厄介です(汗)。そこで、確実に着果させるために、人口受粉を行います。花が開いている午前中に、花の下が膨らんだ雌花の柱頭に、摘んだ雄花の葯(やく、雄しべの先端の花粉の入っている部分)をこすり付けます。
受粉作業は、通常は昆虫たちがしてくれますが、放っておくと、どうしても着果せずに、小さい実のまま黄色くなって落ちたり、茶色く腐ってしまう果が出てきます。株数が多ければ、それでも最終的に収穫数は合うのですが、株数が少ないと余計に受粉に失敗しやすいので厄介です(汗)。そこで、確実に着果させるために、人口受粉を行います。花が開いている午前中に、花の下が膨らんだ雌花の柱頭に、摘んだ雄花の葯(やく、雄しべの先端の花粉の入っている部分)をこすり付けます。

着果させる数は、通常は1株に4~5個くらいが目安。成りすぎた場合は、変形果や未熟果から摘果します。ミニカボチャは放任で構いません。
 着果した実が土に触れていたり草に埋もれていると、虫に齧られ、その齧った後が盛り上がって、表面が凸凹した見難いカボチャになってしまいます。着果が確認できたら、実の下に藁や発泡スチロール、段ボール等を敷いて、草除けを兼ねて果の表面が土に触れないようにしてあげましょう。
着果した実が土に触れていたり草に埋もれていると、虫に齧られ、その齧った後が盛り上がって、表面が凸凹した見難いカボチャになってしまいます。着果が確認できたら、実の下に藁や発泡スチロール、段ボール等を敷いて、草除けを兼ねて果の表面が土に触れないようにしてあげましょう。
また、果の同じ面だけ下を向いていると色が付かないので、肥大化してから最低1度は「玉返し」をしましょう。天地をひっくり返すほどのことは不要で、地面に付いている部分が少し横を向く程度に、座りを直してあげれば十分です。
梅雨明け後の、急な気温の上昇と強い直射日光により、肥大化した実が焼け付いてしまうことがあります。葉に覆われていればよいのですが、危なそうな実を見つけたら、抜いた草などを頭に載せて、日除けしてあげましょう。
収穫は、受粉から日本カボチャで30日ほど、西洋カボチャでは40日~50日と言われています。人口受粉していれば、受粉日もはっきりしますが、それでも幅があります(汗)。やはり、収穫時期の判断は、果の状態を見極めるしかありませんね!。
カボチャは熟してくると、表面のツヤが褪せて、果実とツルを繋いだヘタの部分が緑色から茶色と緑の縞模様に変わり、やがて白っぽくコルク化します。ある程度コルク化し、爪を立てた跡がしっかり残る様になれば、収穫適期。
ヘタを切って収穫し、風通しのよい日陰に置いて、2週間ほど追熟させたら食べごろです。カボチャは追熟させることで、でんぷんが分解されて糖分に変わり、甘みが増してホクホクとした食感になります。後は、ネズミに齧られない様にして、土蔵や物置で保存すれば、年内いっぱい貯蔵できます。なお、ミニカボチャは、収穫後すぐでも美味しく食べられますよ!。
沢山採れたカボチャは、土蔵や物置に仕舞って貯蔵します。年内に食べきれば、凍みる心配もありません。問題は、ネズミです…(汗)。
田舎では、物置や畑の納屋に仕舞っておいたはずのカボチャが、取りに行ってみたら、タネしか残っていなかったなんてことはざらです。殺鼠剤(ネズミ駆除剤)を隣に置いておいても、カボチャだけ食べられてしまうので、役に立ちません…。ネズミに齧られない、丈夫な木箱や、プラスチック製のケースやカゴなどに入れて保存しましょう。
ちなみに、ネズミ除けには、枯れたシソの枝が効くと言われています。種が散らかるので家の中には持ち込めませんが、畑の納屋などで保存する場合は、カボチャの下にシソの枝を敷いたり、上に枝を掛けておくと、多少は効果がある感じです…(笑)。
![]()